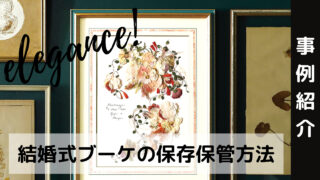- ポストコロナ時代のブランディングとは?
- 【ブランド戦略】人は、ストーリーに心を動かす
- 【原理原則】生活者をその気にさせるブランドストーリー
- 【ブランド戦略】差別化が難しい時代にこそ、力を発揮する
- お客様と社員の「共感」を生み出す装置 ~共感が人々を動かす~
- 【ブランド戦略】ストーリーが強い記憶に
- 「脱・価格競争」その実現のキーワードとは?~ブランドは低価格に代わる付加価値~
- 【ブランド戦略】誰にとっての「いい商品」なのか
- 【ブランド戦略】商品・サービスの見せ方を工夫する
- ストーリーは何を伝えるためのもの?信頼を勝ち取るために ~一環したストーリーが重要~
- 筋の通ったブレのないコンセプトストーリーを
- ズレのない統一感で、仕事への「誇り」を生み出す
- 社員が「誇り」を持って行動に移すために必要なものは?
- 納得感アップで、優秀社員の「定着率」を上げる ~成長実感こそが定着率向上の鍵~
- 自ら考え、決断する機会が大切
ポストコロナ時代のブランディングとは?
山梨県・石和温泉。東京からも近い、この温泉郷は県内最大規模を誇り、大型ホテルから庶民的宿まで百軒余を数えます。
ここにある老舗旅館「石和名湯館 糸柳」。
2020年春までは石和温泉旅館随一の人気旅館として数多くのお客様に慕われ、予約が途絶えることがなかった旅館も、コロナ渦によって状況が一変しました。
キャンセルが相次ぎ、緊急事態宣言下では営業を停止、業績は急速に悪化したのです。
コロナ渦で大きな影響を受けたのは、飲食業と旅行業といわれていますから、これも当然だといえるでしょう。
ただ、このままでは収益を上げるどころか、経営を続けること自体が難しくなる、倒産もあり得るかもしれない。
そんな中で「糸柳」は、足元を見直すためにも、日頃から重視していた従業員教育を、さらに強化していきました。
お客様に安心して訪れていただくためにはどうしたらいいのか、そのために従業員は何を考え、どう行動すればいいのか、お客様に喜んでいただける声がけとは、笑顔になっていただけるサービスとは、さらに「おもてなし」の本質とは何なのか。
「糸柳」は「こころ動かす、工夫がある」というブランドコンセプトを定め、トップおよび経営陣が従業員を集めた全体研修やグループ研修を繰り返し、「糸柳」全体としての「想い」の共有を徹底したのです。
つまり、「人」への投資であり、お客様のことを考え、愛されるべく工夫をしていったといえます。
同時に、お客様にとってのベストとなるように社内の仕組みを変え、また、ホームページなどのオンラインメディアを活用することによって、「糸柳」とひての発信力を高め、外部訴求を続けるようにしました。
多くの旅館やホテル、飲食店が、コロナ渦によって悩み苦しんでいる間に、「糸柳」は他社に先んじるために「攻め」に出たのです。
この「糸柳」の姿勢は、できることからとにかくやってみる、を徹底したものです。施設などのハード面への投資ができなくとも、今できることに目を向けることで、会社が大きく成長する可能性が生まれます。
コロナ渦だから、国や行政からの指導だから・・・と、やらない理由を探すのは簡単でしょう。
ただそれでは、すべてのモノの変化と進化が連続するポストコロナ時代においては、通用しないでしょう。
それよりも、自分たちが持っているものをしっかりと検証して、それを駆使してできることを見つけ、最善を尽くして取り組んでいく。
こういった発想と動きによってこそ、ポストコロナ時代に中堅・中小企業は、ピンチをチャンスに変え、存続・成長の可能性をつかめるのではないでしょうか。
一方、東京にある「ジオ・サーチ」。
地下を透視する世界初・オンリーワンの技術「スケルカ」により、地下の空洞の劣化箇所を正確に素早く見つけ、陥没事故を未然に防ぐことに貢献しています。
同社は、国連からその技術を評価されるとともに、地雷除去への協力要請もあり、オープンイノベーション的に企業を結集したNGOによるタイ・カンボジア国境での地雷除去活動でも成果を挙げました。
すでに韓国・台湾にも進出し、北米進出に向けたプロジェクトの準備も進めています。
また同社は、地上と地下の情報を結合して3Dマップ化するデジタル技術を新たに開発しました。
これにより、グーグルマップをも超越するような地下を可視化できるマップの利用が可能となり、インフラ事業者の設計と施工において圧倒的な工期の短縮と大幅なコスト削減を実現します。
以前から、国内のインフラ業界では高い認知度があった「ジオ・サーチ」ですが、さらにこれまで接点のなかった業界とも協働することで地下の新たな可能性を開拓し、世界中にこのシステムと「ジオ・サーチ」という名前を響き渡らせる日も近いことでしょう。
このように同社は、多くの企業や人に、「地下」というフロンティアの価値を気付かせるべく、ブランディングに取り組んでいます。
【ブランド戦略】人は、ストーリーに心を動かす
この「糸柳」と「ジオ・サーチ」の例は、ポストコロナ時代に企業が参考にすべき、伸び続けている事例といえます。
「糸柳」は、人材育成による「もてなし」というソフトの工夫で対応し、よりレベルの高い満足感を提供できるように進化を遂げ、他社との差別化を推進しました。
また「ジオ・サーチ」は、既存のインフラ事業から視点を変え、新しい技術を生み出すことによって、国内だけでなく、世界から注目される自社づくりを進めているのです。
ブランドとは、ポジティブなイメージを持たせることに成功している会社やモノだと言えます。
ポジティブなイメージとは、「スポーツシューズならNIKEが一番」とNIKE
で働く社員が思うことと同時に、多くの生活者からのNIKE信仰ともいえるような強いシジを得ること、どちらを買うか迷ったときの決め手になるもの、「ベンツ=高級車、成功者が乗る車」と社内外の誰もが連想すること、または漠然とした親しみや好感などのゆるい支持まで、すべてを含んだ前向きなものを指しています。
企業にとって、お客様にポジティブなイメージを持ってもらうこと、また、自社の社員に誇りを持ってもらうことは強力な武器になります。
そして、ブランディングを突き詰めれば、「多くの人々にポジティブなイメージを持ってもらうための活動」ということなのです。
「いいね!」と共感してもらい、数ある企業、商品サービスの中から選んでもらうために行うことすべてが、ブランディングだと考えてください。
行動指針、ロゴ、デザイン、メディアを通じた広報活動、研修、人事制度といった、すべてのことがそうです。
そして、ブランディングにおいて大切なことは、人が感動したり、興味を持ったり、共感したりするブランドストーリーを確立していくことになります。
ブランドを伝えるべき対象には、お客様や取引先、パートナー企業などの外部関係者だけでなく、当然社員も含まれます。
これは事業を動かすのも、商品・サービスをお客様に売るのも自社の社員たちだからです。
社員をおろそかにして企業成長などあり得ませんし、ブランディングを成功させることはできません。
その理解を深めるためにも、まずは様々なケースを紹介しながら、事業、人材、組織において、ブランドストーリーがどのように武器になっていくか、理由を説明していきましょう。
【原理原則】生活者をその気にさせるブランドストーリー
同じようなデザイン、素材、価格の服AとBを目の前に置かれて、「どちらかを選んでください」と言われたとします。
あなたは、どうしますか?何となく気になったほうを選ぶことはできるでしょう。
でも、選んだ理由を明確に答えてくださいと言われたら、困ってしまうと思います。
なぜなら、両者の差別化が難しいからです。
では、Aの服は「この道30年のベテラン職人が丁寧に縫製しているので、縫い目がほつれることがなく、丈夫で長持ちする」と聞いたらいかがでしょうか。
それならほとんどの人がAを選ぶはずですし、選んだ理由も明確に答えられます。
普段、強く意識していませんが、自分の購買行動をあらためて振り返ってみると、モノを買う決断をするとき、そこには往々にして「自分をその気にさせたストーリー」があることに気づくはずです。
言い換えれば、その気にさせるストーリーをつくることが、モノを売る鉄則だといえるわけです。
【ブランド戦略】差別化が難しい時代にこそ、力を発揮する
ポストコロナ時代とはいえ、日本は経済的に成熟し、情報技術が進んだおかげで、日常生活はとても便利に、快適になっています。
しかし、モノやサービスを提供する企業にとっては、機能や技術力だけで他社製品やサービスとの間に差をつけることが非常に難しい状況でもあります。
量販店にズラリと並んだテレビを見ても、同じような価格帯のものであれば、画質をはじめメーカーごとの差などほとんどわかりません。
よほど突出した技術を開発したり、アイデアをひねり出したりできなければ、他社の製品・サービスに大きく水をあけることは至難の業なのです。
しかも、情報はすぐに広がり真似されてしまうため、先行者としてのアドバンテージも長くは続かないのが現実といえます。
このような市場環境だからこそ、ブランディングをすることで、他社と差別化し、共感できるイメージを根付かせることができるのです。
ただし、消費者の心を捉えるためには、魅力的なブランドストーリーがなければ意味がありません。
価格よりも品質や機能性を重視する相手に、「いかにコストを削減して低価格を実現したか」というストーリーをアピールしても、それほど購買意欲を刺激することはできないでしょう。
それでは、魅力的なブランドストーリーとは、どのようなものをいうのでしょうか?
お客様と社員の「共感」を生み出す装置 ~共感が人々を動かす~
ブランドストーリーは、関わる人々にポジティブなイメージを持ってもらうための手段です。
実は、この「ポジティブなイメージを持ってもらう」というところがポイントだといえます。
モノを売り込みたい場合、事実に基づいて、知って欲しいことやアピールしたい特徴を伝えようと努力するものです。
この行為自体は何ら間違っていないのですが、伝えた結果、相手がどのようなイメージを持ったかが重要なのです。
例えば、コロナ渦に見舞われている現在、ある飲食店に、「うちは、感染対策をしっかりしているので安全ですよ」と言われたらどうでしょう。
感染対策は、どんな飲食店もしていることなので、その一言だけでは心は動かず、格別、良いイメージを持つ決め手にはならないかもしれません。
ただ、「うちは、従業員に毎週PCR検査を受けさせたうえ、毎日の検温を欠かしません。
また、店の定員を30%にして、隣のお客様との間を4メートル空けてご案内しています」という事実に着目してストーリーを構築すればどうでしょうか。
「従業員が、そこまで意識高く安全・安心に取り組んでいるなら、衛生面だけではなくて、料理に使う食材の吟味や調理、サービスまでしっかりと行き届いているに違いない」などとイメージして「一度くらい入ってみるか」と考えても不思議ではないはずです。
このように、事実を魅力的にストーリー化することで、お客様に対して、自分たちの商品やサービス、大切にしている想いや考え方を伝え、「共感してもらう」ことがブランドストーリーのポイントだと言えます。
「共感」は、ポジティブな活動を引き出してくれるのです。生活者であれば、購買意欲が上がるでしょうし、取引先であれば付き合うことにメリットを感じて、それまで以上に良好な関係を構築することができます。
さらに、社員からの共感を得られれば、仕事に対するモチベーションが上がり、日々の生産性も向上するはずです。
【ブランド戦略】ストーリーが強い記憶に
魅力的なブランドストーリーには、相手の記憶に残りやすいという利点もあります。
少し話がそれますが、童話「ウサギとカメ」から得られる教訓は何ですかと聞かれたとき、多くの人が「油断大敵」とか「着実にコツコツ行うことが大切」などと答えられるはずです。
子供の時に読んだりきいたりしただけであったとしても、です。
理由は、物語になっているからです。箇条書きで、「油断すると痛いめにあう」とだけ書かれていても記憶に残りにくいですが、ゴールの手前でウサギが昼寝をしてしまい、その間にカメが追い抜いたという物語であれば、理解しやすく、前後の話のつながりから記憶にも残りやすくなります。
同じことがブランドストーリーにもいえます。
たとえば薬などでも、膝の傷みをやわらげる成分名を前面に出して商品をアピールするよりも、「開発者が親の膝の傷みを何とかしてあげたいと強く思い、研究に打ち込んだ結果、誕生した商品で、使用し続けている親は、今では元気にゴルフを楽しんでいる」といったストーリーにしてアピールしたほうが、生活者には覚えてもらいやすくなります。
魅力的なブランドストーリーによって、良いイメージを強く記憶に残すことができれば、相手の中で優先順位が高くなる効果も期待できます。
数ある競合商品のサービスの中で、真っ先に思い出してもらえるようになる、これこそブランディングの目的の一つだといえるでしょう。
「脱・価格競争」その実現のキーワードとは?~ブランドは低価格に代わる付加価値~
機能や技術による商品・サービスの差別化が難しい時代になっています。
そのため、企業は涙ぐましい努力を重ねて、無駄なコストを削減し、価格を下げることでライバルに差をつけようとしてきました。
そのおかげで、経営はかなりスリム化され、効率化が進んだのも間違いありません。
また、コロナ渦による各企業の積極的な改革路線で、そのデフレ状態は、さらに続くことでしょう。
たとえば、「日本マクドナルド」が販売する「ビッグマック」。その価格は対やギリシャよりも安く、スイスに比べれば50%OFFほど。
日本では、どの先進国よりもリーズナブルなのです。
この背景には、生活者の間に低価格志向が根強く定着しているからだと指摘する専門家もいます。
しかし、価格競争には限界があります。
どこまで価格を下げられるかは、企業の体力次第ですので、中小企業には非常に厳しい時代だといえます。
大企業であっても、このままではいつ行き詰まっても不思議ではありません。
ひたすらコストを削って価格を抑える戦略は、働いている社員のモチベーションまでも下げてしまう危険をはらんでいます。
日本では、働く櫃の実質賃金の低下が続き、深刻な問題となっています。この状況を変えるものこそが、ブランドです。
ブランドは価格競争から脱却する付加価値を生み出し、商品やサービス、そして企業に強さを生み出していくものだといえます。
たとえば、機械式時計を考えてみましょう。
世界的に人気の高い海外ブランドのある時計は、定価が200万円。
ところが、購入した後すぐに中古品として販売すると、買取価格が290万円になるそうです。
一方、機能性にすぐれたある機械式時計は、定価が67万円ですが、購入後、同様に中古品として出すと、買取価格は39万円にしかならないそうです。
おわかりかと思いますが、この違いはブランド力によって生まれます。
圧倒的な付加価値を持ったブランドが確立できていれば、中古品であっても、新品を上回る価格での販売が可能となるのです。
低価格化というブライシング勝負の戦略は、長続きしません。
企業だけでなく、そこで働く社員をも疲弊させるだけだからです。
ましてや、ポストコロナ時代は、コロナ渦の影響で消費が落ち込みやすく、企業の売上も打撃を受けやすいでしょう。
だからこそ、低価格に代わる武器として、企業としてはもちろん、商品やサービスへの付加価値として、ブランドストーリーを描き、ブランドの確立を考えていく必要があるのです。
【ブランド戦略】誰にとっての「いい商品」なのか
日本では、いいものをつくっていれば認めてもらえる、買ってもらえるという意識が昔から強い傾向があります。
モノづくりが経済発展を支えてきたのは間違いないことですし、技術力が高いのも疑いないでしょう。世界に誇れる伝統品なども数多くあります。
しかし、求められていないものをいいものだからと押し付けても売れるわけがありません。
たとえば、これからは電気自動車の時代となってきますが、あるメーカーの電気自動車は、重量が3トンもあります。
ただ、日本の立体駐車場には重量制限があるものが多く、なかには3トン未満とされているところもあります。
つまり、3トンの電気自動車は、この立体駐車場に停めることはできないのです。
環境問題に貢献するこの電気自動車は、走行距離を延ばすためにバッテリーの容量を上げることばかりに注力してしまったのでしょう。
しかし、これでは、立体駐車場の多い都心には適していないと思われ、購入をためらわれてしまっても仕方ありません。
生活者にとっての「いい商品」とはいえず、どんなブランドストーリーを練り上げても、成功は難しいといえます。
一つの特性を追求するあまり、プロダクトを総合的に見たときに思わぬデメリットが生まれてしまうケースは意外と多いものです。
たとえば、イマジナのクライアントでバッテリー開発を手掛けている企業があります。彼らはプロダクトをさらに活かすための、バッテリー開発のプロです。
とあるパッケージのバッテリー部分のみの相談を受けても、その背景にある生産者の想いを総合的に紐解くことで、生活者のニーズにマッチさせながら、プロダクトを完成させるコンサルティング能力にも長けた集団です。
この会社は、大手自動車メーカーなど、世界が認めている企業ですが、一般の方にはあまり知られていません。
しかし彼らのような企業が、多くのメーカーから利用されることで、これから先、生活者のニーズとかけ離れた商品をつくってしまうことが避けられるはずだと思っています。
ブランドストーリーは、伝えたい対象を明確にして、その対象に理解してもらえる方法を構築していくものです。
そのため、大前提としては、徹底した市場調査や競合分析などのマーケティングによって、お客様の顔や好みを明らかにしておくことが大切になります。
【ブランド戦略】商品・サービスの見せ方を工夫する
一方、生活者が求めている「いい商品・サービス」なのに、ブランドストーリーをうまく構築できず、売上が伸び悩む場合もあります。
その理由の一つに、その価値に「気づけていない」ケースが多々あるのではないかと感じています。
それは、長年、その事業に携わり続けているために、第三者から見ればすごいこだわりなのに、自分たちでは当たり前のこととしか思えなくなっているような場合です。
たとえば、ある魚屋では、魚が傷まないよう氷水の中に魚を入れていますが、実は、真水は使っていません。
真水だと魚が水分を吸収してふやけたようになって、おいしくなくなってしまうからです。
そのため、塩を入れて塩分濃度を調節した氷や水を使ったり、氷を入れる位置を魚の上側にしたり下側にしたりといろいろ工夫しているそうです。
さらに、塩分濃度が濃すぎると魚に塩味がついてしまうため、濃度にも徹底して気を使っています。
この魚屋にとって、これらは普通のことなので、特にお客様には伝えていません。
ただ、実践していることは「おいしい魚を食卓へ届ける」ための徹底したこだわりであり、この魚屋としての付加価値です。
これらを工夫して生活者に伝えれば、この魚屋の価値を生み出し、信頼を高める、とてもいいストーリーになるでしょう。
同様に、若者が減り、活気を失いつつある田舎であったとしても、ブランドストーリー次第で、魅力的な「秘境」に変わるのです。
いいブランドストーリーを構築するには、何が生活者の心に響くストーリーになるか、見せ方を考えていくことが大切です。
ストーリーは何を伝えるためのもの?信頼を勝ち取るために ~一環したストーリーが重要~
ブランドストーリーは、相手にポジティブなイメージを持ってもらう活動だと繰り返し述べています。
ただし、ポジティブなイメージにつながるからといって、ストーリーに「嘘」を持ち込んでいいわけではありません。
当たり前ですね。明らかな嘘でなくても、商談の場で相手に調子を合わせるため、その場限りのストーリーを話すのもNGです。
会うたびに話す内容が微妙に変わるような不誠実さは、マイナスでしかありません。
一時しのぎのつくり話など、そのうち必ずバレてしまいます。
そういった意味では、お客様と日々会う企業の営業担当者や販売担当者の一挙手一投足には、自社ブランドを悼める可能性も秘められていると自覚するべきです。
では、ストーリーとは何を伝えるためのものなのでしょうか。
それは、相手をその気にさせるだけでなく、会社が大切にしている大義や理念をわかりやすく浸透させ、共感してもらうためのツールだといえます。
会社の規模に関係なく、現在まで成長を続けてきた企業には、必ず「成長できた理由」があり、それこそが、企業としての大義です。
だからこそブランディングするためには、その大義を見直し、それをわかりやすいコンセプトと、伝えるためのストーリーに落とし込む必要があるのです。
また、ブランディングによって事業を成長させ、ブランド価値を向上させるためには、アウターブランディングとインナーブランディングを実施していくことが大切となります。
筋の通ったブレのないコンセプトストーリーを
保育園を数多く経営する「ちとせ公友会」という社会福祉法人があります。
この「ちとせ公友会」が考える保育園の役割は、「子供たちの“いま”を支え、未来のいきる力を育む場所」としています。
つまり、保育園で過ごす子供たちの時間は、人間性や人格の基礎を作り上げることにつながり、自分が何をしたいのか、それを実現するためにはどうしたらいいのかを考え、学びながら歩む姿勢を育むために役立つようにすべきだということになります。
そのために、同法人が打ち出しているコンセプトは、「考えさせるを、考える。」ということ。
これは、同法人の「これからの時代を支える、自立的な子供を育てていきたい」という想いを、子供を預かる保育士にも、子供たちの親御さんたちにも共感してもらうためのものだといえます。
また、「考えさせるを、考える。」というコンセプトには、同法人としての一貫したメッセージが込められており、保育士や親が、子供に自ら考えさせるためにどうするのが最善か、常に考え、追求する姿勢を大切にしています。
たとえば、水道で蛇口をひねることや、コップに牛乳を注ぐことも、小さな子供にとっては初体験。
「ちとせ公友会」の保育士たちは、子供から「学び」の時間を奪わないように、その初体験をそっと見守ります。
はじめて蛇口をひねるとき、左右どちらにひねるのか、どれくらいひねれば水が出てくるのか、ひねりすぎると水が跳ねて友達にかかってしまうことも、すべて自分の目で確かめさせます。
もし水で床を濡らしてしまったら、ぞうきんで拭くという作業を、また新しくさせてあげればいいのです。
それを手前で気付いた大人は、「蛇口はここまでしかひねっちゃダメ」と言って聞かせたくなるものですが、子供の失敗を未然に防いでしまうことは、機長な体験を奪うことにもなってしまいます。
子供たちにとっては、大人にとっての当たり前がすべて、貴重な初体験、新たな学びなのです。
同法人は、保育士側の教育に最も力を入れています。
保育士たちがまず「考える」ことを実践していることが何より大事です。
保育士たちへの教育が行き届いていなければ、子供たちへの教育方法にもブレが生じる可能性があるからです。
ブランディング施策を通して、子供の大事な時期をそばで支える保育士たちの教育に力を入れ、コンセプトとストーリーの浸透を徹底しているのです。
結果として、同法人の子供を預ける親御さんたちは、力強く活きる子供の将来がイメージできるようです。
このように筋の通ったストーリーをつくることによって、内部である保育士も、外部である親御さんも、共通の意識を持つことが可能となり、お互いのミスマッチは起こりにくくなるのです。
ズレのない統一感で、仕事への「誇り」を生み出す
企業理念から販促戦略までズレのない一貫したブランドストーリーは、社外にポジティブなイメージをもたらすだけではありません。
社員にとっても自分が働く会社や仕事、商品・サービスに誇りを持ちやすくなるというメリットがあります。
ブランディングがうまくいっている会社は、企業理念が浸透し、会社の大義に共感して、多くの社員が前向きに仕事に取り組むようになります。
しかしながらポストコロナ時代となった今、テレワークの実施や飲み会・交流会の自粛に伴い、社内でのコミュニケーションが激減することによって、理念の浸透や組織の強化が難しくなっています。
このような状況で、社員が自分の仕事に誇りを持つ機会も減っているのではないでしょうか。
ましてやコロナ渦の中で入社してきた新人は、埃や帰属意識を養う機会さえなかったといえるでしょう。
また、学生が会社を選ぶ基準で「社会貢献」や「やりがい」を重視している中、採用戦略の一環として、自社の大義を、社内外に訴求していくことは極めて重要なことです。
誇りを持てる環境づくりは、企業成長の急務といえます。
社員が「誇り」を持って行動に移すために必要なものは?
社員に自社への誇りを持ってもらうためには、会社が発信するメッセージや方向性を正しく理解することが前提となります。
そのうえで、会社が示す考え方に共感し、会社と同じ方向を向いたとき、社員は一体感を覚え、「この会社で自分がしていること」に誇りを持ち、自社の大義を仕事で体現するようになるのです。
一方、統一感のないブランドストーリーが蔓延すれば、社員は誇りを持つことができず、自身の仕事をないがしろにする可能性さえあります。
しかし、社員が共感できる企業理念やビジョンをつくれている企業がどれほどあるでしょうか。つくれているといっても、そのほとんどは、「どこかで聞いたことがある」ような言葉の羅列で終わっているかもしれません。
ありふれた言葉は覚えやすいかもしれませんが、その裏側に隠された会社の大切にする想いまで描くストーリーがなければ、社員の心に刺さらず、記憶にも残りません。
仮に、経営者の想いに根差した理念を構築できている会社であったとしても、伝えるべきポイントを社員に的確に伝えられているところはほとんどないのではないでしょうか。
あなたの会社の社員は、企業理念に込められた想いや考え方を正確に説明できますか?
社員の間に浸透していない理念など、どれほど立派なものであっても絵に描いた餅であって、企業経営においてプラスにはなりません。
だからこそ、社員が誤解することなく、会社が大切にしてきた想いや大義の理解を促進してくれるブランドストーリーが重要になってくるわけです。
納得感アップで、優秀社員の「定着率」を上げる ~成長実感こそが定着率向上の鍵~
企業の働きやすさを測る指標の一つとして「定着率」があります。
これは入社した人のうち一定期間後に辞めずに残っている人の割合です。
1年後に集計するか、3年後に集計するかは調査機関によって異なりますが、おおむね大企業に比べて中小企業のほうが低いのが現状です。
コロナ渦によって優秀な人材の確保が難しい昨今、せっかく採用した人には長く働き続けて欲しいのが企業の本音でしょう。
中小企業庁のデータによると、企業側が定着に有効だと考える施策の上位は、労働時間の見直し、賃金の向上、休暇制度の徹底など、労働環境の改善に関するものが多くを占めていました。
しかし、社員が考える人材定着に有効な取り組みは、少し傾向が異なります。もっとも多くの支持を集めた「興味にあった仕事・責任のある仕事の割り当て」は企業側が考える取り組みでも2番目にあがっていましたが、そのほかにも資格取得支援、技術やノウハウの見える化など、自身の成長につながる項目が上位に数多く入っていたのです。
一方、定着促進施策として企業が真っ先にあげた「賃金の向上」は、9番目という低い結果でした。社員は、成長につながる取り組みを重視する傾向にあるので、1年後、3年後、5年後といったスパンでのキャリアアッププランを見せることが有効かもしれません。
自ら考え、決断する機会が大切
このことからも社員が会社に何を求めているのか、その一端を知ることができます。社員にとって重要なのは、その会社であれば、おもしろい仕事ができそうだと思えることであり、その会社で働くことで自分が成長できると実感できるかどうかなのです。
私の感覚値ではありますが、この傾向は優秀な人材ほど強いように思います。
では、どんな会社であれば、おもしろく働けると思いますか?成長できると実感できるでしょうか?
肝心なのは、会社が成長するためにチャレンジを続けているかどうかです。
チャレンジするためには、様々な人材の知恵を集結させる必要があります。
そして、現場に可能な限り権限を与えて、スピード感を持って事業を展開していかなければなりません。
要するに、成長できる会社とは、自分の頭で考える仕事に携わる機会が多い会社だといえます。主体的に仕事に取り組むことで、仕事もおもしろくなっていきます。
しかし、成長できるからといって社員が好き勝手に動いては、企業成長にはつながりません。
そこで、会社の大義に根差した方向性をブランドストーリーで示すことによって、社員のベクトルをそろえ、一体感を醸成しながら社員のやる気を事業成長へと結びつけていくことが大切になります。