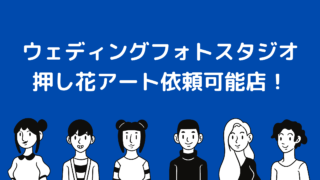- 好奇心が仕事への姿勢を変える
- 成長を促す3条件
- 企業価値を上げるか?下げるか?全ては社員にかかっている
- インナーブランディングの範囲
- 社長と社員は、時間軸が異なる。それを理解してから進めていく
- 社員の力を活かす企業経営の実践を
- 会社に誇りを持てるように、社員教育に力を注ぐ
- 社員教育にはお金と手間がかかるもの
- 就職先は、「人」を見て決めている
- 格好悪さも伝染する
- お金がもたらす満足は低いものでしかない
- 努力の証として収入に意味がある
- 正しい企業文化の育成を
- マニュアルだけで行動は規制できない
- ルールに合わせるのではなく、ルールに合わせる
- 硬直化した組織にはルールが多い
- 変化への恐れが視野を狭める
- 現状維持は衰退への道
- ストーリーづくりの大前提、会社の「大義」を見つめ直す
- コンセプトは、ブランドの独自性を表すフレーズに
- 本当にそれで伝わるか、もう一度考えてみましょう!
- 認知・理解よりも、その先の「共感」が大切
- 社内にアンバサダーを育てる
- 「人事評価」にまで落とし込むブランディングで、社員を伸ばす
- 評価基準を可視化する
- 若手社員の成長を引き出すのは、「直属の先輩」
- 「まぁ、いいや上司」こそがネック
- 「社内」と「社外」、発信内容の完全一致を追求する
- ストーリーのブレが、共感を削ぐ
- SDGsへの取り組みは、企業が持続させるもの
- 社会的責任をどう考えているかの意思表示
- 意識を変えて、人を変える。ブランディングには時間をかけて
- 浸透施策はオーダーメイドで
- ブランディング成功の鍵は、「やり切る覚悟」
- 手間暇かけるだけの価値がある
好奇心が仕事への姿勢を変える
好奇心は、人を積極的にさせます。
普段おとなしい人が、趣味のこととなると、とたんに積極的になったりします。
仕事も同じです。好奇心を持って仕事に取り組んでいる人は、常に、どうすればもっと良くなるのかを考えています。
試したいことが思い浮かべば、やらせてもらえないかと何らかのかたちで自分の意見を発信します。当然、会社阻止ですから上司・部下、先輩・後輩など様々な関係性があり、遠慮する気持ちも生まれてくるものですが、好奇心は、そのハードルを難なく超えさせてくれます。
好奇心は、やりたい仕事、取り組んでいて楽しい仕事、やることに意義を見出している仕事だから生まれてくるものです。
これらは、ブランディングによって生み出すことができるものです。
会社の将来性を示し、仕事への誇りを感じさせることで、「それをする意味」を社員が持てれば、会社で力を発揮することの動機づけになるはずです。
成長を促す3条件
人の成長を促すには、その人の能力を少し上回るミッションを与えることだといいます。
これは心理学における調査でも実証されている理論のようで、現状、さまざまな人材育成メニューの中にも取り入れられています。
この条件であれば、育てたいと思う社員のことをよく知っている直属の上司が、その社員に合った的確なミッションを設定さえすれば、それほど難しいことではないと思います。
また、この理論では、「成長」という成果を現実のものとするには、ミッションのレベル設定だけではなく、取り組む本人の「挑戦への意欲」と「目標」も不可欠だとされています。
ただ、こればかりは当人の内面から湧き出るものなので、上司だけの力ではどうしようもないことだといえます。
しかし、ブランディングを行うことで、目標を共有し、社員の中に挑戦への意欲を芽生えさせることができます。
大義から導き出したブランドコンセプトとストーリー、企業理念と連動したミッションなどは、社員に目指すべき方向性を示すことになります。
その方向性に社員が共感していれば、目標実現に向かって、自分ができることに挑戦していこうという意欲が湧くのです。
「ミッションレベル」「目標」「挑戦への意欲」という3条件が整い、成長を実感できた社員は、働くことへの充実感を抱きます。
そこからさらに、人事評価によって社員のモチベーションを後押しすれば、会社で働く理由を作り出すことができるはずです。
つまり、ブランディングとは、社員一人ひとりが持っている力を引き出して束にし、会社が描く未来像へ向かって力強く進んでいく推進力を生み出す装置のようなものだといえます。
企業価値を上げるか?下げるか?全ては社員にかかっている
私は、インナーブランディングをしっかりと行うことの重要性を繰り返し述べています。
その理由は、社員こそが自社に対するイメージを決めてしまうからです。
いや、社員だけではありません。
契約社員や派遣社員、パートやアルバイトも含めた従業員のほか、業務委託先やパートナー企業など、会社の看板を背負って、お客様と接するすべての人が、会社のイメージを上げることもできるし、下げてしまうこともあります。
事実、多くのマーケティング調査でも、生活者は、その企業の経営者や、その会社に関するメディア報道ではなく、「社員」からその企業をイメージしていると答えています。
ちょっと想像してみれば、それを当たり前のことだと気づくはずです。ショップの販売スタッフの態度が悪ければ、その店だけでなく、そのブランドへの印象も低下します。
飲食チェーン店で気分の悪くなる接客をされれば、そのチェーン店を利用しなくなったりもします。
伸び盛りの飲食店が急速に店舗を拡大していったため、スタッフの育成が間に合わず悪評が経ってしまうといったことは、よくあることです。
例えばポストコロナ時代、感染予防マスクは必需品で、さまざまな企業が開発・製造販売をしています。
あるアパレル会社も自社の持っている技術を利用して感染予防マスクを開発し、自社の直営店で販売をはじめました。
ところが、その直営店に勤める販売員は、その、自社開発の感染予防マスクを付けず、他社製のものを付けていたそうです。
自社販売員が付けない、そんなアパレル会社の感染予防マスクを買いたいと思いますか?
私なら、購入することを躊躇ってしまいます。このように,社員の行動がお客様にとっての「企業価値」「商品・サービス価値」を決めてしまうのです。
インナーブランディングの範囲
ブランドの伝道者には、社員だけでなくアルバイトや業務委託先も含まれているのに、そこまで徹底してインナーブランディングを実施している企業は一握りなのではないでしょうか。
その好例といえるのが、「星野リゾート」でしょう。
体験型リゾートとして絶大な人気を誇る「星野リゾート」では、フラットな組織づくりを推進して、そこで働く人全員に「経営者の視点」を持って欲しいと願っています。
そのために、それぞれの旅館の売上や稼働率、顧客満足度をオープンにして、スタッフ一人ひとりが状況を理解したうえで、発想して、判断し、行動できるように導いています。つまり、スタッフの「自立化」をめざしているのでしょう。
また、一人ひとりが自立すれば、チームとしての役割も理解できるようになり、より良いコミュニケーションができるようになるとしています。
もちろん、パートやアルバイトにも厚い研修を実施して、「星野リゾート」としての「おもてなし」のレベルアップに努めています。
こうして育てていく人材は、「星野リゾート」のホテル・旅館のスタッフとして、お客様が喜ぶ「おもてなし」を、日々、革新できるようになり、ホスピタリティのプロフェッショナルとなっていくのです。
そして、お客様をもてなすスタッフ全員が、「星野リゾート」の「大義」の表現者としての誇りを持って行動しています。それができるのは、「星野リゾート」が、ブランドに影響するのは誰かということを正確に理解して、人材育成に本気で投資しているからです。
インナーブランディングを行う際は、徹底すること。
中途半端な実施は、失敗に繋がるだけです。
自社のブランドを作り上げるのは、お客様や取引先と接する全てと考えるようにしましょう。
社長と社員は、時間軸が異なる。それを理解してから進めていく
経営者と社員では見ている風景が違う。
経営者の中には、お題目を掲げれば、社員がみんな同じ方向を向くと錯覚している人がいます。
企業理念と行動指針をオフィス内の壁に貼り、毎日、朝礼のときに復唱することは、言葉を暗記するには効果がありますが、本来の目的はその内容を理解し、実践してもらうことのはずです。
経営者は、常に会社が存続・発展していくためにはどうすればいいのかを考えています。
3年度、5年後、10年度を見据えながら、逆算して今何をすべきか見出すために、人的ネットワークを広げ、セミナーや経営者同士の懇親会などに参加して知識を更新する方もいるでしょう。
一方、社員はそれぞれ与えられたミッションをクリアするために、頭を使い手足を動かしています。
彼らが見ている視界は、経営者に比べれば、ずっと狭いものなのです。
それが良い悪いではなく、そこに焦点を合わせなければ、日々の業務を前へ進めていくことができないからだといえます。
つまり、経営者と社員では、そもそもの目線が異なるのです。
経営者が企業理念や行動指針として掲げたものからくみ取れるものと、社員がくみ取れるものには、差が出て当たり前なのです。
経営者は、「社員は、自分自身とはまったくの別人格なのだ」と、しっかり認識する必要があります。
また、命令によって遵守するよう求めることにも限界があります。
表面上はさておき、命令に従う人は一部に限られます。
その一部のうち、100%実践できるのは、さらに一握りの人でしかありません。
心から守ろうと思っていない限り、命令の効力は時間の経過とともに薄れていくものです。
だからこそ、ブランドストーリーなのです。経営者が考えていること、描いている未来を浸透させるには、理解し、共感できる物語が必要です。
社員の力を活かす企業経営の実践を
社長のワンマン経営ですべてのことがトップダウンで決まっていく会社は、社長の器の限界が会社の限界になってしまいます。
それ以上に成長するためには、自分より優秀な社員、賢い社員の力を結集し組織として活動していくしかありません。
経営者と社員が別人格であるということは、当たり前ですが、持っている能力や強み、弱みも違うということです。
ある能力については、もしくはある作業については、社長を上回っているという社員が、社内にはいくらでもいるはずです。
ブランディングを行うことで、そのような社員の力を、さらに活かそうとする企業経営を実践することも可能です。
会社に誇りを持てるように、社員教育に力を注ぐ
社員は、会社を映し出す鏡です。
会社が教えた内容以上のことを自ら考え実行してくれるような優秀な人材は少数であり、圧倒的多数は、会社が教えたことをそのまま実践しようとします。
もちろん下位1割ほどは、教えたことの何文の一しか実行しようとしませんが。
こうした圧倒的多数の社員も、会社の「人材」として戦力化してこそ、強い企業に進化することができます。
そのためには、インナーブランディングによって、会社のコンセプトやストーリーに共感させ、自ら考えて動けるようにしていく必要があります。
インナーブランディングに成功した企業の一つに「オタフクソース」があります。戦後、広島のいちソースメーカーからスタートして、今や全国のお好み焼き店の約半数で使われるまでに成長している優良企業です。
あるとき、同社の社員に、「どこのお好み焼き店がおいしいですか?」と尋ねたことがあります。
でも、返答は「お答えできません」というもの。
お好み焼きのソースをつくっているメーカーだから、さぞや詳しいだろうと思いましたし、公に宣伝するわけでも、周りにお好み焼き店の人がいるわけでもありません。
ちょっとした雑談でのことなので、差し支えないだろうと思ったのですが。
お好み焼きソースメーカーとして後発だった同社は、お好み焼き店を地道に回り、商品改良のヒントや販売のヒントをもらいながら成長してきたという歴史があります。
社員は、社員教育などを通じてこのことを理解し、お好み焼き店に尊敬と感謝の念を抱いているからこそ、お店に優劣をつけるようなことはできないと断ったのだと思います。
インナーブランディングによって、社員は会社や自分の仕事に対して、これほどまで誇りを持てるようになるのです。
社員教育にはお金と手間がかかるもの
多くの企業が研修の中で、会社の歴史や理念について教えているはずです。
それが伝わっていないのは、理念そのものがわかりにくかったり、それを伝えやすくするためのブランドストーリーがなかったり、その構成を練り切れていなかったりするからかもしれません。
また、インナーブランディングは、研修だけで達成できるものでもありません。
日々の朝礼や現場での指導においても一貫性のあるメッセージを発信していくことが欠かせませんし、人事業過制度も連動したものに作り替えなければならないでしょう。
ブランディングのための準備がひと通り整ったあとも、定期的に浸透具合を確かめ、状況に応じてアップデートしていくことも必要になります。
インナーブランディングを通じて社員を育成するには、資金も手間も、時間もかかるものなのです。
それを後継者の育成も一緒です。事業承継の段階になって後継者がいないと慌てても仕方ありません。
後継者がいないのは、時間をかけて後継者を育成するために投資をしてこなかった経営者の責任なのです。
就職先は、「人」を見て決めている
入社間もない社員に話を聞くと、多くの人が最終的な入社の決め手は「人」だったと話します。
面接のときに対応してくれた人事部員の人柄がよかった、OB訪問で会った先輩が楽しそうに働いていた、面接中、自然体で話せたなど、出会った人に、何らかのインスピレーションを感じて、この会社ならやっていけそうだと思えたことが大きかったというのです。
人は、自分の考え方や性格など共通したところのある人に親近感を抱きやすいものです。
そして、社員は会社を映し出す鏡ですから、人事戦略としてそれまでの社風と異質なタイプの人材を採用しようと頑張っても、結局入社してくるのは同じようなタイプの人だったというオチになりがちです。
仕事に対する取組み姿勢は事業内容などともリンクしてくるようで、ルーティンワーク中心の企業であれば、変化よりも同じことをコツコツ積み上げていくのを得意とする人が集まってきたりします。
逆に、変化を楽しめる人材を採用したければ、会社自体に変化をチャンスととらえる風土や新しいことに挑戦できる機会を醸成する必要があります。
格好悪さも伝染する
働くことに対する低い価値観を持っている者同士は、集まりやすいものです。
「仕事は生活費を稼ぐためだけにするもので必要最低限のことだけしていればいい」と思っている人の周りには、同じような考えの人が吸い寄せられてきます。
このような働き方をしたいと考えるのは本人の自由なので何か言うつもりはありません。
ただ企業としては、社員にもっと前向きに仕事に取り組んでもらいたいというのが本音でしょう。
とはいえ、お金に対する不満をいつも言っていたり、できないことの言い訳などネガティブなことばかり口にしたり、そんな格好の悪い人のところには、やはり格好悪い人が集まってきてしまうのです。
しかしながら、人事異動によってこれを防ごうとすると、かえって悪い結果を招いてしまうこともあります。
人は基本的に自分に甘い生き物ですから、すぐ近くで楽に働いている社員、気ままに仕事をしている社員がいれば、そちらに惹かれて行ってしまいがちだからです。
根本からこの流れを断ち切り、改善していくには、ブランディングによって会社の大義や行動指針の浸透を促進し、社員の意識から変えていくほうが、遠回りのようで一番の近道なのかもしれません。
社員自身が働く意味を見出し、仕事に対して前向きに取り組めるようになれば、その姿に共感する人たちが集まってくるようになります。
どうせ、「類は友を呼ぶ」のであれば、少しでも会社の考え方に共感してくれる人を集めたほうが会社の力になるはずです。
お金がもたらす満足は低いものでしかない
お金に関する面白い調査結果があります。
それは、年収が一定額を超えると満足感がほとんど上がらなくなるというものです。
その額は500万円であったり、800万円であったりと、蝶さによって多少のバラつきはありますが、ある金額を境に満足度がガクっと下がるところは共通しています。
経済的に豊な国の幸福度が、実はそれほど高くないというデータもあります。
2020年時点の名目GDP(国内総生産)のトップはアメリカで、2位が中国、日本は3位にありますが、国連が取りまとめている「ワールド・ハピネス・レポート」の2021年版によると、幸福度のランキングはアメリカが19位、日本が56位、中国は84位とものすごく低いのです。
また、モノを手に入れる喜びにも上限があります。生活に必要なものがひと通りそろうまではモノを買うたびに喜びや満足感は膨らんでいきますが、必需品がそろったとは一時的な満足感しか得られなくなるそうです。
考えてみれば、欲しいものがある時には、手に入れるまでが楽しいのであって、手に入れてしばらくすると持っていることが当たり前になり、満足感は大きく下がってしまうものです。
収入が増えれば嬉しいのは当然でしょう。
しかし、上がったときの満足感は長続きせず、すぐに「もっと欲しい」と思うようになり際限がないのも事実です。
そのため、働く目的を収入に置いている人は、常に、今よりも高い収入がもらえる会社を求めて転職を繰り返すことになります。
現在は人手不足ですから優秀な人材を確保するために、それなりの収入を保証することは間違いではありません。
しかし、一度入社した社員に長く活躍してもらうことを前提とするなら、収入だけで釣るのは間違った採用戦略だといわざるを得ません。
努力の証として収入に意味がある
お金に関する調査にもう一つ面白いものがあります。
高収入を獲得した成功者は、自分がそれまでに重ねてきた努力の結果としての収入に高い満足を感じるというものです。
つまり、高収入は、多くのことを成し遂げてきた証だから現在の地位をつかむまでにどれほど苦労があったとしても、大きな満足感につながるというのです。成し遂げたことの中には、当然仕事も含まれています。
このことからも、打ち込むだけの価値ある仕事と、それを成し遂げたという達成感を得られる環境が人の心をつかむことがわかります。
だからこそ、金銭的報酬だけに頼るのではなく、インナーブランディングによって会社の大義に共感する人材を採用し、働く目標を明確に示しながら教育制度をリンクさせることで目標達成を支援していく。
そして、その目標を成し遂げた人を正当に評価する人事評価制度で満足感を高めていくという好循環を生み出すことが重要なのです。
正しい企業文化の育成を
昨今、技術大国ニッポンを支えてきた老舗メーカーの不祥事が立て続けに発覚しています。
たとえば、欠陥エアバッグ問題で、超優良メーカーだった企業が、民事再生法の適用を申請したことは記憶に新しいでしょう。
この自動車部品メーカーは、自社のエアバッグに不具合があることを認識しながら、事実を隠して数年間にわたって製造販売を続けます。
そして、アメリカでの大規模なリコールに発展して、負債額は1兆円を超える規模となり、没落したのです。
こういったニュースを耳にするたびに、企業文化として根付くものは、正しいものや素晴らしいものに限ったことではないのだと思わずにはいられません。
不正が行われていた企業の社員の中には疑問を感じる人もいたはずですが、入社したときから上司に「これでいい」と教えられていくうちに、自分で判断することを放棄し、「これでいいのだ」と思い込むようになっていったのでしょう。
出世や上役、同僚たちとのしがらみから、わかっていながら口をつぐんでいる人だっていたはずです。
そのような人たちにとって、「このやり方が企業文化として根付いている」という事実が、不正を正当化する免罪符になっていたのかもしれません。
現在、コンプライアンスは企業経営を考えるうえで無視することのできない重要な要素になっています。
情報化社会となった今では、どこの企業も個人情報の取り扱いや情報漏洩に神経をとがらせています。
しかし、ITシステムによって防げるものは一部でしかなく、情報漏洩の半分以上は誤操作や紛失、管理ミスといた人的ミスが原因です。
人間ですから、ミスをすべてなくすことなどできないでしょう。
とはいえ、それでも、社員の意識を変えることで大きく減らすことは可能なはずです。
ただ、社員の意識を変えるためにといっても、単に、ものごとをルール化するだけでは、いい結果は出ないでしょう。
ルールで縛ろうとしても、結局、社員はそのルールの奥底にある背景を理解せず、それに引っかかる手前のことでこなそうとするだけです。それでは、まったく意味がありません。
大切なのは、社員に「何のためのルールか」ということをわからせることです。
会社の大義に共感する人を社内に増やし、企業文化によって、組織をマネジメントできれば、前述した自動車部品メーカーのような事件は、起こるはずもありません。
マニュアルだけで行動は規制できない
過度なマニュアル化は、社員の思考を停止させ、テンプレート的な仕事しかできなくさせることもあり得ますので、それも危険です。
また、マニュアルを用意するだけで、みんながその通りに動いてくれれば手間はありませんが、そうではないから、「バカッカー事件」などというものは発生してしまうのです。
従業員が冷蔵庫に入っている画像をSNSにアップして炎上してしまい、店舗が閉鎖に追い込まれたのではたまったものではありません。
社員が、会社のルールを守らなければならない理由を理解して、不正を不正だと指摘できる強さを持つには、それを支えてくれるよりどころが必要です。
ブランディングは、それを社員の心の中につくってくれるものだといえます。
だからこそ、このポストコロナ時代は早急にインナーブランディングを実施して、社員が会社の大義を軸に自ら考え、正しい動きができるようにしていかなければなりません。
ルールに合わせるのではなく、ルールに合わせる
日本人はルールをつくのが本当に好きです。
学校には明らかに必要とは思えないような校則があふれ、メーカーでもグローバルスタンダードを上回る自社規格を設けて自らを縛ろうとします。
その結果、自分の首を絞めてしまい、データ改ざんなどというお粗末な事態を引き起こしていたのでは意味がありません。
なぜ、これほどルールをつくりたがるのでしょうか。私見ですが、安心したいのだと思います。
ルールさえ守っていれば、やるべきことはやっていると考えるのではないでしょうか。でも、この考え方はとても危険です。
ルールを守ることばかりに終始して思考が停止してしまい、ルールをつくった本来の意図を忘れてしまう危険性があるからです。
ルールとは「この一線を越えたらヤバい」という境界を設定するものであって、本来それを守っていればいいというものではありません。企業においては理念や目指すべき未来を実現し会社が成長していくためや、組織として機能するためなど、最低限守るべき基準としてルールが設けられます。
だから、本当は社員の目線は理念や目指すべき未来へ向けられているべきなのですが、ルールばかりが強調されるとルールを守ることが目的化してしまいます。
これでは本末転倒です。
たとえば、労働時間を短縮するため1ヶ月の残業時間に上限を設け、そのルールを徹底しようと、夜18時以降は社内の証明が落ちるように決めたとします。
しかし、会社として本来求めるべきは、生産効率を上げた結果、残業が減るという状況のはずです。
この目的を見失ってルールを守ることだけが目的となると、結局社員が仕事を自宅に持ち帰るだけで労働時間の短縮にはつながりません。
硬直化した組織にはルールが多い
また、ルールが増えてがんじがらめになると、組織は硬直化してしまいます。
ポストコロナ時代は、スピードや変化が求められるものなのに、手続きばかり多くて物事がなかなか前に進まないという事態を招くのです。
そして、ルールから少しでも外れてしまうと「ダメだ」とストップがかかり、生産効率が下がります。
形骸化したルールを守るためにビジネスのスピードを遅らせることなど、何の意味もありません。
硬直化した組織では、社員自らが考える仕事も減っていきます。それは、会社の魅力が減っていくことと同義だと思うのです。
優秀な社員ほど、自ら考え、挑戦できる環境を求めます。
彼らを会社につなぎ止めておくためにも、ルールに頼った経営は控えるべきです。
ブランディングによって、企業の大切にする想いの浸透を図るとともに、ルールの上位概念として大義があるということを社員にあらためて理解してもらうことはとても重要なことだと考えます。
変化への恐れが視野を狭める
経営者の仕事は、会社の進むべき道を示すことです。
どのような戦略に基づいて会社を成長させていくのか、会社はどこへ向かっていくのか。
画を描いて、社員を導いていく仕事は、他の誰でもなく経営者にしかできないからです。
しかし、視野が狭くなっていては本来見えるものも見えなくなってしまいます。
たとえば、業績が好調に推移していると、現在の戦略の延長線上でしかものを考えなくなりがちです。うまくいっているものを変えるのは、怖いと思うからでしょう。
その恐怖にとらわれた時点で、視野は狭まっているのです。これは延長線上以外にある可能性を自ら除外してしまう危険性をはらんでいます。
経営者は、変化を恐れてはいけません。
長く継続し、発展し続ける企業は、事業の幅を広げたり、どこかで大きな方向転換をしているケースが多いものです。
それは、どんな事業にも寿命があるからだといえます。
たとえば、インターネット販売ビジネスの急速な普及によってリアル店舗を凌駕したプラットフォーマーにも、今、変化が訪れています。技術の進歩によって、自社のECサイトを簡単につくれる時代になったことで、各メーカーがECモールから離脱する動きが出てきています。
さらに、プラットフォーマーが、ECモール内でブランドの模倣品を流通させてしまえば、そのオリジナルブランドは、ECモールでの出店を取りやめます。
つまり、時代の波に乗ったことで、利益や流通の独占をしようとしたプラットフォーマーの姿勢は、長続きしないということです。
プラットフォーマーのような形態をとる企業は、今後も存続していくでしょうが、展開を見直し、方向転換をしていかなければ、競合が増えていく中で、独占を続けるのは難しいかもしれません。
現状維持は衰退への道
経営者は企業を永続させるためにも、事業の「現状維持」という発想を捨てなければなりません。
現状維持という考え方は、次第に時代から取り残されていくものであって、そのままでは現時点での売り上げや存在感を未来にわたって保つことなど不可能なのです。
アパート・マンションの建設管理の大手・大東建託が100%出資する子会社「ガスパル」という会社があります。
同社は、大東建託が建設するアパート・マンションのガス販売および設備工事を請け負っていますので、安定経営を続けています。
ただ、同社は現状に満足してはいないのです。
インフラという安定事業にと胡坐をかいて現状維持をするのではなく、社員が一丸となって、「ワクを越えると、セカイは広がる。」というコンセプトの下に、エネルギー事業を展開すべく、アイデアを生み出しながら、新しい挑戦をしています。
そして、人材教育に多大な投資をすることによって、社内にアンバサダーを増やし、社員が自社にプライドを持てる環境をつくっているのです。
さらに、自社のポテンシャルを信じて、お客様との信頼関係を築き、果敢に挑戦することによって事業の幅を広げて、地域と社会に貢献ができる総合エネルギー会社への道を進んでいるのです。
「現状維持は衰退への道」だと認識すれば、変化することを恐れなくなります。狭まっていた視野も広がり、将来にわたって成長していくための選択肢も増えるのです。
現状を維持するという守りの発想から、挑戦するという攻めの発想へ変わることで、社内にも活気が生まれます。
このような変化を社内に生み出すには、何よりもまず経営者が現状維持という考え方を捨て、ブランディングに臨む必要があるのです。
ストーリーづくりの大前提、会社の「大義」を見つめ直す
ブランドストーリーを構築するためには、その出発点となる大義を明らかにする必要があると述べました。
大義とは、会社が大切にしている主義や社会提供価値であり、成長を続けてきた企業発展の原動力となるものです。
それは創業以来、脈々と受け継がれてきたDNAかもしれませんし、社会やお客様、社員に対する考え方や接するときの心がけかもしれません。
会社によって、その内容は異なりますが、成長している企業であれば、必ず共感を呼ぶ大義があるはずです。
この大義をもっとも理解しているのは経営者です。
そのため、まずは経営者の心の中を分解していく必要があります。
「お客様への想い」
「社員への想い」
「なぜこれまで成長できたのか」
「どのような会社であり続けたいか」
「どのような成長、未来像を描くのか」
経営者は、これらを自ら問いかけながら、漠然とした想いや考えを言語化していきましょう。
また、大義は組織や社員の中にも根付いています。それは経営者の視点から考えているものとは異なり、「この会社で働く動機づけ」というカタチをとっているかもしれません。
そういった社員の心の奥底にある価値観や動機、思考の表出化のためには、社員同士で語り合うワークショップを実施することも効果的です。
コンセプトは、ブランドの独自性を表すフレーズに
日本企業のホームページを訪れ、その理念を確認してみると、「信頼・信用」「安心・安全」「誠実」などの言葉が多く使われています。しかしながら、そういったことは大前提であり、お客様や生活者がそれを読んだところで、深い共感は得られないでしょう。
たとえば、銀行が「信用」を前面に打ち出していたります。
ただ、そもそも信用できない銀行に大事なお金を預けるわけがありません。
銀行において、信用は大前提なのです。食品メーカーにおける「安心・安全」や、病院の「誠実」なども同様といえます。
生活者からみれば、そうであって当たり前のことを企業理念として掲げられても、何ら感銘は受けません。
当然、記憶にも残らないでしょう。
しかし、銀行の経営者としては「銀行にとって、もっとも大切なものは信用なのだから理念において信用を謳うのは当然だ」と発想してしまいます。
とはいえ、ウランディングにおいて本当に大切なのは、「信用」や「安全・安心」「誠実」という言葉を理念として掲げるに至った背景や想いと、それを語るブランドストーリーだと心得る必要があります。
経営者としてさまざまなことを学び、経験したからこそ味わえる言葉の重みというものがあるでしょう。
たとえば、子供の頃に見た映画を大人になってから見ると、当時、気づくことのできなかった新たなおもしろさや感慨深さを味わえたりします。
これは、子供時代からそれまでの間に、いくつものことを学び、新しい価値観や基準を身に着けたからこそ、違う角度でその映画を観ることができたからです。
それと同じで、経営者と同程度の経験値や価値観を持たない人が、経営者が共感している言葉の奥深さを感じ取るのは不可能といえます。
企業の魅力を伝えるためのブランドコンセプトは、自社の独自性をしっかりと表しながら、ターゲットとなる相手に伝わり、共感を覚えるようなフレーズを考えていくことが重要なのです。
本当にそれで伝わるか、もう一度考えてみましょう!
ここまででわかるように、ブランドコンセプトとストーリーは、企業の独自性が表れていることが大切ですが、同時に、社内と社外の二つの視点から構築しなければなりません。
それによって、その後の浸透が大きく違ってくるのです。
自分たちの会社が、何を、いつ、どのように、誰のために提供しているのか、こだわりは何か、それを実行する想いとはどのようなものなのかを考えてください。
会社の大義を、社長から社員へと間違いなく伝えるためには、コンセプトは、どんな世代でも理解しやすく、わかりやすい言葉を使うようにしましょう。
ただ、社長と社員では、培ってきた経験値と時間軸が違っています。ここも、見逃してはいけません。
また、自分たちの常識という思いこみを取り払うことも忘れないようにしましょう。
業界用語のように、その世界では当たり前のこととして通用しているものでも、外の世界へ行くとまるで通じなかったなどということは珍しくありません。
認知・理解よりも、その先の「共感」が大切
ブランドストーリーによって生み出される「共感」は、認知や理解とは異なります。
たとえば、雨の中、傘があるのにずぶ濡れになりながら重い荷物を運んでいる人がいたとします。認知とは、あそこにずぶ濡れで荷物を運んでいる人がいるなと認識することです。
理解とは、両手でないと運べない重い荷物だから嵩がさせず、ずぶ濡れなんだとわかることです。
ただ、認知や理解でとどまってしまっては、行動には結びつきません。
その人を見て、同じ働く人間として頑張る気持ちがわかるとか、何か自分にできることはないかと共感が生じるからこそ、傘を差しだしたり、荷物を運ぶのに手を貸したりするのです。
ブランディングにおいては、共感によって会社が示す理念や考え方をわがことのように思えるから自分の言葉で話せるようになるのであり、誰かに伝えたいという衝動が生まれてくるのです。
社内にアンバサダーを育てる
しかし、社内ですら共感の輪を広げていくのは簡単なことではありません。
企業理念と行動指針に矛盾を感じれば、そこに共感は生まれません。
「利他の心が大切です」と謳っているのに、営業研修で「いかに買わせるか」というテクニックばかり教えられては戸惑ってしまいます。
社員が率先して会社の大義を広めようと頑張っても、結局、営業成績のいい人間ばかりが評価されるのでは、大義の体現などバカバカしくて、やっていられなくなるでしょう。
だからこそ、育成や評価などのズレをなくす必要があるのです。
また、制度の一貫性を保つだけでなく、社内にアンバサダーとなるキーパーソンを育てることも大切だといえます。
そのためには、ブランディング・プロジェクトを立ち上げてメンバー内に会社の大義を浸透させ、彼らが各部位所に戻った時に回りの社員へ広めてもらうのです。
どこの会社にも発信力と周囲への影響力が強い社員はいるものですから、その人を巻き込めると社内への浸透スピードをより早めることができます。
また、お手本となる存在を会社が示すという方法もあります。
自社の想いや考え方に合致した人を表彰することで、「今、会社が評価するのは、こういう人です」というメッセージを全社員に向けて発信するのです。
その人が手掛けた成功事例や表彰したポイントを紹介しながら、社員の間で共有することによって、何が求められているのかを伝えることができます。
会社の大義に根差した価値観が、社内の共通言語として語られるようになれば、文化として定着したといえます。
しかしながら、1年やそこらで企業文化は根付きませんので、じっくりと腰を据えて取り組む姿勢が重要となります。
「人事評価」にまで落とし込むブランディングで、社員を伸ばす
ブランディングのために、会社の大義を社内に浸透させていく上で、人事評価制度が果たす役割は非常に大きいものがあります。
社員が会社の掲げる大義に共感し、ビジョンをともにして、正しい方向に動いてくれれば、会社が強くなるからです。人事評価制度は、そのための武器になるともいえるでしょう。
そもそも、会社が登ろうとしている「山」を認識できていない社員は、どんな組織でも多いものです。
そういった齟齬があれば、ブランディングは成功しません。多くの社員は、常に、意識の低いほうに引っ張られてしまいます。
もしもあなたの会社が、富士山に登ろうと考えているならば、社員全員にそれを認識させ、そのための準備と心がけをしてもらわなければなりません。
そういった組織になるためには、人事評価制度やキャリアパス制度をそのためのカタチにし、それぞれに会社の大義を盛り込むことが大切になります。
人は誰かに認められたとき大きくモチベーションが上がり、誰かに認められたいという気持ちが仕事や成長に対する意欲を生むものです。
こういった心の動きを活かすことで、会社の大切にする想いの浸透を、評価の面から後押しすることができます。
そのためには、組織への貢献度や理念にそった行動を、どれだけできたかという観点を重視した「理念浸透型・人事評価制度」を導入していくといいでしょう。
理念浸透型・人事評価制度では、社員一人ひとりの日々の業務を記録して、組織に対する貢献の度合いを評価します。
成果だけでなく、指導力や新規企画力、事業立案力といった貢献度と、行動指針を体現できているか、ブランドを大切にする想いのようなものにもウェイトを置いた評価にするわけです。
そもそも人事評価制度は、単に「評価する」ためのものではなく、社員の成長を促し、会社の力を伸ばしていくためのもの、ということを理解しなくてはなりません。
部下の育成を上司がサポートし、彼らのキャリア成長を応援することも企業の務めです。
それでは、そんな社員を育成する評価制度について、簡単に説明してみましょう。
票か制度は、「業績」と「行動」という評価基準に二分され、社員の貢献度は、「業績」に紐づけられています。
「業績」は、売上や新規訪問数、業務改善率、提案数などとして数値化されるものです。
一方、「行動」は業績に至るまでのプロセスにおいて、会社の行動指針を体現できているかといったポイントを見ていきます。
社員の貢献を見落とさないために、目標管理制度があるのですが、この目標管理は、ブランドコンセプトを理解した人が設計し、扱っていかなければいけません。
なぜなら会社の目指すゴールや、そこから導き出される社員一人ひとりに求められる業績や仕事に取り組む姿勢は、ブランドコンセプトから紐解くことができるものだからです。
それは裏返せば、ブランドコンセプトを構築したところで、社員が理解したうえできちんと行動に移していなければ、会社が変わることがないということでもあります。
会社の年間目標などは、未来のあるべきブランド像から逆算して設定します。
同様にして、部署としての目標から個人の目標までを落とし込んでいく、というように進めていきます。
ブランディングの真髄は、共感によって想いを浸透させ、人々が行動に移すためのサポートをしていくことです。
会社のブランドコンセプトとストーリーが明確になったあと、社内で一人ひとりが具体的にどういった行動に移せば、会社への貢献と評価されるのかを明確にする段階が、評価制度の設計ということになります。
よりサポート体制を強めるという意味では、何が期待されているのか、きめられた期間内で何をしていくかという事柄を定めて、都度評価しフィードバックをしていくリアルタイム評価が、非常に効果的です。
正直、半期ごとの評価では、適切な育成は難しいと考えています。それは、半年前のことを鮮明に覚えている人が少ないことからもわかっていただけると思います。
このように、評価の仕組みは一人ひとりの成長を支えるものであって、給与分配だけのためのものではないということを念頭に、制度を組み立てていきましょう。
たとえば弊社では、上司が部下の成長をサポートするための「月次のメンター制度」を採用しています。
社員たちの大事な人生設計ともいえるキャリアを考え、彼らが3年後や5年後にどうなっていたいのか明確にし、それを実現するための課題を見つけるコミュニケーションの時間を大切にしています。
またメンター制度においてとても重要な役割を担うのは、新たな世代の人材成長を促してくれる中間層の社員たちといえます。
ですから中間層に対しては、部下育成という側面で、会社にどれだけ貢献しているかという部分も、決して見過ごせないポイントです。
評価基準を可視化する
注意したいのは、評価結果をフィードバックする面談を年1回行うだけでは不十分だということです。
世界最大の会計事務所である「Deloitte」のマネージャーは、部下の評価のための面談や評価会議に、会社全体で年間200万時間という膨大な時間を費やしていました。
それでも、パフォーマンスレビューの面談直後に会社を辞める人が増えていたといいます。
それは、ただ部下のために時間を費やせばいい、というわけではないことの証明になりました。
そこで、年間を通じて「何ができていて、どこをより頑張ればいいのか」ということを上司が部下に丁寧にフィードバックする機会を増やし、日々、社員の成長を支援する仕組みを構築しました。
これによって退職者を減らすことができたといいます。
このように成長実感は、「この会社で働き続ける」という強い動機になり得ます。
同社は、部下を評価するためのミーティングの時間を、本人を育成するための有意義なフィードバックの時間に変えました。
しかしこれをするには、上司にとって単に評価をくだすだけよりも、時間がかかります。
部下のキャリア設計を把握したうえで、さらに働き方をしっかりと見ている必要があるからです。
でも、そうでなければ、ミーティングの時間だけとっても機能しないことが、はっきりとわかったのでした。
社員の成長意欲を人事制度によって刺激して日々の業務に対するモチベーションを上げるには、理念や行動指針と評価基準に矛盾のないことが大前提です。
そのうえで、報酬が上がる条件やキャリアパスの道筋を明確に示すという方法もあります。
極論をいえば、係長、課長、部長、取締役になるための条件を社員に開示するわけです。
評価基準が可視化されていなければ、生殺与奪を握っている上司の顔色を気にするのも、ある意味仕方ないと思える部分があるからです。
しかし、本来であれば、社員が目を向けるべきは企業の掲げる大義であり、お客様でなければなりません。
上を気にするあまり、社内調整などが多くなり、お客様に提供できる価値があるはずなのに、それ以外のことにエネルギーを使っていては本末転倒です。
人事評価制度は、社員全員が会社の大義に共感し、会社の進む方向性とベクトルをそろえ、その達成のために力を発揮できる環境づくりに結びついているべきだと、私は考えます。
若手社員の成長を引き出すのは、「直属の先輩」
人事評価制度を企業理念と連動させることで、成長実感を得られるものへ変えたとしても、それだけでは社員が生き生きと働くために十分とはいえません。
前述しましたが、人が成長するには、スキルを少し上回る課題に意欲を持って取り組むことが必要です。
その際、明確な目標も必要で、会社が目指す方向性を明確に示すことで、社員が目標を設定しやすくなることも話しました。
ただ、もっと身近に憧れの先輩や上司がいるほうが、より具体的な目標をイメージしやすく、成長意欲はより高まることが期待できるでしょう。
社員は、「社長を目標に」とは、あまり思いません。
それよりも、上司や先輩が充実して仕事に取り組んでいれば、「自分も」という気持ちが湧いてくるものです。
そのような存在の人に、「今取り組んでいる仕事は、会社にとってどのような意味があるのか」「この仕事を達成することで、どのような将来へとつながっていくのか」を語ってもらうほうが、素直に耳を貸すことができます。
成長を加速させる組織をつくるためには、リーダーやマネージャー層への想いの浸透を率先して促し、その人から周囲へ浸透させる流れを作っていくべきなのです。
また若手社員でも、誰かの先輩になった時点で、後輩に見られていることを意識しないといけません。
新人からすれば、先輩はすべて、ロールモデルになっていることを理解しましょう。
「まぁ、いいや上司」こそがネック
成果を生み出す組織では、明確な大義やビジョンが共有され、メンバーの共感を得ているものです。
社員は自ら仕事を見つけ行動し成長するという好循環の中にいます。
その成長をサポートする仕組みもあり、社員同士のコミュニケーションも活発です。
社員同士が互いに刺激し合いながら、さらなる成長をもたらしてくれます。
人の行動は、周囲の人間関係に大きく影響されることは、行動科学でも証明されていることなのです。
しかし、このような組織でも、あっという間に、成長できない後ろ向きな組織へ変わってしまうことがあります。
それは、「まぁ、いいや」という気持ちで仕事をする、リーダーやマネージャーが異動してきた場合です。
マネジメント層に後ろ向きな人材がいると、いくら人事評価制度や育成制度といった仕組みを整えても機能しません。
理念を浸透させようとしても、組織の末端までは広がっていかないでしょう。若手社員も、最初は抵抗してそれまで通りモチベーション高く仕事に取り組むでしょうが、評価されることがないと知れば、バカバカしくなり会社を去っていってしまうかもしれません。
組織を活かすも殺すもマネジメント層次第なので、理念浸透施策では、この層には特に注力して取り組む必要があります。
「社内」と「社外」、発信内容の完全一致を追求する
今は、調べたいと思ったことは、たいていインターネットなどで調べることができます。
会社の歴史や社長のメッセージなどオフィシャルなものはもちろん、会社の内部事情といった一昔前ではほとんど表に出なかった情報も、現役社員や元社員が匿名で投稿できる口コミサイトなどから収集することが可能です。
今や会社にとって都合の悪いことを隠そうとしても、隠し切れない時代になっているのです。
そのため、アウターブランディングを考えるうえで、インナーブランディングと連動させることは、これまで以上に重要な要素になっています。
生活者は賢いですから、企業が発信するキャッチコピーや商品紹介などのメッセージが、ある程度企業にとって都合がいいようにつくられていることを知っています。
そのため、少しでも「本当?」と思えば、浦をとるためにすぐ調べるものだと考えるべきです。
そして、そこにズレを感じたら、消費者はあっという間に離れていきます。
インナーブランディングとアウターブランディングに一貫性を持たせるには、会社の大切にする想いが、社内に浸透していなければなりません。
ブランディングは、社内への浸透からはじまり、社外への発信へと繋がっていくものなのです。
たとえば、商品やサービスを開発するとき、「ウチの会社の方向性なら、こういうものはつくらないよね」というチェックを社員自身が行っていく必要があるからです。
ストーリーのブレが、共感を削ぐ
また、それまでの方向性とはまったく異なる商品をつくろうとするときには、会社の大義に繋がるブランドストーリーの構築が、さらに重要になります。
「生活者の味方」をスローガンに掲げて「質の高い製品を誰もが気楽に手の届く価格帯」で提供してきた会社が、いきなり高級ブランドを立ち上げるとなったら、生活者が「なるほど」と納得できるストーリーがないと、簡単には受け入れてもらえないはずです。
ブランドストーリーにブレがあると、インナーブランディングとアウターブランディングや、企業ブランドとプロダクトブランドなどの間にズレが生じます。
ズレがあると、そこには矛盾が生まれて、メッセージを受け取ったアンバサダーの共感が削がれてしまいます。
ヒット商品を生み出すブランドストーリーの精度は経験値によって高めていくことはできますが、「これで間違いない」という方程式はありません。
しかし、売れない商品や共感を生めない商品には、必ずズレが生じているのです。
これは国内だけでなくグローバル市場においても同様です。
むしろ、伝えることに長けている外国人のほうが、ブランドストーリーのブレやズレに敏感に反応するかもしれません。
SDGsへの取り組みは、企業が持続させるもの
最近は、SDGsをテーマにして、新しい取り組みをしようとしている企業が増えています。ただ、SDGsへの取り組みを、間違って捉えている企業もあるようです。
SDGsとは、企業が、それぞれになっているビジネスによってかなえる目標です。
社長の趣味嗜好はもちろん、単なるボランティアで実施しても意味がありません。ボランティア活動はたいてい、一時的なもので終わってしまいます。
収益が全く出ないうえに、自社の事業と関係もないことを企業が継続するのは難しいのです。
そしてSDGsを、事業を通じて叶えることによって、社会に貢献し、お客様や生活者から「いいね!」と思われる企業になってこそ、意味があるといえます。
そうすれば、社員の共感を得ることもできますし、誇りの持てる企業としてのブランディングにつながっていくのです。
これはESG経営にも同じことがいえます。
ESGとは、「環境」「社会」「ガバナンス」に取り組む企業を増やして、世界規模の環境問題や社会問題を解決していこうとするものです。
ここでも短絡的で意味をはき違えた取り組みをすれば、社員から共感を得られずに、お客様や生活者にも理解されず、せっかくの活動が、企業としてのブランディングどころか、真逆に、マイナス効果を及ぼすことがあるのです。
社会的責任をどう考えているかの意思表示
SDGsやESGとは、企業が継続して取り組むことによって、社会へ与える影響にも責任を持ち、社会からの要求に対して適切に対応することです。
つまり、企業PR目的の延長線上にある活動とはまったくの別物であり、たとえばスポーツチームのスポンサーになるということなどもSDGsやESGとは捉えられないのです。
福岡県・大川市に「タンスのゲン」という会社があります。家具・寝具・家電・インテリア用品などのインターネット通販事業をしており、年商175億円を突破して急成長をしています。
この会社の企業理念は、「Design the Future 暮らしの未来をデザインする」です。
また、同時にコーポレートメッセージとして、「大川を、世界のインテリアバレーに。」というコンセプトを発信しています。
大川市は、もともと家具の製造で賑わった町ですが、婚礼家具の需要縮小で家具製造業者が廃業してしまい、町からは人や店、企業が減り続けています。
そんな中で「タンスのゲン」は、自社が大きく成長することによって、大川という町に人や店を呼び戻しながら、自社の収益を地域に還元することによって、町を盛り上げようとしているのです。
「タンスのゲン」は地域あってこその企業だと捉えています。
企業を永続させるためには、その企業がある地域に活気がなくてはならないと強く思っています。
だからこそ「大川を、世界のインテリアバレーに。」というコーポレートメッセージを掲げ、大川という地域jを人と技術と情報、そして期待が集まる地にしようと試みているのです。
今後、地方企業に求められることは、同社のように企業が主体となり、地方創生を行う姿勢です。
地方企業が真に社員の幸せを創るのであれば、地域の活性化を図ることが必ず求められます。
社員はもちろんのこと、地元の人々を巻き込み、誰もが共感する地方創生を行うことが、企業の責任でもあるのです。
同社が生活者の未来をデザインしながら成長して、大川をインテリアバレーとして確立できれば、これ以上の地域貢献はありません。そこに今、多くの若者が共感しています。
このように実践することが、本質的に、企業が事業で社会貢献するということであり、取り組みとして持続可能なものとなっているのです。
SDGsやESGは、会社が社会に対する責任をどのように考えているのかを示すことにもなるので、それだけに、理念との連動は絶対条件だといえます。
意識を変えて、人を変える。ブランディングには時間をかけて
経営者の中には、カルチャーブックや人事評価制度が完成した時点で、ブランディングは終わったと考える人がいます。
それはとんでもない誤解です。
人の考え方はそんな簡単に変わるはずがありません。ツールがそろったところからがスタートなのです。
若手社員、中堅社員、マネージャークラスなど、階層別の研修や社内ワークショップを通じて、カルチャーブックに書かれた内容について理解を深める機会を定期的に設ける必要があります。
そして、会社の大義をもとにつくり上げたコンセプトを社内でどのように体現するかを考え、社員一人ひとりが日々の業務で実践できるようにしていかなければなりません。
それは短時間ではできないことです。
長い道のりになることを覚悟して、じっくりと取り組んでいかなければならないのです。
また、定期的に理念浸透度調査を実施して、社員の共感度を確認することも大切です。不十分だとわかればテコ入れする必要があるかもしれません。
ブランディングは、仕組みやカタチを整えるだけで閑静するものではありません。
1年、2年と時間をかけてじっくり取り組むものなのです。カルチャーブックをつくったことは、単なる制作物を仕上げただけです。
ブランディングに終わりはないと理解しましょう。
浸透施策はオーダーメイドで
ブランディングのために会社の想いを浸透させていく手法に、正解はありません。なぜなら、会社の規模や性質、風土などによって、そこで働く社員も、それぞれ変わってくるからです。
例えば、「ユニクロ」を見てみましょう。
同社は、海外へ進出した当初、日本流の内部規則や教育、評価制度を持ち込みましたが、うまく機能しませんでした。
それは、日本と海外では、文化や常識、給料体系の標準など、何もかもが異なっていたからです。
海外で、その国ごとにある文化や常識を理解せず、いきなり日本流の企業理念を浸透させ、それに準じて社員を動かそうというのは無理な話です。
結局、現場と経営の意思疎通が図れず、売り場づくりやサービス提供に一貫性を保つことができませんでした。
そこで同社は、「ユニクロ」のブランドコンセプトとそこに込められたストーリーを学び、どんな働き方や姿勢が求められているのかを理解できるようにする研修を実施して、会社の大義にそった人材育成を徹底するようにしました。
また、ブランドコンセプトに合わせた目標設定やその実践行動を評価に取り入れることで現場スタッフの意識を高めることに注力して、結果、現在の世界展開へとつながるようになったのです。
これは海外の話ですが、日本国内で経営を行う企業でも同様です。
同じ日本国内であっても、エリアや地域によって歴史や風土はそれぞれ違っています。
また、そこで育ち、教育を受けてきた「人」のキャラクターも、それぞれ大きく変わってくることでしょう。
したがって、自社の想いや社会提供価値を社内に浸透させるためには、働く社員を見て、考えたうえで、自社独自の効果的な方法を、「オーダーメイド」で作り上げていかなければなりません。
経営者は、これを理解したうえで、自社に適した理念浸透法を見つけ出すようにしていきましょう。
ブランディングのために、社員の意識を変え、社員を変えていく。
これには、一つの正解があるわけではなく、また、一朝一夕にできるわけでもありません。
達成には多くの時間と独自の施策が必要になってくるのです。
ブランディング成功の鍵は、「やり切る覚悟」
世の中には、達成するまでに時間も手間も必要だけれど、途中でやめてしまうと、あっという間に元へ戻ってしまうことがたくさんあります。
トレーニングやダイエットがそうですし、プロのピアニストも「1日練習を休むと自分にわかり、2日休むと批評家にわかり、3日休むと聴衆にわかる」などといわれます。
ブランディングもまさにそうです。
最後までやり切らなければ、何の効果も発揮しません。
しかし、新たにブランディングをはじめようとすると、社内から必ずといっていいほど、「本当に効果があるのか?」「コストをかける価値があるのか?」という声が上がってきます。
ブランディングがはじまってからも、「いつ成果が出るんだ?」「やはり、何も変わらないじゃないか」と横やりが入ることはあります。
このような社内圧力に負けずに最後までやり通すには、トップが強い意志を持って進めることが必要です。
結果が出るまでには相応の時間がかかること、最低でも年間、人一人を雇うほどの投資がいることを理解したうえで、途中でやめないと腹をくくらなければなりません。
手間暇かけるだけの価値がある
前述のソースメーカー「オタフクソース」は、創業者の理念である「利他の心」を大切にし、「人々に喜びと幸せを広めることを自らの喜びとする」という考えを「たらいの水哲学」というもので表現しています。
たらいの水を自分のほうへ引き寄せようと動かしても、手を止めると水の波紋は自分とは反対の方へ広がっていきます。
一方、相手のほうに水を差し出せば、水は跳ね返って自分のほうに寄ってきてくれる。
このように、商売も自分たちの利益だけを考えるのではなく、相手のためになることを考えて世の中に幸せを広めていけば、やがて自分のところにも返ってくるという教えです。
この大義が浸透している同社の社員は、お客様であるお好み焼き店に足を運ぶことを厭いません。お客様の声から学ぼうとする姿勢にもブレが見られません。
そして、お好み焼き文化を広めるために「お好み焼課」を立ち上げてしまうなど、業界の繁栄のために本気で頑張っているのです。
また同社は、お好み焼課のほかに、お好み焼きの文化や歴史を知り、体験もできる施設「WoodEgg お好み焼館」をつくったり、新入社員研修でキャベツ農場研修や実店舗研修、工場研修などを行い、関係者とのつながりを体感する機会を設けたりしています。
社員全員がお好み焼きをつくれるようにと、社内資格「お好み焼士」までつくりました。
ここまで徹底して、創業者の理念である「利他の心」を浸透させたからこそ、このように、文化が広く社員の中に根付いているのだと思います。
ブランディングは、手間もコストもかかりますが、手をかけながら丁寧にやり続けることで、必ず効果を実感する日がきます。
しかし、途中で投げ出したり、逃げたりしてしまうと、それまでの努力が水の泡になるだけでなく、やってきたことが嘘、偽りになってしまいます。
ブランディングを成功させるためには、経営者が「やり切る覚悟」を持つことが大切なのです。