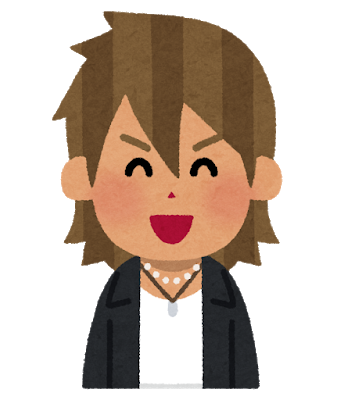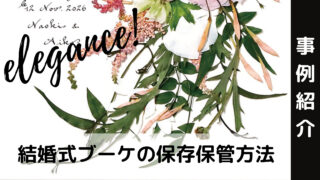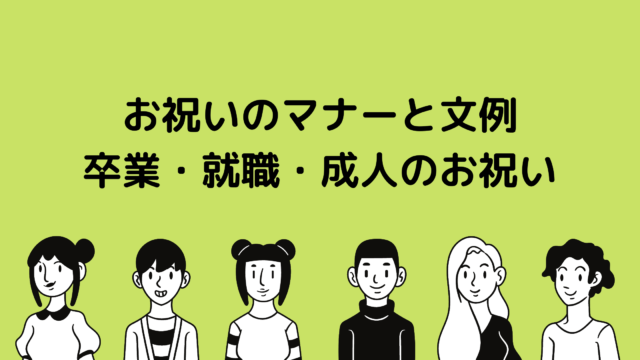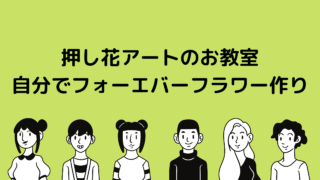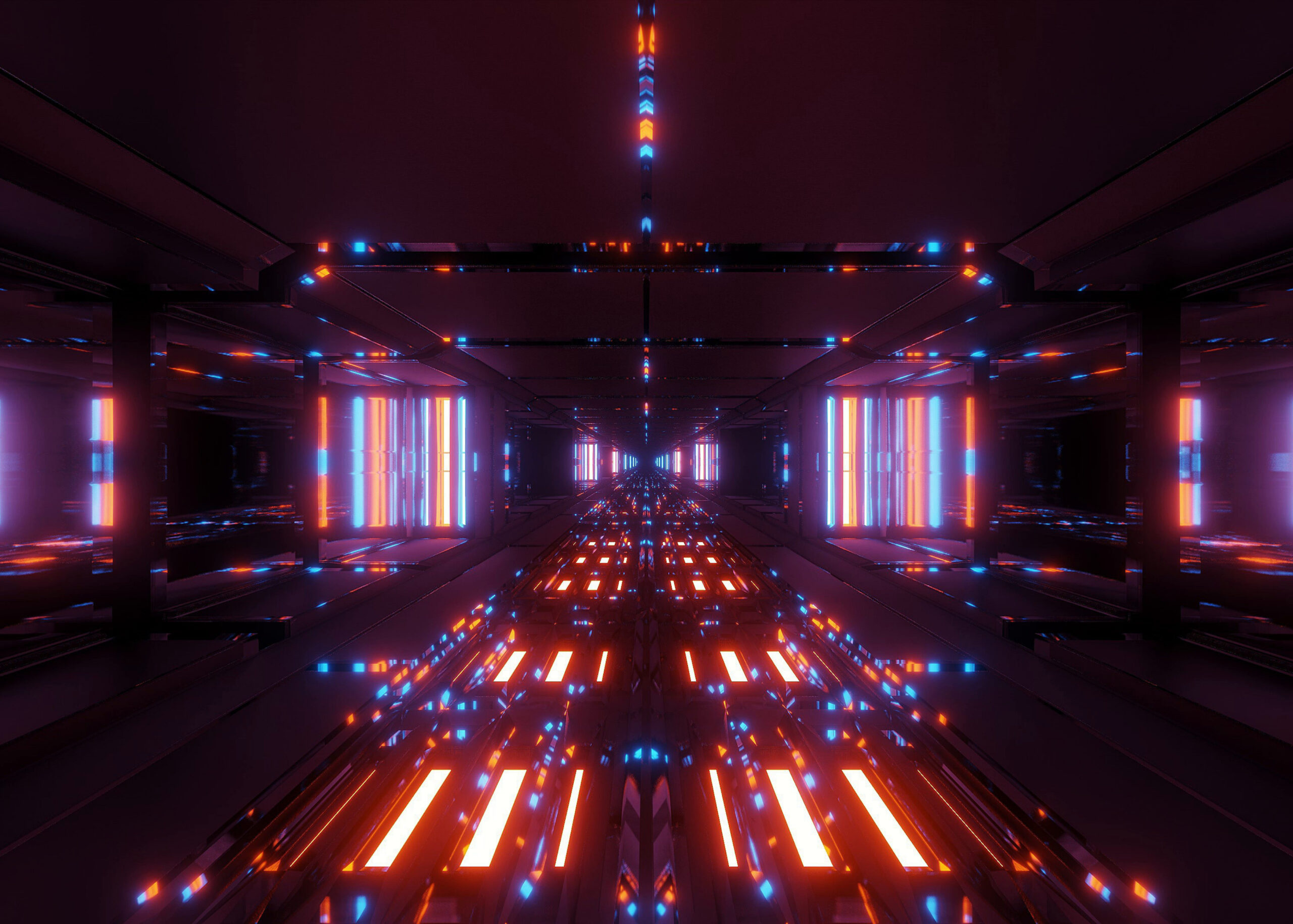

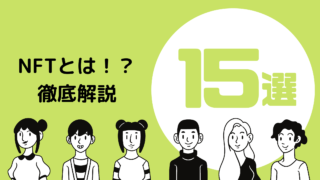








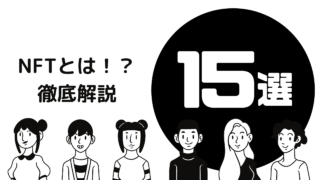


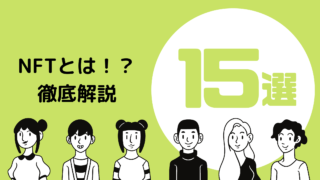

世界中で話題となるNFTアート
ここで言うトークンとはブロックチェーン技術を利用して発行したデジタルデータ(暗号資産)を指します。よってNFTアートとは、ブロックチェーン技術を利用した、代替え不可能で唯一無二の価値をもつデジタルデータを指します。
現在、NFTアートは世界中で話題となっており、2021年はそんなNFT市場の幕開けとなりました。
NFTアートブームの最初のきっかけを創出したのは「CryptoPunks」というNFTアートプロジェクトです。
Larva Labs社にて2017年6月からはじまったこのNFTアートプロジェクトは、世界初のNFTアートといわれており、非常にシンプルな24×24ピクセルアートでゾンビを基調としながらAIによって生成された1万体のジェネレイティアート(コンピューターによる機械的かつ無作為に生成されたアート)であることが特徴です。
このCryproPunksの一つの「キャラクターが2021年1月、約8000万円で取引されたことで世界中で話題になりました。
そして同年8月中旬には、大手決裁業者であるVISAが本NFTを購入したことで、大きなニュースになりました。
これに続いたのがスイスに本社を置くSuum Cuique Labs社がプロデゥースしたプロジェクト「Hashmasks」です。70名以上のクリエイターが8か月もの期間を要して準備した1万6384体のマスクに個性を与えたアートですが、2021年1月28日の販売と同時に即完売したことで一躍有名なプロジェクトとなりました。
Hashmasksは5つの特徴的なパーツを組み合わせ、ひとつのキャラクターアートとして描かれています。そして最大の特徴が、Hashmasks保有者には毎日10NCTトークンが配布されることです。
NCTトークンは、一定数もつとHashmasksの名前を変更することができます。名前変更で使用されたNCトークンは消滅されるので、Hashmansksの名前が変更されるほど、NCTの価値は上昇します。
最も人気のあるHashmasksのキャラクターは、2021年1月当時、約6900万円の価値で取引されたことで話題になりました。
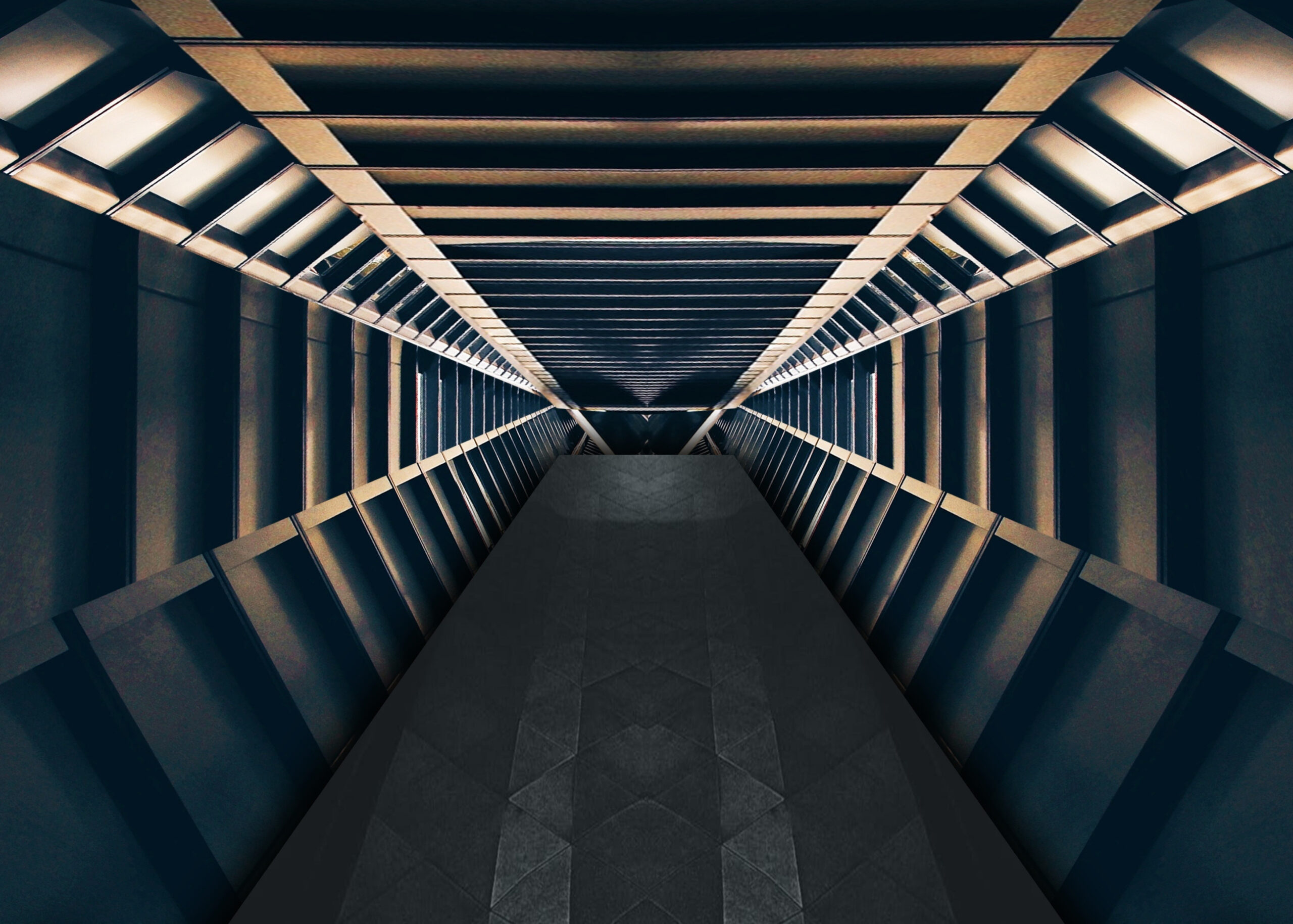
【NFT】投資家たちを魅了する「希少性」
それはNFTの価値を創出する上で重要な要素のひとつ「希少性」です。
CryptoPunksもHashmasksもそれぞれのアートに特性があり、またジェネレイティブアートであるため、中には珍しいデザインもありました。
そこにはNFTだからこそ、誰がそんな珍しいアート作品を所有しているのか、そして誰が発行したのかがブロックチェーンによって証明されていることにより、希少性の高さの証明も可能にしました。
もちろん、「クジラ」といわれるクリプトリッチの人々(ビットコインを大量に保有している人々)の資産の使い道やプロモーションなどの要素もなきにしもあらずですが、ここにNFTとしてのアートの価値が見出されたことも考慮すべき要素となります。
このように2021年は年初から一貫して、とにかく希少性が高いNFT作品を購入することに夢中になる投資家が多くあらわれた傾向がありました。その投資家たちがどこでこの作品を購入したのか、アート系NFTの購入場所である代表的な2つのマーケットプレイスをご紹介します。

【NFT】NFTを牽引するOpenSeaとRarible
ゲームアイテム、デジタルアート、コレクターズアイテム、イベントチケット、ドメイン、メタバースの土地や福などさまざまなジャンルのNFTを扱っています。
2021年7浮きの月間販売金額は300億円、そしてその勢いは止まらず、8月には2000億円を突破すると予想されています。
Raribleは、世界中の人々がデジタルアイテムをつくり、アクセスし、マネタイズできる世の中に!をビジョンに掲げ、2019年にアート専門として開始したNFTマーケットプレイスです。そしていまでは、ゲームアイテムやドメイン、メタバースの土地なども取り扱っています。
マーケットプレイスとして利用者2万2000人、月間販売金額18.2億円のオープンなマーケットプレイスとして運営されて広く認知されています。
Raribleの大きな特徴のひとつが、組織の透明性を大事にしていることです。
Rarible DAO(自律分散型組織)を推奨してコミュニティと共に運営を行う方針を打ち出していて、自社の貨幣、RARIトークンをもつことでVoting Power(投票権)をもち、コミュニティ運営に貢献できる仕組みによって根強い層の支持を獲得しています。
いち早くマーケットプレイスのみならずトークンを発行してコミュニティ運営にシフトした体制として注目されているため、他のマーケットプレイスも模範にするかもしてません。事実、同じくアート専門のマーケットプレイスSuperRareなどもトークン発行を表明しています。
このようにOpenSeaやRaribleといった海外のNFTマーケットプレイスは、それぞれのビジョンをもち、アップデートを重ねており、今後も間違いなく成長していくでしょう。

【NFT】国内のアート系NFTマーケットプレイス
「nanakusa」は国内初の個人によるNFT発行・販売・二次流通機能を備えた統合型NFTマーケットプレイスです。
「nanakusa」で主に展開されているのはCreatorsとPartnersの2セクションです。
CreatorsでNFTを発行・販売するためには、公認アーティストとして承認される必要があり、2021年8月現在約150名の公認アーティストがnanakusaでNFT発行・販売を行っています。
「nanakusa」としては、そんな公認アーティストと一緒に成長することをミッションのひとつとして掲げており、クリエイター・ユーザー目線のUI・UXの向上を掲げて実装しています。
導入する機能は、
・イーサリアムのガス代が高騰するため、Polygon導入
・一次流通の販売に関するクレジットカード機能の導入
・NFTを所有している人だけが見ることができる閲覧権限機能
・クリエイターのコラボレーションを推奨するロイヤリティ分配機能
・クリエイターが税制申告しやすいようにGtaxの導入
このような機能により、アーティストにとってもより良い環境を提供しています。
その他にもメタバースへのギャラリー展開やコミュニティビルディングの強化など、クリエイターや事業者がよりよいコンテンツを世界へ発信できるための環境づくりに励んでいます。

【NFT】盛り上がりをみせるNFTアートイベント
2021年7月、アジアのNFTアートの祭典「Crypto Art Week Asia」が開催されました。本イベントではアジア5か国6都市でNFTアートのリアルイベントが開催され、「nanakusa」も本イベントにプラチナスポンサーとして参加しています。
フィジカルアートとNFTアートの融合を目指した東京会場では、現代アーティストやクリプトティスト、ボクセルアーティストなど幅広いクリエイターが参加しました。
イベント期間中はNHKの取材など、メディア露出の効果もあり合計2118名の来場者となって注目を集めました。
これまでデジタル上にあったNFTが目の前にあることで実感が湧いた来場者の多く、同時にバーチャルに拡張されることで未来への可能性を感じるという声もあったそうです。
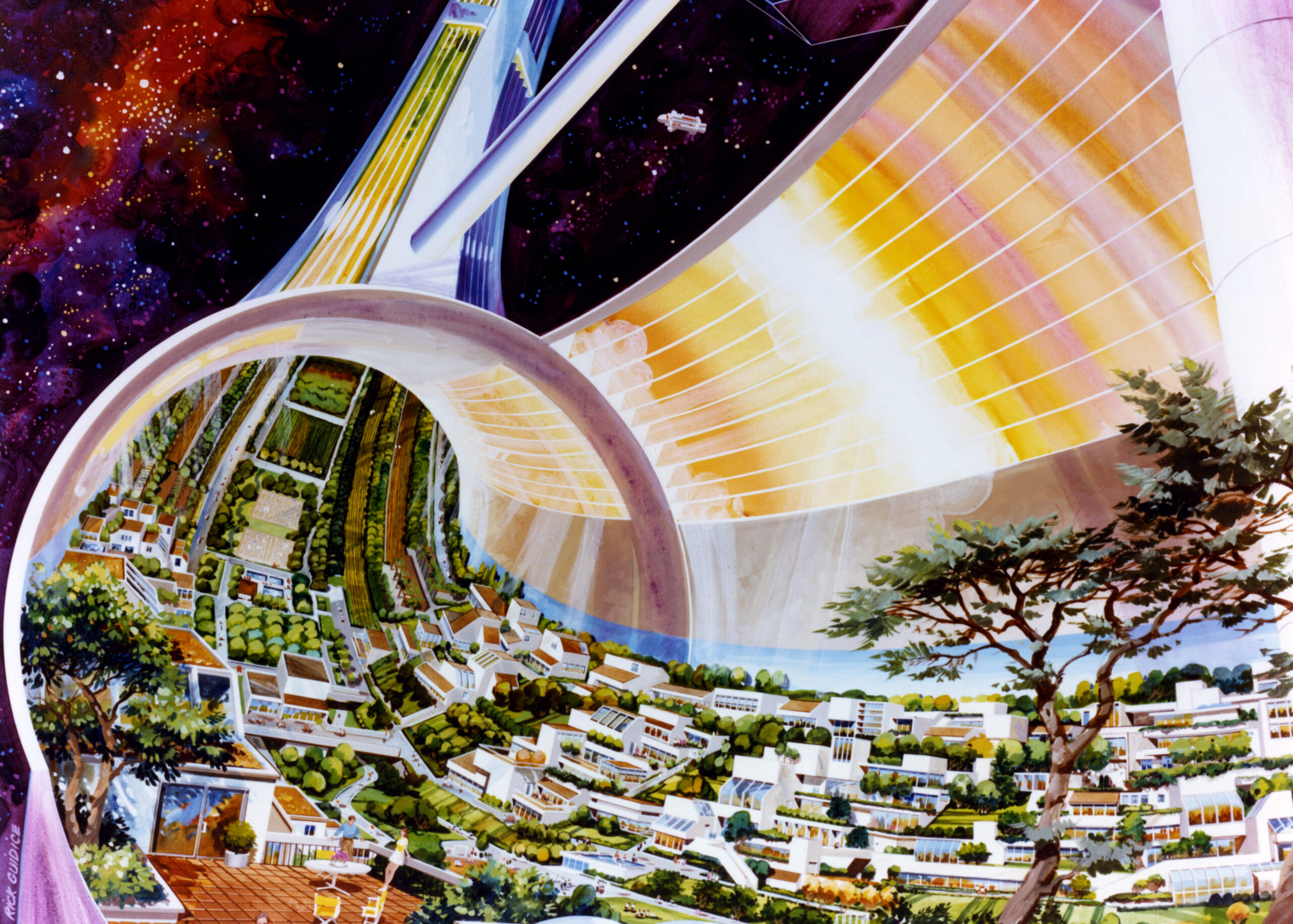
【NFT】NFTアートにおける法規制の課題と取り組みに
その一方で、NFTにおける権利や取引における法整備などはまだまだなされていません。
特に所有権に関しては、現在の日本法上ではNFTなどのデジタルデータ、すなわち「無体物」には適用されないです。
この課題については、日本に限らず世界でも大きな議論になっています。そんな課題に取り組んで解決策を提示しているのが、スタートバーン社。
「世界中アーティスト、そしてアートにかかわるすべての人が必要とする仕組みを提供し、より豊かな世界を実現する」をミッションにアート作品をICタグ付きブロックチェーン証明書を発行する「Startbahn.Cert」とブロックチェーンを活用したアート流通・評価のインフラとなるサービス「Startrail」を提供しています。
Startbahn.Certは作品情報や来歴を継続的に更新し、保全するブロックチェーン証明書のプロジェクトです。
記録された情報を、ウェブ上やスマートフォン上でユーザーが使いやすいUIに変換して、「Cert」というICタグ付きブロックチェーン証明書として提供しています。
そして、このStartrail上に記録される情報を活用して審査が通れば誰でも簡単に、作品を管理できる仕組みになっています。
つまり、イーサリアムのERC-721に準拠した「Startrail Registry Record」にアート作品の情報を記録しているのです。
またブロックチェーンを通すと管理しなければならない秘密鍵を改善するためにTorus社のテクノロジーを活用。GoogleアカウントやSNSで認証完了できるようにしており、ユーザーのことを考えたサービスを提供しています。
このシステムを活用してアートオークションサイトSotheby’sで現代美術家の池田亮司氏が「A Single Number That Has 10,000,086 Digits」を2021年6月に発表しました。ブロックチェーンテクノロジーを介して垣根を超えています。

【NFT】今後のアート系NFT市場の動向予測
世界中ではさまざまなNFT関連のビッグニュースが毎日のように発信されています。日本でも4月に村上隆氏、7月には草間彌生氏のNFTが販売され話題になりました。
今後も著名なアーティストの参入は続いていくと予想されます。
それに合わせて、現代美術コレクターとNFTアートコレクターそれぞれなどのがどのように共存し、新しい価値を見出していくのかも注目です。
また、NFTはアートだけではなく、ゲームやイベントチケットのような利用用途も主流となっていきます。
これからは「メタバース」「トークンエコノミー」などのキーワードにあらゆる分野に入り込んで加速していくことが予想され、NFT市場はさらに加速して広がりを見せていくでしょう。
いまや多くの人がスマートフォンを所有し、SNSが生活の一部になっているように、ウェブ3.0時代のテクノロジー並びにNFTが人々の生活に溶け込む状況がまもなく訪れます。
いかにこの概念並びにバーチャルの世界観を取り込むかがキーとなってくるでしょう。
故に、すべてに関連するNFTビジネスは、まだ序章にすぎないのです。