ビジネスをしている人なら、誰しも
「お客さんを増やしたい!」
「不況でも変わらずついてきてくれるファンが欲しい!」
こんな願望を持っているのではないでしょうか。
本記事を読んで頂いている皆様も少なからず
「いまより売上をアップさせたい」
「良質なお客さんを増やしたい」という思いがあるはずです。
では、「それをいままで実現できていないのは、YouTubew活用できていなかったのが原因です」といわれたらどう思うでしょうか。
「YouTube?そんな子供が観るような軽いエンタメ媒体なんて使わないぞ」
そう思われた方は、今後のビジネス集客に苦労するかもしれません。
いま、コロナ渦においても売上を伸ばし続けている国内外の企業は、
YouTubeをメインの集客手段にしているところが多く、その流れはいっそう加速していくことが確定的だからです。
YouTubeは単なる娯楽としての動画媒体ではなく、
いまやビジネス上の集客戦略の中心媒体ともなっているのです。
例えば、あなたがYouTubeを活用するならば、次のようなメリットを享受することができます。
- 商品やサービスへの集客誘導が永続的になされる
- あなた自身のファン、あなたのビジネスのファンになるお客さんが生まれる
- 感染症や不況など世想に左右されず、インターネットから安定的に集客できる
- YouTubeの広告収入のみならず、様々なルートから収入が得られる
- 競合と一気に差をつけた売上アップが見込める
本記事を読み終えた頃には、「YouTubeからの集客」の仕組みと、
具体的なノウハウを獲得できているでしょう!
早くチャンネルを立ち上げたいと、動き出したくなってウズウズしているかもしれません。
難しいとか、もう遅いということはありません。その理由は本記事を読めばきっとわかります。
そして、「オンラインの時代」にあって、しっかりとファンを作りながらビジネスを拡大、安定させていくことができるはずです。
- YouTube市場はまだまだ先行者有利
- いますぐYouTubeチャンネルを作るべき理由
- モノが溢れる時代の販促キーワードは「指名買い」「コト消費」
- 動画の何がそんなにすごいのか?
- 高齢者層もスマホを使いこなし、YouTubeを楽しんでいる
- 狙うべきは「検索ハウツーコンテンツ」というジャンル
- いずれは動画が検索エンジンのトップに?Googleの考えていること
- YouTube集客の実例
- 中国に見る「ライブコマース」というさらなる可能性
- 意外と知らない!YouTube攻略の基本
- そもそもYouTubeとは何か
- YouTubeはなぜ「Googleビデオ」に勝ったのか?
- YouTubeはGoogleが所有するテレビ局
- 人はどこからYouTubeにたどり着くのか「流入経路」の話
- 自分の動画を効果的に見つけてもらうには?
- 広告収益化は継続のモチベーションになる
- ビジネス系チャンネルの落とし穴と対策
- 大衆受けならこのジャンルを狙おう~テーマ選び~
- 初期にはニッチなテーマに手を出してはいけない
- YouTubeで超高額商品は売れない
- スマホ1台でできる撮影オペレーション
- YouTubeでの話し方のコツ
- トーク構成の具体的な流れとテンプレ
- YouTubeチャンネルの立ち上げ方と初期設定
- 視聴者を惹きつけるチャンネルアートのデザイン
- クリックされるタイトルとサムネイル作成の極意
- 自分のチャンネルに挿入できる広告と加入用件
- 最初の目安は「半年で100本投稿」
- 無料で使えて便利なリサーチ・分析ツール
- 広告収入以外のマネタイズをしましょう!
- YouTubeから自社商品への効果的な誘導方法
- YouTubeにアップしてはいけないコンテンツ
- 自分のことは自分が一番客観的に見られない
- ここで差がつく!動画ビジネス飛躍のヒント
- チャンネル成長のカギは「ストック」と「フロー」のバランス
- 続けるだけで上位1%の法則
- YouTubeが伸びない原因:「自意識の壁」を克服しよう!
- あなたのチャンネルを伸ばすための情報源
- 「テーマのごった煮」に悩んだらサブチャンネルで可能性を広げよう
- YouTube×WEBの組み合わせでSEO効果をアップする方法
- 次世代型の動画集客手法:TikTokやInstagramのリール
- 昨今の動向と、これから
YouTube市場はまだまだ先行者有利
ユーチューバーの終焉!?広告収益で稼ぐ時代は終わった!
検索ハウツー需要が急増している
「YouTubeがどうやらビジネスや集客でいいらしいぞ」
「あのお店は、YouTubeのおかげで最近調子いいらしい」
ビジネス感度の高い皆さんなら、こうした言葉を聞いたことがあるかもしれません。
では、「YouTube」と聞くと、どんなイメージを持つでしょうか?
HIKAKIN、はじめしゃちょーなど、エンタメ系のユーチューバーを思い浮かべる人も多いと思います。
2014年「好きなことで生きて行く」というフレーズをYouTubeが広告コピーとして打ち出したあたりから、YouTubeは一般の人たちにもかなり認知される動画プラットフォームになってきました。
そして、こういった主にエンタメ系のユーチューバーは、「インフルエンサー」と呼ばれ、YouTubeからの広告収益をベースに稼いできました。現在も、YouTubeは「広告収益で稼ぐ=再生回数で稼ぐ」媒体だと思われがちです。
しかし、時代はここ数年で大きく変わっています。いまやYouTubeは、単にユーチューバーが広告収益で稼ぐ媒体ではなくなりました。
一般の生活レベルで、検索エンジンとして調べものをしたり、ノウハウやハウツーを吸収したりといった需要が急速に高まっているのです。
人間関係、仕事術、料理のレシピ、壊れた家電の直し方、これらの検索に耐えうるコンテンツの需要が近年YouTube上で加速しています。
そして、そうした検索ニーズに対応するハウツー型のコンテンツを提供する企業や個人が増えています。
自社の商品やノウハウ、考えを知ってもらうために、YouTubeをブログやWEBサイトのような媒体、つまり「集客の窓口」として活用し、大きく成功しているところもあるのです。
それはどういうことなのでしょうか。
まずは検索のプラットフォームの利用者数をざっくり見てみましょう。
世界で最も利用者が多いのがGooGleです。
また、近年の検索の回数としては、Googleは「世界中で1年間に2兆回」にものぼるというデータがあります。1999年が10億回ですから、いかにすさまじい勢いで伸びているかがわかると思います。
ではその次はどこかというと、いまはYouTubeが世界第2位なのです。月間で20億人ものアクティブユーザーが存在し、アクセス数は243億もあります。
ここまでYouTubeの利用者が増えたのは、単なる「ユーチューバーを見るためのエンタメ媒体」という、これまでの使い方やイメージではなく、検索エンジンとしての需要が増加している証左だといえるでしょう。
5G到来で「動画」のハードルがますます低くなる
動画市場の勢いが高まっている要因は様々考えられますが、そのひとつに、2021年から5Gが本格化しはじめたことが挙げられます。
5Gとは、簡単にいうと、これまでよりも高速で大きなデータの送受信が可能になる環境のことです。
より解像度が高く、容量の大きい動画を楽しめるようになります。
例えば2時間程度の映画なら、5Gの環境下ではわずか3秒ほどでダウンロードできます。
YouTubeなど動画の視聴ハードルがグンと低くなるというわけです。
15年ほど前、スマートフォンがまだ普及していなかった時代には、動画を視聴するのは容易ではありませんでした。自宅の優先LANをパソコンにつなぎ、画像が粗い状態で途切れ途切れの動画を見ていた方も多かったのではないでしょうか。
また、手持ちの携帯電話で動画を観ようとしても、ガラケーと呼ばれる折り畳みのケータイを持っている人が多く、動画を観るにはダウンロードに10分以上はかかったものでした。
パケット制限があったので、ガラケーで動画をずっと観てしまい、携帯電話の請求書が5万円を超えたという痛い思い出が私にはあります。
ですが、いまはスマートフォン全盛の時代です。インターネット環境も以前と比べて格段に進歩しました。あちこちでスマホをWiFiに繋ぐことができ、美しい画質の動画をスムーズに楽しむことができます。
私の知人には、山手線で動画を視聴していたら、うっかり1周してしまっていたという人もいます。
テクノロジーの発展と共に、動画を視聴する環境も加速度的に進化し、今後インターネットの高速化で動画の視聴ハードルはよりいっそう、低くなっていくのです。
売れない小さなお店が月商1000万円を突破した話
では動画は実際のところ、どんな風にビジネスに繋がるのでしょうか。
とあるペットショップでは、コロナ渦の影響もあり、リアルのお店の集客が前年比マイナス90%にまで落ち込んでしまいました。
しかし、その店主は、ピンチはチャンスと受け止め、新しい集客ツールとしてYouTubeでの発信を取り入れることにしました。
発信の内容は、「初めてペットを買ったときの飼育方法」や「ペット別の値段」「飼育の楽しさ」などを、等身大でフランクに店内から届けるというもの。
チャンネルを開設してからわずか4ヶ月で視聴者数は3万人を超えました。店内でも「いつもYouTubeを見ています」というお客さんの声が頻繁に聞こえるようになったのです。
月商は200万円程度に下がってしまっていたのが、600万円程度にまで回復し、多いときは1000万円を突破するようになりました。
こんな風に商品の直接的な情報ではなく、商品に関連する「汎用的な情報」をプロの視点から伝えるだけでも、観た人が親近感を覚えてファンになり、集客へと自然に繋がっていきます。
また、YouTubeは、ネットショップや自社サービスURLリンクへの誘導などと非常に相性がよいです。
YouTubeでお店や個人など発信者の情報を聞き、ファン化
↓
動画の説明欄を見て、そのお店のWEBサイトや他のネットショップで買い物
という流れが主流になってきています。
自粛生活により、楽天やYahoo!、Amazonの流通総額は、昨年対比の1.5~2倍近くになっています。
また、日本全体や世界全体で見た「EC化率」も年々上がっています。
ネット販売において、YouTubeは抜群に相性がよく、法人であれ個人であれ、YouTubeをうまく使えば売上を飛躍的に伸ばすことができるのです。
ビジネスユーチューバーの台頭
YouTubew本業に活用する「ビジネスユーチューバー」のなかには、相当な数のファンを持つ有名人も存在します。
例えば「マコなり社長」は、渋谷にあるプログラミングスクール「テックキャンプ」などを運営する株式会社divの代表取締役ですが、YouTube開始から2年ほっで、チャンネル登録者数が10万人超となり、直近では90万人超にまで伸びました。
2021年9月に休止を発表しましたが、そうしたYouTubeでの活動が、本業であるスクール集客はもちろん、オンラインサービス運営、教育パッケージ販売などへと広がったことは、明らかです。
チャンネルの広告収益は月に100万円以上と推定され、一般的な感覚では多いように感じられるでしょう。
しかし、年商数億~数十億円規模の会社にとっては大した額ではなく、それよりも、YouTubeを窓口とした本業の利益のほうがはるかに大きかったはずです。
◇チャンネル始動 2018年11月
◇チャンネル登録者数 92万人
◇YouTube広告収益 100~300万円(推定)
◇オンラインサービス 3000万円(推定)
◇教育パッケージ単発 4000万円(推定)
また、元・日本マクドナルド社長で、現在はセミナー講師として活躍する鴨頭嘉人さんもビジネスユーチューバー界隈では有名人です。
本業では、組織構築・人材育成・セールス獲得について講演や研修を行っています。
◇チャンネル始動 2021年11月
◇チャンネル登録者数 108万人
◇YouTube広告収益 50~160万円
◇講演 100万円
◇YouTubeプレゼンテーションセミナー 1000万円
ご著書によると、YouTube動画を長年投稿していてもなかなかのびていなかったそうです。
しかし、そのプラットフォームとしての可能性にいち早く気付き、いまではチャンネル登録者数が100万人を超す売れっ子のセミナー講師となって、大成功を収めています。
ビジネスユーチューバーのコンテンツのジャンルは多岐にわたりますが、共通するのはYouTubeの広告費で稼ぐというよりも、本業として受注する商品やサービスがあり、そこへの導線や全体的な集客としてYouTubeで発信していることです。
YouTubeの広告収益は動画の再生回数に影響されることが多く、そこに頼ったビジネスでは「コンテンツポリシー」と呼ばれるYouTubeの規約や動画の流行りすたりに売上が左右され、安定的な収益を得るのが難しい側面があります。
しかし、YouTubeを「本業への入り口の集客手段」として捉えるのであれば、そういった懸念に制限されずに、ビジネスを安定させていくことができます。
1企業1YouTubeチャンネルの時代がやってくる
今後、「1企業につき、1YouTubeチャンネル」という時代が必ず来ると予測しています。
その理由について詳しくは次でお伝えしますが、まずお伝えしたいのは、動画には「圧倒的な情報伝達力」があるということです。
一般的なWEBサイトと比べると、動画1分につきLP100ページ分の情報量があると言われています。静止画と比べてそれだけ多く伝えられる動画という媒体を、使わない手があるでしょうか。
また、動画にはWEBサイトの文章を読んでいると疲れる。画面上だと文字が見づらいといった理由から、これまでは情報が届いていなかった高齢者層にもリーチできるという利点があります。
そして極めつけは、YouTubeは検索エンジンとして世界で9割近くのシェアを占めており、時価総額が世界トップ5のGoogleが所有しているという点です。
ここまでの話から見えてきたと思いますが、これからは、動画の時代であって、しかも動画といえばGoogle傘下のYouTubeが圧倒的なシェアを持っており、YouTube1択が道理なのです。
いまの動画ビジネスの状況は20年前の楽天やAmaznonなどでのインターネットショッピングや、様々なWEBサイトの繫栄期と同様、というとわかりやすいでしょうか。
まさに今後10年20年のうちに、YouTubeはよりいっそう普及していくと予測されます。
昔は「楽天市場」というと「何それ?」と思う方が多く、インターネット自体についても「怪しい」というイメージを持っている人が珍しくありませんでした。
私が元いた楽天という会社の創業社長である三木谷氏は、1997年の創業当時、経営者向けのセミナーで「これからはネット通販の時代が来る」と高らかに宣言したところ、集まった経営者は皆ポカンという顔をしていたと言います。
しかし現在ではもはや、小売であればネット通販を行っていないところは後進とみなされ、ホームページがない企業はあやしく、存在していないかのように思われてしまいます。
楽天は皆さんご存知の通り、その後ネット通販で大成功をおさめ、わずか20年ほどで時価総額2兆円以上の大企業に成長していきました。
それを考えると、今後、「1企業に1つYouTubeのチャンネルがあって当たり前」「YouTubeで情報発信をしていくのが当たり前」いや、むしろ「ないと信頼がない、情報がない」とみなされる時代に突入していくのは明白でしょう。
逆にいうと、動画コンテンツの時代に乗り遅れず、先手を打っていくことで、競合他社に圧倒的な差をつけることができるのです。
まだまだ先行者有利のブルーオーシャン
「そうは言っても、すでにYouTubeにはチャンネルがありすぎて、いまさら初めても遅いのでは?」と思った方もいるかもしれません。
ではまず、発信者の数に目を向けてみましょう。いまのところYouTube上で情報発信をしている人は、YouTube利用者のうち、わずか0.03%しかいません。
世界中の驚くべき利用者数からすると、「発信者側」としてYouTubeというツールを使用している人は、1万人に3人という割合なのです。
もしあなたが人口10万人の都市で、新しく自転車屋さんをオープンするとしたら、競合の自転車屋がすでに100店舗あるA町と、まだ1軒しかないB町のどちらにお店を構えるでしょうか?
おそらく9割以上の方が「まだ1軒しかないB町」に出店したいと思うはずです。
私自身が最初のYouTubeチャンネルを本格的にスタートさせたのは、2020年3月頃でした。
コロナ渦の影響でセミナー開催などリアルでの集客などができなくなったため、新しく何か始めようと思い立ち、自分のチャンネルをスタートしました。
すでにYouTubeの認知度はすさまじいどころか、エンタメ系の人や芸能人などがたくさん流入してきた頃でした。「いまからでは遅いかも」と思いましたが、蓋をあけるとそんなことはありませんでした。
個人事業主や経営者の方々に向けて「起業・ビジネス」のノウハウや、使える助成金などの情報を発信しはじめたのですが、チャンネル視聴者数がわずか半年で5000人を超え、現在では2・5万人を突破。月間ではチャンネル単体の視聴者数が90万人を超える月も出てきています。
そのYouTubeをきっかけに、コンサルティングやプロデュースの依頼や問い合わせが急増し、月間で1000万円の売上を超える月もあるくらいに成長したのです。
そして私のクライアントも、現在進行で、売上を大きく伸ばすことに成功しています。
そう、YouTubeは、まだまだ「ブルーオーシャン」“先行者利益”の市場であり、「始めるのに遅すぎる」ということはないのです。
さあ、動画というコンテンツをうまく活用し、YouTubeという圧倒的なプラットフォームを自社の強力なビジネスツール、ファン作りの場として活用していきましょう。
そこにはあなたが想像する以上の恩恵と、ワクワクする未来が待っているはずです。

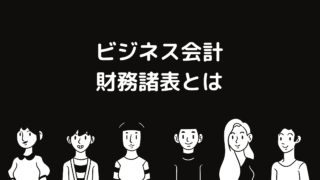
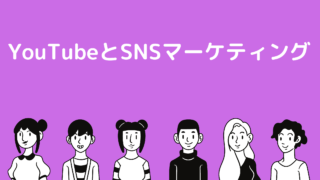

いますぐYouTubeチャンネルを作るべき理由
今や信頼できるメディアはテレビCMより〇〇〇
インターネット、さらにはSNSの台頭により、人々の購買心理は変わりました。テレビや雑誌といったマスメディアからの情報とは別に、「自分の信頼する著名人やインフルエンサーからの情報」によって商品を購入するというケースが、ここ数年で増えつつあります。
テレビが全盛の時代には、テレビCMは最もインパクトのある宣伝方法でした。商品の認知度を上げるために、大手の広告代理店に億単位のお金を払い、人気の芸能人を起用してCMを製作し、大々的に放映する。ほんの数年前までこれが一番強かったのです。
それがいまでは、例えば人気女優が青汁のCMに出て「青汁を飲んで美しくダイエット」と宣伝したところで、「私も青汁をいますぐ買おう」とはなりにくいという考えが浸透しつつあります。
実際にその女優さんが青汁を飲んでいるかどうかは別として、いまいちリアリティに欠けると感じる人が多いのでしょうか。このやり方だと、商品の認知度はアップするかもしれませんが、実際の購買には繋がりにくいのです。
一方、自分がフォローしているユーチューバーやインスタグラマーが自身のSNSなどで「この青汁は本当においしくて、ダイエットのお供に効果的でした」と投稿していたら、「試しに買ってみよう!」と思う人が多いようです。
宣伝=購入から信頼=購入という消費マインドへ
さて、そのテレビCMの中の人気女優と、自分がフォローしているインフルエンサー、両者の違いは何でしょうか。
ひとつは「信用度」です。
ネットの発達で情報があふれている現代では、人々は大手のマスメディアや、お金をかければ放映できるテレビCMのような情報ではなく、「信頼」できる人や媒体からの情報を何よりも求めています。
ある調査ではこんな結果が出ています。「最も信用できるメディアは?」というアンケートに、20~30代の男女の約63%が「SNS」と回答し、「テレビ」はその半分の32%程度にとどまりました。
ひと昔前までは「知る」ことが「購入」に直結していて、「テレビでよく見る有名人の宣伝する青汁だから買う」という人が多くいました。圧倒的に情報が足りない時代では「宣伝=購入」という構図が成り立っていたのです。
しかしいまは、「信頼=購入」という消費マインドができつつあります。そうした状況のなか、これからはインターネットを使った情報発信をしなければモノやサービスが売れない時代へと突入していきます。
インターネットから情報を得ている割合は、いまは若い世代が多い傾向がありますが、高齢者のスマホ所有率は右肩上がりで増えています。
今後、ネットやSNSを使いこなす人がどんどん増えていくことは、想像に難くありません。
情報発信こそが消費者の「信頼」を勝ち取り、情報発信をする人や会社が売れて行くという戦いになっていくのです。
モノが溢れる時代の販促キーワードは「指名買い」「コト消費」
もうひとつ、消費者の購買心理の変化について、大切なことがあります。それは、「モノの消費」から「指名買い」「コト消費」に変化したということです。
モノがあまりなかった時代には、商品という「モノ」自体に価値がありました。
1950年代の後半、日本経済の急成長期には、「白黒テレビ」「洗濯機」「冷蔵庫」が三種の神器と呼ばれて、豊かさや憧れの象徴となっていました。また、1960年代半ばにいは「カラーテレビ」「クーラー」「自動車」が新たな三種の神器として売り出され、頭文字をとって「3C」と呼ばれるようになりました。
いずれも当時は高値で、所有すること自体に価値がある商品だったのです。
ただ「商品が良い」「サービスが良い」だけでは売れない
しかし、現在ではどれも持っていて当たり前になりました。いまは当時の三種の神器のように、ほとんどの人が「どうしても手に入れたい」と切望しているものは、あまりありません。モノ自体の価値が下がっているともいえます。
いま求められているのは、モノではなく「あのお店から購入したい」「商品の裏側にあるストーリーが欲しい」といった心の充実です。これを「コト消費」とか「指名買い」といいます。
例えば、私がコンサルティングをしている国内のとある爬虫類専門店は、TwitterやYouTubeでの発信を通して、多くのファンを獲得しています。
「いつも情報を発信してくれている、顔の見える店長がいるこのお店から買いたい」
「YouTubeでいつも観ている爬虫類に愛着が湧いて買いたくなった」
「しっかりと爬虫類の種類やいままでの歴史を紹介してくれて、よりいっそう購入する気持ちが強くなった」
爬虫類ショップは無数にありますが、お客さんはこうした気持ちからファンになるようです。そこには、商品だけでなく、商品を売る人やその裏側にあるストーリーを重視するという購買心理が働いています。
これは、現代ならではの現象です。
別の事例を挙げると、こんまりこと近藤真理恵さんの書籍「人生がときめく片付けの魔法」が、世界40か国で累計1000万部超えと、記録的な大ヒットを果たしました。
これは「モノを所有するのではなく、整理したり、断捨離したりすることにより人生が好転する」という思想に基づいていると言えます。
まさにこのことは、「モノ」から「心」への価値変化を表しており、現代の消費者マインドを捉えていく大きなヒントになります。
こうした流れは、言い換えると、「今やただ単に商品が良いだけでは売れない時代に突入している」ということです。商品を手に入れるだけでなく、それを手に入れることで「どんな体験を得られるか」「どんな繋がりが生まれているか」を知ってもらい、初めて売れる時代なのです。
動画の何がそんなにすごいのか?
最初にお伝えした通り、YouTube市場はまだまだ発展途上です。そもそも、世の中全体に出回っている「動画コンテンツの量」自体が、あまり多くありません。
インターネット上には無数のコンテンツが存在しますが、ブログや写真などを中心とした「テキストコンテンツ」と、YouTubeなどの「動画コンテンツ」に分けると、両者の投稿数・発信数には圧倒的な差があるのです。
現在どのジャンル・テーマにおいても、テキストコンテンツの量を100とすると、動画コンテンツは1~10程度しかなく、そこには10~100倍の差があります。
例えば、いまGoogleの検索エンジン上で「確定申告 方法」と検索をかけたら、約4580万件のテキストコンテンツがヒットします。そのうち、動画コンテンツはわずか44.7万件ほど。約100倍ものコンテンツ量の差があるんです。
動画コンテンツはなぜ伝わりやすいのか
また、「1分の動画で伝えられる情報量は、LP100ページ相当」という話をしましたが、静止画の情報量との違いについて、より具体的な例を挙げたいと思います。
ここでちょっと、テレビ通販を想像してみてください。
有名なところで「ジャパネットたかた」があります。汚れがよく落ちる家庭用食器洗剤や、ジェットホース、枝切ハサミなど様々な商品が紹介されますが、番組をみているとつい買ってしまいたくなるという人も多いのではないでしょうか。
例えば、家庭用食器洗剤を購入するにあたって、ホームページに綺麗な写真が1つ掲載されているのと、通番番組でその洗剤を実際に使い、油でギトギトのお皿がさっぱりと洗われてつるつるになる映像を見せられるのとでは、どう違うでしょうか。
動画だとグッと伝わるものがあり、使用のイメージや効果が連想されて、ただテキストや写真が掲載されたホームページの何倍も、その商品を「買ってみたい気持ち」にさせられるのではないかと思います。
「WEBサイトやブログなどで情報を発信していくよりも、動画だとはるかに情報が伝わりやすい」のです。
そして、動画を活用することで、商品やサービスがより深く、素早く伝わるという側面に加えて、「人間が伝わってくる」という効果も期待できます。
企業のWEBサイトによくある「会社案内」の代表者挨拶を思い浮かべてみてください。そこに、「近年の経済状況は新型コロナ渦の影響により・・・」などと文章で長々と書いてあるとします。
それよりも、YouTube動画で社長が話している様子が3分程度、ホームページに埋め込まれていた方が、ユーザー側にとっては何倍も親近感が増し、好感度も高まって、伝えたいこともしっかり伝わるのではないでしょうか。
動画にはそうした特徴があり、これを誰でも発信できるYouTubeで行えば、広く多くの人に情報を配布できるというわけです。
ザイオンス効果で依頼が増加
実際、私のクライアントはその効果を実感されています。個人で活動しているある税理士さんは「わかりやすい節税対策」や「確定申告の方法」「ビジネスと税金周りの情報」などを、2年ほど前からYouTubeで発信しはじめました。
最初は動画の撮影や編集などにてこずっていた様子でしたが、2~3ヶ月もすると、スムーズに動画をアップできるようになっていました。
いまでは、チャンネル登録者数が2万人を超え、「私の会社を見てほしい」というコンサルティングの依頼が、毎月10件以上もコンスタントに入ってくるようになりました。
お客さんに依頼した理由を聞いてみると、やはりYouTubeで毎日、税金まわりのテクニックなどを聞いているうちに、親近感が湧いて「この人にお願いしたい」という気持ちが生じてきたそうです。
そうした顧客心理は、マーケティングの世界では「ザイオンス効果」という名前がついています。「人は接触頻度が多くなればなるほど、その対象に対して親近感を持つ」という効果のことです。
その税理士さんは、「毎日動画で観ているうちに、まるで昔からその人を知っているかのような効果」が得られたわけです。
高齢者層もスマホを使いこなし、YouTubeを楽しんでいる
YouTubeというと年齢層の高い人はあまり観ないイメージもあるかもしれませんが、現代では50~70代の方々も積極的にYouTubeで動画を視聴しています。
その理由として挙げられるんが、「文字の読みづらさ」です。これまで主流だったパソコンのブログやWEBサイトなどの文章コンテンツは、その年代の方たちにとって、文字が小さく読みづらかったのです。
しかし、YouTubeであれば動画や音声で情報を伝えられ、テレビ感覚で観ることができます。
先日、私のクライアントである企業の70歳の社長と話していたときに、こんなことをおっしゃってました。
「正月に孫が帰ってくるから、お餅の焼き方を調べようと思ったんだけど、今は完全にYouTubeで調べてるよ」と。
あなたの周りにいる年配の方にも、そうした使い方をしている方がいるはずです。
高齢者層のスマホ保有率が高まっている
事実、総務省のデータではスマートフォンの世帯保有率が2020年は86.6%にのぼり、年代別だと50代は85.9%、60代は67.4%、70代でも38.3%となっています。
また、情報通信機器の世帯保有率の推移としては、2017年あたりからパソコンを抜いてスマホの保有率が目立ってきました。ずっと右肩上がりで伸びており、この先さらに増えていくことは間違いないでしょう。
多くの方が実感しているかと思いますが、電車に乗れば9割以上の方がスマホを操作し、SNSや動画視聴、ゲームや情報収集を楽しんでいます。これは20年前には考えられなかった光景ではないでしょうか。
私の知人の経営者の中には、もはや仕事はスマホひとつで完結しているという人もいます。クライアントや社員との連絡手段はLINEで、そして会議はオンライン会議ツールのZOOMをスマホに入れ、スケジュール管理はアプリで、銀行の支払いや決済などもスマホで完結させているといいます。
そして、仕事だけでなく、空の時間を一番埋めてくれる手段なツールもスマホです。朝起きてコーヒーを飲みながら、通勤・通学の合間に昼休みのちょっとした時間に、寝る前の時間に、そんな隙間時間にスマホでSNSを閲覧したり、調べものをしたり、YouTubeで動画を観たりと、1日をスマホとともに過ごす人が圧倒的多数です。
いまやスマホは、ラジオになり、本になり、ゲーム機になり、パソコンになり、辞典になり、すべての機能を兼ね備えているのです。
それに伴い、動画広告市場も年々倍々ゲームに近い勢いで造花しています。2018年と2023年の比較では、3倍近くまで動画市場の成長が見込まれ、特にスマートフォンでの成長は顕著です。
どんどん人が動画、特にスマホでの動画視聴に入っていき、その分、閲覧料を原動力とする広告も増えていく。今後10年で、この動画市場はさらに10倍にも増えて行くとも言われています。
狙うべきは「検索ハウツーコンテンツ」というジャンル
いかにYouTubeという媒体が活況で、時代的にもいまはまだ有利ということがわかったかと思います。じゃあ自分も番組を作ろうと、著名なユーチューバーに倣って「スライム風呂に入ってみた」とか「ウーバーイーツ買い占めてみた」といった、エンタメ系のコンテンツを発信していくべきでしょうか。
もちろん、そんな必要はありません。あなたがやるべきことは、「自分のビジネスに繋がるお客様への情報提供」であり「信頼に繋がる発信」です。くれぐれもエンタメ路線に走らないでほしいと思います。
特に昨今は、コロナ渦で広告やテレビ番組などの撮影が延期となった影響もあり、芸能関係者が次々とYouTubeに進出してきました。
有名な芸能人や文化人、スポーツ選手や「インフルエンサー」と呼ばれるような人たちは、既に知名度や影響力を持っています。
なので、YouTubeを始めたばかりでも、すぐにフォロワーがつきやすい傾向にあります。また、そういった人たちは人前に出ることに慣れていて、トーク力が高く、人々を楽しませるツボを押さえているので、間違いなく一般人よりも「エンタメ向き」です。
したがって、一般の人はわざわざその市場で戦うべきではありません。そこはレッドオーシャンです。よほどの特異性がない限り、エンタメ系コンテンツを発信しても彼らに勝てないどころか、本業のビジネスには繋がりにくいと考えたほうがいいでしょう。
YuoTubeで学んで五輪のメダリストに!?
では、ビジネスを加速していきたい人はどういったコンテンツを発信していけばいいのかというと、最初に少し触れた「検索ハウツーコンテンツ」という市場です。
「週末にでかけたとき、お茶するお店を探したい」とか、「急に腰が痛くなって困った」という場合、多くの人がGoogleやYahooなどの検索窓に、「カフェ 渋谷 オススメ」「腰痛 直し方」などと入れて、検索していると思います。
これが、コンテンツのネタになるのです。そうした検索ネタは、いまやYouTubeの検索窓でも同じように検索されています。
YouTubeはエンタメ系に限らず、実用的なコンテンツでも発展を遂げており、家具の組み立て方から、家庭菜園の方法、トイレの黒ずみの取り方、洗顔フォームの使い方、歯の黄ばみ取りの方法、美味しいプリンの作り方まで、教えてくれるんです。
驚くことに、YouTubeで「寿司の握り方」を学んで実際に店を出してしまった板前さんや、やり投げの方法をYouTubeで学んで、オリンピックの銀メダリストになってしまったケニアの選手も実在します。
知りたいことを「いつでも観られる」という圧倒的利便性
YouTubeでは、1分であろうと1時間であろうと、コンテンツの長さを自由に調整してアップロード可能できるのも魅力的な点です。
これがテレビ番組だったら、予算をたっぷりかけて様々なセットを用意し、最低でも10分くらいの長さのコンテンツを用意しなければなりません。
そして何より、テレビとは違って即時性のニーズに優れている、つまり、「いつでも観たいものを観られる」というのがYouTubeの素晴らしいところです。
従来のテレビ番組では、放映時間に合わせて観なくてはなりませんでしたが、YouTubeなら、検索窓に指定のキーワードを入力すれば、すぐに目的の動画を見つけることができます。
いわば、動画版のWikipedia的なプラットフォームとしてめきめき成長しているのがこのYouTubeなのです。
こうしたニーズを考えれば、例えばあなたが魚屋さんであるならば、「魚のさばき方」や「調理の仕方」「家庭でできる料理のノウハウ」といったことを発信すべきです。
一般のユーザーは、そうした情報を求めています。
そのような実用系のコンテンツの視聴者数は、急増はしないかもしれませんし、エンタメ系の数百万再生のコンテンツには及ばないかもしれません。
そうだとしても、気にしないでください。
いったんサイト上にアップすれば、永続的に検索に引っかかります。
つまり、人々のニーズを半永久的に満たす「ロングテールのコンテンツ」としてWEB上に存在し続けるのです。
私自身、チャンネルを開設したという話をしましたが、いまでもYouTubeのプロデュースやコンサルティングを提供するかたわら、複数のチャンネルを持って動画を投稿しています。
そのうちの1つは「就活チャンネル」で、自分自身が以前行っていた「就活のコツやノウハウ」を動画にしています。1動画あたり数十万再生の動画もいくつかあります。
また、私のクライアントである中小企業診断士の方は、新型コロナウィルスの期間に国から支給された「特別定額給付金のもらい方」や企業向けの給付金である「持続化給付金の申請方法」などの動画を投稿し、数十万回再生されています。
こんなにもYouTubeでハウツー物のコンテンツが再生されているんは、動画が音声や動く画像によって、物事をわかりやすく伝えられることの現れではないでしょうか。
いずれは動画が検索エンジンのトップに?Googleの考えていること
インターネットを使いこなし、ビジネスに有利な活用をしていくには、プラットフォーマーの気持ちを考えなければなりません。
この場合は「Googleはどうしてほしいのか?」を考えることが大切です。
結論からいうと、Googleは「YouTubeをたくさん活用してほしい」と思っています。
実際Googleでは、YouTubeの動画枠を検索結果のトップに設ける仕組みを取り入れてます。ひと昔前までは、動画のコンテンツが検索で上がってくることはありませんでした。
これはつまり、「我々Googleは今後、さらに動画を検索で重視します」というメッセージです。
試しに「オムレツ 作り方」とGoogleの検索エンジン上で検索してみると、動画の検索コンテンツが上位に表示されるはずです。
もちろん、他の言葉で検索しても、検索結果の上位にこのような動画コンテンツタブが表示されます。そして、その動画の中でも「YouTubeの動画」が多い傾向にあるのです。それはなぜでしょうか。
YouTubeはGoogle傘下のサービスであり、利用者や視聴者が増加しているとお伝えしました。つまり、検索結果の上位に動画コンテンツを表示することで、多くの人にGoogleのサービスを利用してもらえるというわけです。
また、YouTubeはGoogleの貴重な収入源ですから、そのYouTubeの動画に広告が挿入され、それをユーザーが視聴することで、Googleの売上が向上します。
そういった世界最大手の検索エンジンであるGoogleの思惑もあり、今後YouTubeは検索の面でもさらに優遇されていくことになると考えられるのです。
YouTube集客の実例
検索ハウツーコンテンツをビジネスに繋げた例について、もういくつかご紹介したいと思います。ここでは、YouTube動画をリアル店舗やネットショップへの集客にうまくつなげている例を取り上げます。
検索ハウツーコンテンツを上げて集客した具体例①
感激安心のお花屋さん ゲキハナ
「自宅でできる園芸のノウハウ」や「初心者向けの育て方」などについて、社長が個人名でチャンネルを作り、動画で丁寧に親しみやすく伝えています。
ザ・お店という見せ方ではなく、花屋の店主が友人に話しかけるような、フランクな言葉遣いや表情で語られているのがポイントです。
それにより「純粋なファン」として普段から動画を視聴する人が増えていると考えられます。
視聴者から長期的な信頼を得られれば、「今度、普段から見ているこの方のお店から商品を買ってみようかな」という心理作用が働きます。その結果、動画の説明欄に貼ったURLなどから、自社やネットショップへの誘導、販売へと繋がります。
検索ハウツーコンテンツを上げて集客した具体例②
中華一筋
美味しい中華料理や、まかない料理の作り方、スタッフとの掛け合いなどを面白く伝えています。再生回数400万回以上の動画が複数ある、人気チャンネルです。
まず、「食」というジャンルは普遍的に高いニーズがあり、YouTubeでも再生回数が伸びやすい傾向にあります。
その中でもこのチャンネルが注目を集めている原因としては、プロならではのテクニックや調味料、器具の見せ方、料理の豊富なアレンジ、エンタメ要素などが考えられます。
「スタッフとの掛け合いが面白く、いつも見ています」というコアなファンを得ており、その結果、説明欄のURLから、シャルやパーカー、コップなどの自社商品や、中華料理のネットショップへの誘導に繋がっています。
検索ハウツーコンテンツを上げて集客した具体例③
スグレモン自動車用品
自動車に使えるクリーナーや掃除用品など、汚れ落とし系のスッキリコンテンツを配信。この会社自身、車のクリーナー関連商品を販売しているのですが、動画内で取り上げている自社商品は少なめです。
こうした「汚れが落ちる系」の動画は、YouTubeならではのニッチなコンテンツと言えるでしょう。古い道具を綺麗にしたり、虫歯を治療したり、耳掃除をしたり、視聴者が「綺麗になってスッキリした」と感じるようなコンテンツは、動画で観るとクセになるものがあるようです。
視聴者は「使える商品が紹介されている」という流れ、感覚で見ることができるんで、「商品の宣伝を見せられている」というネガティブな印象を持たれにくいのです。
検索ハウツーコンテンツを上げて集客した具体例④
魚屋の森さん
若くて元気のある鮮魚店の二代目“森さん”が、魚のさばき方や、自身で作るまかないなどの動画をアップしています。
森さんの“キャラが立っている”のが特徴です。
「飾らない、ほんわかした雰囲気、笑顔が素敵」といったところが好評で、固定ファンを獲得。「魚屋にこんな人がいるんだ!」というギャップとも相まって、視聴者数を急激に伸ばしています。
結果的に、動画説明欄からの居酒屋への集客、自社の魚介類のネットショップに誘導ができているようです。
中国に見る「ライブコマース」というさらなる可能性
YouTubeには、単なる情報発信にとどまらず、「ライブコマース」としても活用できるという特徴があります。
ライブコマースとは「オンライン販売」と「ライブ配信」を組み合わせた販売形態のことです。消費者がリアルタイムで商品に対する質問やコメントをしたり、販売者がそれに応えたりして、双方向でコミュニケーションをとりながら買い物、販売ができます。
近年では大手企業も、このライブコマースを取り入れており、食品・小売は三越伊勢丹、化粧品・コスメは資生堂、アパレルはベイクルーズやシップスなどが参入しています。
これまでのECでは、お客さんがリアルタイムで商品への質問などをしながら買い物をするというのは不可能でした。ECサイトに陳列されている商品やサイズ、カラーバリエーションを、写真とテキストの情報を頼りに購入するまでにとどまっていました。
少し進んでいる企業でも、チャット機能などが限界でした。
しかし、ライブコマースによって、「より精度の高いお買い物体験」を届けることが可能になったのです。お客さん側としては、静止画やテキストだけでは感じられなかった商品の使用感がわかりやすく、詳しい情報を得られます。
日本でもライブコマースの動きが盛んになっている
このライブコマースは、世界各国で取り入れられ、近年のブームになっています。例えば、中国では、世界でも最も盛んにライブコマースが利用されており、もはや日常のワンシーンとなっています。
目的の多くは販売商品のPRで、インフルエンサーと呼ばれる人によってライブ配信されるケースが主流です。
企業のコンサルティングなどを手掛けるデロイトの統計データによると、2018年時点での中国におけるライブコマース市場は約44億ドル。
前年比132%という伸び率で、推定視聴者数は4億5600万人、毎日、4000以上のアカウントが合計15万時間以上のコンテンツを配信する市場になっているのです、
中国国内のライブコマースのうち、売れ筋のカテゴリーはファッション・美容関連、生鮮食品などのジャンルです。
中国で最も使用されているECプラットフォームのタオバオも、ライブコマースを導入しており、60万以上ものアイテムをライブコマースで購入することができます。
一方、日本でのライブコマースは、まだまだブルーオーシャンの市場です。2017年頃からライブコマースという言葉が浸透しはじめたという程度です。
しかし、2020年のコロナ渦のあおりを受け、非接触・非対面形式の販売の流れが、日本でも盛んになってきました。その流れから、政府としても、持続化補助金やIT導入補助金などを用意し、コロナ渦の影響を鑑みた非接触・非対面の販売ができるITプラットフォーム、EC構築を、積極的に支援をする動きを見せています。
意外と知らない!YouTube攻略の基本
新しいツールを取り入れるとき、それについてよく知ることは、ビジネスを成功させる条件のひとつです。そこで本記事では、YouTubeの成り立ちや仕組みについて、見て行きたいと思います。
そもそもYouTubeとは何か
いまや多くの人に親しまれているYouTubeは、2005年にアメリカで誕生しました。創業者は、元PayPalの社員であったチャド・ハーリー、スティーブ・チェン、じょーど・カリムです。
このサービスを着想したきっかけについて、ジョード氏は、2004年にジャネットジャクソンが起こした第38回スーパーボウルのハプニングや、同年に発生したスマトラ島沖地震の動画を事件後にインターネットで検索しても見つからなかったことだったと言います。
有名な話ですが、YouTubeに初めてアップロードされたのは、カリム氏が動物園の象の前にいる動画で、いまでも閲覧することができます。
その後YouTubeは、2006年にGoogleに16.5億ドルで買収され、現在はGoogleの子会社の1つとして運営されています。そしていまやYouTube上には、毎分500時間以上もの動画がアップロードされているのです。
あらゆる人にチャンスの扉が開かれている
YouTubeの特徴は、力や経済力の有無に関係なく、すべての人にチャンスを与えられていることです。誰もが動画を閲覧するだけでなく、評価やコメント、そしてアップロードをすることができます。
お金がなくても、人が全くいない田舎に住んでいても、人と話すのが苦手でも、誰でも簡単にインターネットを介してコンテンツをアップロードすることができるのです。
まさに、これまで発見されてこなかった個人やビジネス、コンテンツにとって、希望のあるプラットフォームとなっています。
その証拠に、YouTubeの公式ページにはこう書かれています。
「YouTubeの指名は、表現する場所をあらゆる人に提供し、その声を世界中に届けることです。YouTubeは、人々が自らのストーリーを発信し、コミュニティを共有、形成するための助けになりたいと考えています。
また、YouTubeは価値観として、次に示す4つの自由を掲げています。
- 表現の自由
- 情報にアクセスする自由
- 機会を得る自由
- 参加する自由
つまり、YouTubeとは、ビジネスを通じて、あるいは多くの個人が平等に自由に発言し、情報や機械を得て、コミュニティや新たな世界に踏み出していくためのきっかけとなるような場所だと言えるのです。
YouTubeはなぜ「Googleビデオ」に勝ったのか?
そもそも、GoogleはなぜYouTubeを買収したのでしょうか。
皆さん、もうおわかりですね。そう、これから動画がますます主流の時代になってくるということをGoogleが認知し、その世界を実現するためです。
GoogleがYouTubeを買収する前の2005年、実はGoogleはYouTubeのような動画プラットフォーム「Googleビデオ」を開発していました。
そのGoogleビデオが目指していたところは、オンラインで映画やドラマを配信するためにハリウッドスタジオと契約することでした。
当時、Googleはそれらの商業ビデオを配信するために、各種コンテンツメーカーと交渉を初めていましたが、それと並行して「ユーザー自身も投稿ができる」という機能を付けていました。
つまり、「プロが作った商業コンテンツ」と、「一般ユーザーが作ったコンテンツ」が混合しているような状態でした。
意図せず、結果として面白いことが起きました。Googleが苦労してライセンスを獲得した「プロが作った商業コンテンツ」ではなく、「素人が作った一般動画」の方がはるかに再生回数が多く、人気となったのです。
Googleビデオで最初に“視聴回数100万回”を達成したのは、中国人の大学生2人が広州美術学院の寮で、バックストリートボーイズの曲を口パクして熱唱している動画でした。
こうした初期の動向を踏まえ、YouTubeは完全に素人が投稿するプラットフォームとして舵を切ります。プロではなく一般ユーザーが作るコンテンツの方が断然、可能性があることをGoogleは察していたのです。
その結果Googleは、2006年にYouTubeを自社の過去最高額である16億5000万ドルで買収し、このプラットフォームを一新して、GoogleビデオをYouTubeへと移行させました。
そしていまでは、先述したように一般人の動画、特にハウツーコンテンツは、人々の検索ニーズを満たすだけではなく、世界的なプラットフォーマーであるGoogleという検索エンジンの次なる一手として大きく成長しているのです。
Googleは、こうした動画コンテンツ主流の時代と、自社で持つ圧倒的な検索エンジンとの親和性を先読みしていたというわけです。
YouTubeはGoogleが所有するテレビ局
YouTubeを攻略して味方につけ、自社や商品のファンを作るには、YouTubeという媒体の考えていること、特に「YouTubeは何をしてほしいのか」をとらえなくてはなりません。
結論から言えば、「YouTubeはGoogleが所有するテレビ局」と考えると、各段に攻略しやすくなります。YouTubeは、クライアントからの広告出稿によりビジネスモデルが成り立っているのです。
YouTube上の動画は無料で視聴できる代わりに、動画の最初や途中に広告動画やバナーが表示されるようになっています。企業などクライアントは、YouTube側からこの広告枠を購入し、広告費を支払っています。
テレビ局のビジネスも同様です。番組の間に挿入されるCMを企業に買ってもらうこと、つまり広告費、スポンサー費用によって成り立っています。面白い番組を作るテレビ局や、視聴率が高い番組には、必然的に多くの視聴者が訪れます。
「人気番組にCMを流したい」と思うのが、スポンサーの心理で、これはYouTubeにも同じことが言えます。YouTubeは、あなたが広告を自分で挿入するかどうかによらず、あなたのチャンネル・番組が「広告を挿入するために価値があるかどうか」を常に判断しています。
ですから、あまり視聴者を楽しませられていないチャンネルや、数カ月更新のないチャンネルには、YouTube側も評価を落としているのです。
その逆に、しっかり定期的に動画をアップしているチャンネルや、視聴者が離脱せずに動画を閲覧しているチャンネルは「YouTubeのおすすめ」として積極的に押し出してくれます。
YouTube側としても「人気の番組になり得るポテンシャル」をしっかり評価しているのです。
YouTubeを攻略するからといって、取り立てて新しい考え方を持つ必要はなく、「自分がお金を出す企業のスポンサーだとしたら、どういう番組を作っていると広告を出稿したくなるのか?」という視点を持っていると答えがおのずと見えてくるでしょう。
そうすれば、細かいYouTubeのアルゴリズムの攻略や、動画の形式、長さはどうすればいいのかといった、本質的ではない問題にとらわれずに済むようになります。
人はどこからYouTubeにたどり着くのか「流入経路」の話
とはいっても、アルゴリズムについては抑えておいた方がいいこともあるので、簡単にご紹介します。
インターネット上のプラットフォームを動かしている情報処理の仕組みを「アルゴリズム」といいます。ここでは、「YouTubeがどのような動画を誰に出しているか」という仕組みについて言及します。
ビジネスをしていく上で考えるべきなのが、「YouTubeの視聴者がどこから動画を見つけてくるか」という「流入経路」です。
あなたがYouTube上で動画を視聴するときのことを思い浮かべてみてください。
様々な経路からYouTube視聴に至っているかと思います。検索結果の上のほうに表示されたものをなんとなく観る場合や、あるいは、よく視聴するチャンネルの「関連動画」や「おすすめ」として表示された動画が気になって観るケースなどがあると思います。
関連動画やおすすめとして何が表示されるかは、視聴者によって異なります。そこには基本的なアルゴリズムが働いているのですが、まず押さえておきたいのは、アルゴリズムは「人が作っている」ということです。
YouTubeの場合、その運営主体であるGoogleが作っているわけですが、ではGoogleは何を考えているのでしょうか。難しい話を抜きにして一言でいうと、「たくさんYouTubeを観て欲しい」と思っています。
ですから、人々がたくさんYouTubeを観るようなプログラムを設計しているのです。
「なんとなくYouTubeを眺めていたら、1~2時間経過していた」
という経験はありませんか。それは、Googleが日々考えて精度を上げているアルゴリズムによる仕業です。
人々が動画視聴に至る経緯とは
それでは、多くの視聴者はYouTube上の動画をどこから発見して閲覧しているのでしょうか。Google検索による流入以外には、主要な経路として次のようなものがあります。
【YouTube検索】YouTube検索窓での検索です。「肉じゃが レシピ」などと検索したときに一覧で出て来ます。
【ブラウジング機能】YouTubeからの「おすすめ表示」での流入。YouTubeのトップページなどに、「あなたへのおすすめ」として表示される動画です。
【関連動画】他の動画の「関連動画」表示からの流入です。動画を視聴していると、パソコンなら動画の右横、スマートフォンなら動画の下側に一覧で表示される「視聴動画に関連した属性の動画」のことです。
【チャンネルページ】人々があなたの「YouTubeチャンネルページ」を訪れ、そこから動画を視聴するという経路です。
【終了画面】動画の最後の画面で、あなたに合った動画や特定の動画が表示されるかと思います。そこからの流入です。
【外部】YouTubeのURLリンクがSNS上でシェアされて視聴者が閲覧したり、あるいは、ホームページなどに埋め込まれた動画からの流入です。
【再生リスト】YouTubeには、自分のチャンネルの動画をテーマごとにまとめられる「再生リスト」という機能があります。そのリストからの流入です。
自分の動画を効果的に見つけてもらうには?
視聴する側の流入経路がわかったところで、今後はあなたがYouTubeを発信する側として「どうやって自分の動画を効果的に見つけてもらうか?」という話をしたいと思います。
結論をいうと、「YouTubeからのおすすめ」を攻略することが大事です。先述の流入経路でいえば「ブラウジング機能」と「関連動画」です。この2つからの流入に乗れるコンテンツ作りを目指しましょう
YouTube上で再生回数の多い動画の流入経路は、まとめると次の3点です。
- ブラウジング(YouTubeトップのおすすめ)
- 関連動画からの流入
- YouTube検索からの流入
再生回数が多い、つまりヒットしたり、伸びたりする動画の流入経路がこのような結果となるのはなぜだと思いますか?
「YouTubeはGoogleのテレビ局」という話を思い出してください。「クライアントの広告出稿でビジネスが成り立っている」というのが、YouTubeの儲けのしくみでした。
ユーザーがYouTubeを観れば観るほど、より多く広告も閲覧されることになります。閲覧回数などの成果報酬型の広告形態をとっているYouTubeにとっては、より多く広告が閲覧されることでより多く広告売上が立つ、すなわち、より多くYouTubeの儲けになるのです。
そのため、YouTubeとしては「何としてでもユーザーをYouTubeの中に留めておき、たくさん動画を観てほしい」わけです。
そうなったときに、ブラウジング(おすすめ動画)と関連動画というのあh、ものすごく効果を発揮します。
「どの番組がおすすめとして表示されるか」は、人によって異なります。
YouTubeは、ユーザーの「閲覧履歴」「評価」「Google上での検索履歴」などを総合的に判断して、おすすめ動画や関連動画を決めているのです。
例えば、あなたが猫が大好きだとして、YouTube上でたくさん猫の動画を観ていたりすると、あなたのYouTubeトップのおすすめや関連動画に、猫の動画が多くなるよう、YouTubeのAIによってカスタマイズされています。
したがって、YouTubeを攻略するには、いかにユーザーの「おすすめ動画と関連動画に乗るような動画を作っていくか」がポイントになってくるのです。
広告収益化は継続のモチベーションになる
本記事でお伝えするYouTube活用の目的はビジネスの窓口、あるいは会社や商品・サービスの潜在的な認知向上ですが、せっかく動画をアップするなら「広告収益」が入るに越したことはありません。
月に少しでも広告収益があると、チャンネル運営を頑張っている“報い”を感じやすく、継続するモチベーションにもなるでしょう。
YouTubeの動画発信者は、一定条件を満たすと、自分の動画に広告を挿入することができるようになります。この広告の閲覧効果に応じて、クライアントがYouTubeに支払った広告をシェアするような形で、発信者は収益が得られるのです。
視聴者の属性や広告の種類によって単価が変わりますが、相場としては1再生あたり0.1~1円ほどの広告収益が、YouTubeから発信者に支払われます。
「ユーチューバー」と言われる人たちは一般的に、この広告収益を得るために動画を作成しており、広告を差し込んだ動画のパフォーマンスに応じて、YouTubeから広告料をもらっているのです。
発信者側としては、「YouTubeという広告プラットフォームを使う側の視点」を持つことが大切です。
もちろん、あなたが広告主となり、自分のチャンネルや商品・サービスの広告を、YouTube上に出稿することも可能です。予算は少額から始めることができ、極端な話5000円でも設定可能です。
自社の商品やサービスに合ったフォーマットを選べば、効果的な宣伝をすることができます。
チャンネル登録者数と広告収益の目安
参考値として、チャンネル登録者数と広告収益の目安を紹介します。これはあくまで1つの目安であって、実際はジャンルや投稿頻度によって広告収益の額や桁数が大きく違ったりもします。
また、動画の長さによって、途中でたくさん広告が挿入できる場合は、1再生回数あたりの広告収益も比例して高くなります。
| 登録者 | 月間再生回数 | 月間広告収益目安 |
| 1000人 | 2万回 | 2000~6000円 |
| 5000人 | 10万回 | 1万~3万円 |
| 1万人 | 20万回 | 2万~6万円 |
| 3万人 | 60万回 | 6万~18万円 |
| 5万人 | 100万回 | 10万~30万円 |
| 10万人 | 200万回 | 40~60万円 |
| 50万人 | 1000万回 | 100万~300万円 |
| 100万人 | 2000万回 | 200万~600万円 |
ビジネス系チャンネルの落とし穴と対策
YouTubeをビジネス活用する上で、初心者が陥りやすい共通の失敗ポイントというものがあります。それを事前に押さえておくことで、「何が正しいのだろうか」と試行錯誤する最初の半年~1年ほどの時間を、短縮することができます。
「遇者は経験から学び、賢者は歴史から学ぶ」という言葉があるように、自分の経験だけに頼るのではなく、いろいろなチャンネルの軌跡から見れる“失敗ポイント”をしっかり確認しておきましょう。
押さえるべきは「ファネル」の上の方
失敗ポイントの最もたるものといえば、「視聴者の状態を理解しない発信をしてしまう」ことです。具体的には、いきなり自社商品やサービスの紹介から始めてしまったり、ビジネスの売り込みを始めてしまったりするチャンネルのことです。
お客さんがモノやサービスを購入する際には、「認知」「興味関心」「比較検討」「購入申込」というフローをたどっていきます。
集客にあたっては、この逆のフロー(ファネル)で考えることが非常に重要になってきます。
YouTubeは、ライトな情報であるファネルの上のほう、「認知」「興味関心」のフローが得意な媒体です。
いきなり「購入申込」に繋げようとする企業が多いですが、それではなかなかうまくいきません。9割がたの企業がここから始めてしまいます。
例えばスーツ店がチャンネルを開設して、最初から「購入申込」に繋げようとすると、「当店の取り扱いスーツ種類」「当店のコロナの取り組み」「初めて入店される方はどうすればいい?」などをテーマにした動画になります。
観る側としては、いきなり商品を紹介されても、あまり興味を持たない人が多いものです。一般の視聴者が気に留めるような内容で始めることが大切です。
スーツ店のチャンネルであれば、「ネクタイの結び方とコツ」「女子受けが良いスーツスタイル」「今さら聞けないボタン留めルール」などが、一般視聴者受けしやすいでしょう。
他にもわかりやすい例を挙げてみましょう。
私の友人に化粧品を販売している人がいます。ある日、「YouTubeを始めました」という連絡がありました。私は「頑張って!」と返事をし、楽しみにしていました。
しかし、数カ月たったある日、その友人から「動画を20本ほどアップしているのに、ほとんど再生されていない」という嘆きの連絡がありました。それもそのはず、動画を観てみると「自社製品の紹介」しかしていなかったのです。
自社商品の紹介だけに留まっているのであれば、視聴者からは「なんだ、ただの自社の宣伝か」と思われてしまい、ほとんど見向きもされません。
では、このチャンネルはどうしたらよいのでしょうか。
答えは、「化粧品に関して一般人が知りたい、汎用的なキーワードに沿った内容」を扱うことです。例えば、「就活メイクの方法」や「時短メイクの方法」「肌がきれいになる洗顔ケア」「デート時のリップ選び」など、女性の多くが気になるような言葉をキーワードとして入れていくのです。
私は友人にそのようにアドバイスをしました。すると、そのテーマに沿った内容の動画は、すぐに数本が10万再生を超えるなどの伸びを見せていました。
YouTubeで発信するからには、YouTubeの得意な層「認知」「興味関心」にフォーカスしたテーマ、赤の他人でも興味を引くテーマを最初に投稿すことが効果的なのです。
大衆受けならこのジャンルを狙おう~テーマ選び~
「お金」「健康」「人間関係」「恋愛」「ダイエット」
これらのテーマは普遍的に多くの人が興味を持つ分野です。10年後、20年後も変わらずに人々が欲しているジャンルの情報といっても過言ではないでしょう。
短期的には自社の商品には結びつかない場合もありますが、多くの人の興味を引くことに成功し、あなたやあなたの会社の人気が広がれば、「なんでもいいから、あなたの商品が買いたい」「この会社のファンだから、何か買って貢献したい」という視聴者の応援心が生まれてきて、結果的に自社の商品の売上に繋がってくるものです。
例えば、マコなり社長のチャンネルで言うと、動画のジャンルは「仕事ができない人の特徴」や「寝る前に絶対やってはいけないこと」などの「仕事や生活のライフハック」「自己啓発」「仕事術」などの分野です。
しかし結果的にマコなり社長のファンができ、彼が出す商品やオンラインサービス、はたまた代表を務めるプログラミングスクールの「テックキャンプ」などへの集客に繋がっています。
テーマはたくさん扱うべきか?統一すべきか?
多くのYouTubeチャンネル運営者から、「内容に統一性を持たせた方がいいのか、それとも伸びる動画は何でもやったらいいのかわからない」といった相談が寄せられます。
「切り口は最初、専門的なものに統一した方がいい」というのが、私の見解です。
まずは1つの切り口で、そのチャンネルに合った動画をあっぷしていきましょう。
例えば税理士の方であれば、「個人事業主や中小企業の社長向けの“節税術”」を大テーマとし、そのテーマに即した「経費申請の賢い方法5つ」「個人事業主が法人成りで節税するための売上目安3つ」などの動画をアップしていくのがいいでしょう。
悪い例で言うと、税理士として集客したいのに、エンタメ系の「メントスコーラやってみた」や「料理動画」、自分語りの「起業術」など、目的からそれた動画をいろいろとアップしてしまうケースです。
YouTubeチャンネルで発信しようという人は意識が高く、動画制作の引き出しやネタがたくさんあって、どんどんアップしてみたくなるのだと思います。
その気持ちはわかりますが、そこはグッと堪えましょう。
視聴者がビジネス系のチャンネルを望んでいるのは「具体的なノウハウや情報」だということを常に意識しましょう。
動画での「顔出し」は必須?
よくクライアントから「顔出し」について、絶対出すべきかと質問をされるんぼですが、端的に言うと、「出した方がよいか、個人の場合は出さなくても効果は見込める」というのが私の回答です。
例を挙げると、企業やアイドルグループのチャンネルで、複数人が顔出しをせずにYouTubeに動画をアップしている場合は、さすがに視聴者は違和感を感じてしまうでしょう。
しかし、個人のチャンネルで顔出しなしであれば、視聴者は「顔を出せない、もしくは出したくない人なんだな」と割とすんなり受け入れてくれます。
「アニメーション+本人の声」「Vlogなどの動画+テロップ」といった顔を出さないスタイルの動画でも、チャンネル登録が数十万人以上になるほど人気の動画はたくさんあります。
「ザイオンス効果」の意味でも顔を出すのが一番ですが、出せない場合は出せないなりの工夫をしたり、戦略を取ればいいのです。
初期にはニッチなテーマに手を出してはいけない
YouTubeチャンネルを立ち上げて動画を配信したものの、再生回数が一向に上がらない・・・というパターンは他にもあります。それは「他のチャンネルがやっていないオリジナルのテーマで勝負しよう」と考えてしまう場合です。
このことは、YouTubeの視聴数を伸ばす上で重要な「関連動画」の話に繋がっていきます。ニッチなテーマではなく、すでに他のチャンネルがたくさん動画を出しているような人気のテーマであれば、たとえそれが後発であっても「他の動画の関連動画」として掲載されやすくなるのです。
しかし、他のチャンネルがほとんど出していないテーマの動画であれば、検索数やニーズが極端に少ないジャンルである可能性が高く、「関連動画」からの流入も少なくなってしまいます。
目安としては、チャンネル登録者数が1000人に届くまでは、基本的に「ヒットしている動画テーマを攻めましょう!」という戦略が効果的です。徐々に視聴者がつき、「このチャンネルが出してくれる情報なら有益に違いない」という認識まで持っていければ、オリジナルのコンテンツを出しても伸びていきます。
YouTubeで超高額商品は売れない
YouTubeでオンラインサロンやメンバーシップ、あるいは様々なバックエンド商品を提供するにあたって「価格設定」は視聴に行うべきです。
具体的な額でいうと、YouTubeチャンネル経由のお客さんに20万円以上の商品を売るのは厳しい傾向があります。バックエンド商品の価格設定としては、単価数千円~20万円の範囲がベストです。
なぜ高額だと売れないのか?
特にビジネス系の情報発信系のチャンネルに共通して言えることですが、YouTubeからあなたやあなたの会社の存在を知るに至った視聴者は「無料で情報を仕入れたい」「ライトな情報を仕入れたい」と思っているケースがほとんどです。
要するに、そこまで本気でお金をかけて勉強する媒体と捉えていないお客さんが多いのです。
これが資格の学校や大学受験の予備校、ビジネス英語の学校などであれば違います。
本人にとっては死活問題なので、数十万~100万円以上のお金を払ってでも勉強したい、そのための商品やサービスを購入したいと思う人もたくさんいるわけです。
しかし、YouTubeでは、「空き時間などにサクッと無料で情報が知れたらいいな」という風に思っている視聴者が多いということを認識しておいてください。
もちろん、例外もありますが、一度もあなたと会ったことがない不特定多数に向けて、YouTubeで商品やサービスを売りたいと思った場合は、20万円以内に留めるのがいいでしょう。
月額のオンラインサロンの料金であれば980~4980円くらいの範囲に設定し、少し安めの印象を与えるのがオススメです。
これがいきなり「オンラインサロン月額1万円」となると、相当影響力のあるインフルエンサーや著名な社長などでなければ、集客は厳しくなります。
また、単発のバックエンドの商品を売りたい場合は、3万~5万円以内に留めるのがオススメです。
例えば、英語を教えるチャンネルを運営している個人や企業が、いきなり50万円の英語勉強のオンラインパッケージ商品を作っていくら動画で宣伝しても、売れません。チャンネル登録者数が数万~数十万人以上であっても、です。
スマホ1台でできる撮影オペレーション
YouTubeで動画をアップするために「撮影して、編集する」と考えると、「なんだかとても大がかりなことをしなければいけないな」「機材や道具には、多少高くてもしっかりしたモノを揃えないといけない」と思ってしまう人がとても多いです。
しかし、最初は簡易なモノでいいのです。ビジネス系のチャンネルでは、スマホ1台だけで撮影した動画で、登録者数十万人というチャンネルはたくさんあります。
YouTubeで大切なことは「映像の綺麗さや編集のクオリティ」ではなく、「テーマ」や「内容」なのです。
自分で撮影や編集がガッツリできる、会社にそのような環境が整っているといった場合を除いては、簡易な撮影オペレーションでとにかくスタートしましょう。徐々に撮影を習慣化できて慣れて来たら、少しずつ撮影や編集のクオリティを上げていけばいいのです。
スマホ撮影&アプリ編集、クオリティは3割でOK
では実際にどうすればいいかというと、「Vlog系」というジャンルの場合は、編集の技術が求められますが、ビジネス系ならば撮影はスマホ、編集はアプリ、あるいはデフォルトのパソコン内蔵ツールでの編集だけでも大丈夫です。
例えば撮影はiPhone、スマホ3脚、ピンマイク、編集はパソコン(Mac)内蔵のiMovieがあればOKです。
これだと、手持ちのスマホ以外でかかる費用は5000円程度と、かなり費用が安く抑えられます。編集にかける時間の目安は10~15分くらいです。
ビジネス系はこのパターンで撮っている方がかなり多い印象です。
視聴回数やチャンネル登録を伸ばすコツとしては、最初は数で勝負すること。クオリティは3,4割でいいので、とにかく動画をアップする習慣をつけましょう!YouTubeに「定期的に動画を上げているチャンネルなんだ」とみなしてもらうこと、そして、実際に出してみて「こういう動画がヒットするのか」という傾向を掴むことが大事です。
YouTubeでの話し方のコツ
YouTubeを始めたいけど始められないという方の中には、「私はしゃべりがうまくないんです」という方が一定数いらっしゃいます。
「アナウンサーみたくしゃべれないんです」とか「普段、人前でしゃべったこともないし」とおっしゃいます。
その気持ちもわかりますが、うまく話す必要はなく、「友人やお客さんに話すいつもの感じ」で話すことができれば、それで十分です。
なぜでしょうか。それは、YouTube視聴者には「アナウンサー感」「オフィシャル感」「起業の真面目感」といった固いイメージよりも、普段のありのままの状態の方が親近感が高まる傾向にあるからです。
試しにYouTubeで、自分のよく見るジャンルを検索してみてください。「iPhone 裏技」「就活メイク」「SEO攻略」など。数十万回以上、再生されているような動画でも、意外と話し方は普通だと感じ取れるのではないでしょうか。
ただし、撮影となると極端に言葉が出なくなってしまう、言い間違えてしまうという場合は、徐々に慣れて行きましょう。
音読用の本などもいまはたくさん売っているので、毎日10分間、発生の練習をするだけでもいいのです。
また、トークのある動画で一番陥りがちな点は、「えっと」や「まあ」「あのー」といった“間をつなぐ言葉”がたくさん出てきてしまうということです。これらの音声は、視聴者にとっては聞きにくい場合が多く、自信のなさや、間が空いた印象を与えてしまいます。
焦って話す必要はありません。次の言葉が出なくなってしまったとしても、編集でその部分をカットすれば大丈夫です。
自分の動画をチェックして、これらの言葉がたくさん出ている場合、意識的に使わないようにしていきましょう。それだけであなたのトークはグンと聞きやすくなります。
本人が思っている以上にYouTubeは「うまくしゃべれなくていい」「そのままでも全く問題ない」というケースが多いものです。まずは始めてみて、そこから徐々にトークを改善していくというステップでいいのです。
これはYouTubeに限らず、インターネット全般での発信に、「飾らない等身大」「ありのまま」の方が信頼できるという傾向があります。さあ、まずはそのままのあなたで1本目を撮ってみましょう!
トーク構成の具体的な流れとテンプレ
YouTubeで発信するテーマは決まったものの、いざ撮影となると「何を話したらいいのかわかりません」「アドリブでは話すことができません」という方がいます。
そのような場合にオススメなのが、最初は台本を作ってから一字一句本通りに話す、という方法です。
台本はワードやパワーポイントでも、パソコンに不随しているメモ機能でも、紙に手書きでも、個人の使いやすいものを使いましょう。
そして慣れてきたら、徐々に台本を見る回数を減らし、アドリブで読めるようにしていけば、動画作成の時短になります。
やはり台本を作るとなると、アドリブで話す場合よりも3倍以上はじかんがかかってしまうからです。また、アドリブで話せることは、YouTube以外にも応用が利きます。プレゼン、商談、日々の会話など、あらゆるシーンでトーク力がアップしていくのを感じられるでしょう。
台本からアドリブに移行する際、最初は一字一句話し言葉で書いていたところを、徐々に要点だけに絞った箇条書きにするなど、台本を減らしていくとアドリブへの移行がしやすいです。
トークの大きな流れ
まずポイントとして、大きな流れをご紹介します。台本やトークの流れを考えるにあたっては次の3つを大切にしましょう!
1:この動画の内容とメリット、最後まで観る意味
動画の内容(テーマ・概要)を最初に話すことによって、視聴者は最後まで閲覧する意味を見出しやすくなります。そして、最初に概要を示しているので、動画の内容が頭に入ってきやすいというメリットもあるでしょう。その結果、YouTubeにおいて大切な指標である「視聴者維持率」を保てる動画になります。
2:中身は要点を絞る
話をするときは余計な前置きや脱線した話、言い訳などはなるべくしないようにしましょう。それらは視聴者が興味を持たないものです。例えば緊張を隠すために「まだチャンネルを開設したばかりで話がうまくないかもしれないですが、聞いてください」などという前置きや言い訳をしてしまいがちです。それらはエンタメ系でかわいらしいアイドルならよくても、ビジネス系やノウハウを語るチャンネルであれば不要です
3:動画のまとめ
一通り話をした後は、最後に簡単に要点をまとめると、話が整理されて視聴者の理解度が深まります。「今日の動画のポイントは3つです。1つ目は~」などと繋いでいき、30秒程度でまとめるのがよいでしょう。まとめが数分以上と長くなると中だるみして視聴者は飽きてしまうので注意しましょう。
誰でも使える「トークテンプレ」
全体の大きな流れがわかったところで、次に具体的な「トークのテンプレート」を紹介します。基本的にはどのようなジャンルのYouTubeチャンネルでも、このフォーマットに沿って話していけば、要点がうまくまとめられ、視聴者にとってわかりやすい動画作りができるはずです。
以下に、実際に話す際の構成要素をまとめてみました。実際のトークの際にアレンジしてご活用くださいね!
導入
- 動画の全体像
- この動画を観るメリット、観た後にどういう効能や学びがあるか
- 最後まで観るべき意味
コンテンツ部分
- 内容を簡潔に3つくらいのポイントに絞って伝える
終わり部分
- 動画のまとめ
- チャンネル登録や高評価ボタンへの誘導
YouTubeチャンネルの立ち上げ方と初期設定
動画をYouTubeに投稿するには、まずYouTubeのアカウントを作成してチャンネルを立ち上げることからスタートします。5分もあれば、アカウントを発行して自分のチャンネルを作成することが可能です。
チャンネルの立ち上げ方
チャンネルを立ち上げる手順は、大きく次の2つです。
YouTubeにログインすると、チャンネル登録やGoogleボタン・badボタンによる評価、再生履歴の管理などができるようになります。
さらにステップ2まで行うと、自分の動画をアップロードできるようになります。
1:GoogleアカウントでYouTubeにログインする
YouTubeにアクセスし、画面右上からGoogleアカウントでログインします。Googleアカウントを持っていない場合、
- アカウント作成をクリック
- フォームに名前やユーザー名、パソワードなどを入力しアカウントを作成
2:YouTubeチャンネルの名前やアイコン画像を設定する
YouTube上で右上のユーザーアイコンをクリックします。「チャンネルを作成」をクリックすると、チャンネルの「名前」と「アイコン画像」の設定画面が出て来ます。
チャンネルの名前を決めて入力し、アイコンの画像を選択して「チャンネル作成ボタン」を押せば、チャンネルの作成が完了します。
必ずやっておきたい初期設定
YouTubeチャンネルを立ち上げたら、次の4つは必ず設定しましょう!
設定は、チャンネルやコンテンツの管理ツール「YouTube Studio」上で行います。
- チャンネルアイコン
- チャンネルアート
- 基本情報
- キーワード
チャンネルアイコンの設定(プロフィール画像)
チャンネルアイコンは、YouTubeで自身のチャンネルや番組が提示される際に、動画の下やコメントの横などにプロフィール画像として表示される円形の画像です。
デフォルトでは、Googleアカウントの頭文字などが入ったアイコンになっています。
アイコンには、人の写真を使うのがオススメです。メインで話す方を、できればプロが撮った写真を使えるとベストです。
チャンネルと関係ない犬や猫の写真、建物の写真などは、YouTubeにおいて重要な「人への親近感」が感じられないのであまりオススメできません。
- アイコンの設定は、YouTube Studio上の「カスタマイズ」⇒「ブランディング」⇒「写真」から行います。
- 写真のサイズや内容について、YouTube公式には次のように示されています
98×98ピクセル以上、4MB以下の画像をオススメします。PNGまたはGIFファイルを使用してください。画像はYouTubeコミュニティガイドラインを遵守したものである必要があります。
チャンネルアート
チャンネルアートとは、あなたのチャンネルの入り口上部に表示される、バナー画像のことです。
画像の設定は、YouTube Studio上の「カスタマイズ」⇒「ブランディング」⇒「バナー画像」から行います。
基本情報
あなたのチャンネルに関する説明や、誘導したいリンク先のHP・SNSのURLを「基本情報」に記載しましょう。
説明はユーザーにわかりやすい内容にしたいものです。個人でチャンネルを発信する方であれば、「なぜ、このチャンネルをやっているのか」「どのような動画を発信しているのか」「これまでの経歴」「チャンネルの内容に繋がる実績」などを記載すると、チャンネルを発見したユーザーはわかりやすいでしょう。
入力はYouTube Studio上の「カスタマイズ」⇒「基本情報」から行います。
チャンネルのキーワード設定
チャンネルを表現する主要なキーワードを設定しましょう。例えば、「フリーランスのための起業ノウハウ」のようなチャンネルであれば、キーワードは、「副業」「フリーランス」「脱サラ」「ブログ」「起業」などがいいでしょう。
YouTubeはこのキーワードをもとに動画の内容を判定しており、検索結果や関連動画として類似したコンテンツが表示されやすくなる傾向にあります。
ただし、多めに設定し過ぎるとYouTubeから“ノイズ”として判定されてしまうので、5~7個、多くても10個以内に設定しましょう。
入力は、YouTube Studio上の「設定」⇒「チャンネル」⇒「基本情報」から行います。
視聴者を惹きつけるチャンネルアートのデザイン
たどり着いた経緯は何であれ、YouTubeで視聴した動画を「これ面白いな~、どういうチャンネルだろう?」と思って、チャンネルのアイコンをクリックしたことはありませんか。
そんな風にして、動画に興味を持った視聴者はチャンネルのホーム画面を訪れます。その際に、チャンネルアートやアイコンが魅力的だと思ってもらえれば、「このチャンネルは引き続き有益な動画を提供してくれそうだな、今後もチェックしておこう」という心理が働き、視聴者はチャンネル登録に至ります。
したがって、チャンネルアートはしっかり考えて作ることが大切です。
チャンネル登録者が増えれば、継続的に動画を観てくれる人が増えます。それは、「チャンネル登録者1000人・総再生時間4000時間」という収益化の条件到達の助けにもあります。
では、チャンネルアートはどのように作成したらよいのでしょうか。
チャンネルアート作成のポイント
もしPhotoshopなど画像加工のツールがあるなら、それを使って画像のサイズを調整するのが理想的です。Macであれば、内臓の「プレビュー」の「ツール」からも、画像のサイズ変更や切り取りなどができます。
これは簡易的ですが、パワーポイントで作り、「画像」として基地出して設定するという手もあります。
具体的なサイズとしては、「横2560ピクセル×縦1440ピクセル」で作成すると、TV、パソコン、スマホやタブレットなど、様々なデバイスでの表示に対応したチャンネルアートが完成します。
必ず表示させたいタイトルやロゴは、「横1546ピクセル×縦423ピクセル」の中に収まるように作成しましょう!
この画像は、チャンネルの上部全体に表示されます。文字はあまり詰め込み過ぎずに、チャンネルが目指す方向性や発信内容、視聴者へのメリットなどを、2行以内程度で完結に伝えていきましょう。
デザインとしては、「スマホで表示しても一発でどういうチャンネルかがわかるビジュアルと文言」にすることがポイントです。
- 設定は、YouTube Studio上の「カスタマイズ」⇒「ブランディング」⇒「バナー画像」から行います。
- なお、写真のサイズについて、YouTube公式には次のように示されています。
すべてのデバイスで最適に表示されるように、2048×1152ピクセル以上、6MB以下の画像を使用してください。
クリックされるタイトルとサムネイル作成の極意
これは公式に発表されていることですが、YouTubeは動画の内容のほあ、「タイトル」「説明」「サムネイル」などの主要データの指標を重視しています。
そして、それらのデータの成果が高い動画を、「おすすめ」や「関連動画」で積極的に露出したり、「検索結果」に表示する際に上位に出したりします。
動画の「タイトル」を決めるときのコツ
では、タイトルをつけるときはどんなことがポイントになるのでしょうか。
ズバリ「同じジャンルのヒットしている動画のタイトルを参考にする」というのが手っ取り早いです。なぜなら、同ジャンルでヒットしている動画のタイトルは、需要がある可能性が高く、また、そういった動画の「関連動画」としても表示されやすくなるからです。
そして、次の3つを意識してみることをオススメします。
- 文字数は長くても35文字以内に留める
- 【 】を使ってタイトルにメリハリをつける
- YouTubeの検索窓でタイトルのキーワードを入れて、リコメンドを見る
1の理由として、YouTube動画をスマホで視聴する際に、表示できる文字数が限られていることがあります。
また、タイトルが長いと、クリックするまでにタイトルを読むことに時間を要するので、できれば25文字以内に留めるのが理想的です。
2に関しては、文字のられるのみだとテキストが読みにくいためです。例えば、【要注意】など【 】を使って、タイトルにメリハリをつけると読みやすくなって動画へのクリック率が高まります。
3は動画を作る際のキーワード、例えば「オムレツを作る動画」であれば「オムレツ」という単語をYouTubeの検索窓に入力してみましょう。
すると、「オムレツの作り方」「オムレツ ふわふわ」「オムレツ ホテル」「オムレツ プロ」など、リコメンドの単語が検索窓の下に表示されます。
これは、YouTube上で視聴者が頻繁に閲覧する動画や検索語句が表示される場合が多く、需要のあるタイトルを考えるときの参考になるのです。
今回の「オムレツ」であれば、表示されたリコメンドの単語から【プロの味!】すぐできるふわふわオムレツの作り方。といったタイトルを考えることができます。
サムネイル作成のポイント
次にサムネイルについて見ていきます。
サムネイルとは一言でいうと「動画の看板」です。
例えば、あなたが街を歩いていて「お腹空いたな、何かお昼に食べたいな」と思ったとします。その場合、数あるお店の中から選ぶにあたって、まずどこで判断するでしょうか。
そう、看板です。
「中華料理」「ランチ500円」「山盛りチャーハン定食」などの看板から、私たちはそのお店に入るかどうかを決定します。看板で「何を提供しているお店か」「それは美味しそうか」というのを判断しているのです。
サムネイルもそれと同じような効果を果たします。その動画が「何について発信しているのか?」「面白そうか」「有益そうか」という点を判断し、クリックするかどうかを決める材料となっているのです。
つまり、サムネイルはお店で言うと「入店」、動画で言うと「クリック」してもらうための重要な役割を持つということです。
たまに、文字がたくさん詰まっていたり、動画の概要やタイトルをそのまま書いていたりするサムネイルがありますが、それでは数ある動画の中から選んでもらえません。
また、動画をアップロードすると、YouTubeが作成したサムネイルが自動的に3つ提示されますが、より多くの視聴者を惹きつけるために、自分でサムネイルを作成するのがオススメです。
では、効果的なサムネイルの戦略とデザインはどのようにすれば良いのでしょうか。YouTubeはサムネイルについて、このように述べています。
サムネイルとタイトルはチャンネルの看板のようなもので、視聴者はこれらを手掛かりにして動画を視聴するかどうかを決めます。サムネイルとタイトルをうまくデザインすると、より多くのファンをチャンネルに引き寄せることができます。
また、どのような動画なのかが予測できるため、視聴者に動画を最後まで見てもらうことができます。そして、幅広い広告主にコンテンツをアピールできます。
効果的なサムネイルを作るポイントをまとめると、次のようになります。
- スマホでの視認性(見やすさ)を優先する
- 文字を詰め込まず、主要な単語を大きく目立たせる
- 動画の説明やタイトルをそのまま書くのではなく、キャッチーな単語や主要なキーワードを記載する
- 見にくくなるので、画像やイラストの上に文字を入れ過ぎない
ジャンルやテーマによって異なる面もあるので、同じ分野の動画で再生回数の多いものを観て研究してみましょう。
自分のチャンネルに挿入できる広告と加入用件
一定の条件を満たすと自分の動画に広告を入れることができるようになります。YouTube上に広告枠を設置したチャンネル側は、広告を出稿したクライアントの広告費を、YouTubeと分配する仕組みになっています。
チャンネルの動画に差し込める広告フォーマットは、次の5種類です。
チャンネルに設定できる広告フォーマット
ディスプレイ広告
視聴者の動画タブの右上に表示される静止画のバナー広告枠です。動画の再生を妨げずに、画面の端の方に表示されるので、視聴者に不快感を与えずに広告を設置することができます。
このようにディスプレイ広告は動画を中断しないため表示されるのがデフォルトになっています。
オーバーレイ広告
視聴者が動画を閲覧する際に、途中で「ぴょこん」と表示される横長のバナー広告枠です。動画の視聴を大きくは妨げないバナー広告ですが、下にテロップが表示される動画の場合、テロップに広告がかぶさる形になることがあります。
視聴者側は、その見にくさを回避するために、広告に表示される「×」印を押すことにより、バナーを非表示にすることができます。
興味がある場合は、そのバナーをクリックすれば、出稿されている商品やサービス紹介のページに遷移します。
スキップ可能な動画広告
YouTube上で再生される動画形式の広告です。動画の再生前後や再生中に流れるシステムになっています。皆さんもYouTubeで動画を視聴する際に、「5秒後からスキップできます」といった表示の広告動画を頻繁に目にするのではないでしょうか。
スキップ不可の動画広告
基本的な露出先は「スキップ可能な動画広告」と同じですが、途中でスキップができない点で異なります。ですから、5秒ではなく動画のすべてを観て内容がわかるような骨太な広告が多い傾向があります。
デメリットとしては、スキップできないことで視聴者に不快感を与える側面が少なからずあります。
バンパー広告
動画の再生前に入る、6秒以内の動画広告です。スキップ不可という点では「スキップ不可の動画広告」と同じですが、こちらは最大6秒と短いのが大きな特徴です。
なお、自分が広告を出す場合の予備知識としては、これらの他に「マストヘッド広告」という、YouTubeのサイトトップ画面に表示される広告も存在します。
パートナープログラムの利用資格
実際に広告収益を得るには、まず「YouTubeパートナープログラム」に加入する必要があります。加入にあたっては審査があり、その条件として次の内容が提示されています。
YouTubeパートナープログラム「利用資格の最小用件」
- すべてのYouTubeの収益ポリシーを遵守していること。YouTubeの収益ポリシーとは、YouTubeでの収益化を可能にする一連のポリシーです。YouTubeパートナーがYouTubeで収益を得るには、YouTubeパートナープログラムのポリシーをはじめとする契約により、収益化ポリシーを遵守することが求められます。
- YouTubeパートナープログラムを利用可能な国や地域に居住している
- チャンネルに有効なコミュニティガイドラインの違反警告がない
- 有効な公開動画の総再生時間が直近の12ヶ月で4000時間以上である
- チャンネル登録者が1000人以上である
- リンクされているAdSenseアカウントを持っている
チャンネル収益化の条件
このようにYouTubeのチャンネル収益化の条件はいくつかありますが、大きくは2つです。
- チャンネル登録者数1000人以上
- 公開動画の総再生時間が直近12ヶ月で4000時間
この2つ以外は、基本的に設定上の条件なので問題なくクリアできるはずです。
チャンネルをスタートしたての頃は、まず「チャンネル登録者数1000人」を目指すとよいでしょう。目安として、チャンネル登録者数1000人を超えると、公開動画の総再生時間4000時間に達している場合が多いからです。
オススメの広告設定
「設置できる広告が複数あって、どれを選べばいいかわからない」という方も多いと思います。そんな方におすすめなのが「スキップ動画」以外の選択をオンにすることです。
理由としては、様々なYouTubeチャンネルの視聴者の行動調査などをしていると、「スキップ不可の動画」は視聴者に「広告がスキップできなくて不快だ」という感情を抱かせて、その場で動画の離脱に繋がってしまうからです。
もちろん、チャンネル登録者が数万人以上いて、安定的にチャンネルを視聴してくれている場合は、スキップ不可の動画を挿入しても離脱には繋がりにくい傾向にありますが、チャンネル登録者が1000人を超えたばかりなどのチャンネルでは選択しないことをオススメします。
また、YouTubeにアップした広告を設置する該当の動画が8分以上の場合は、動画の前、途中、後にも動画広告を配置できるので、こちらも全てオンにして選択しておきましょう。
最初の目安は「半年で100本投稿」
コンサルティングをしている会社の担当者や、自身で発信している社長さんに、よくこんな事を聞かれます。
「YouTubeはスタートしたてのとき、どれくらいの頻度でアップすればいいのですか?」
「1日5本くらいアップしようと思うのですが、どうでしょうか?」
こういった具合に、投稿頻度を気にされている方が多いと思います。
「本数と頻度」「投稿時間」の2点について、それぞれ最適な答えを見ていきましょう。
本数と頻度
動画の投稿本数に関しては、まずは「半年で100本を目指す」ということが最低の目標ラインとなります。
理想は「毎日投稿」ですが、それは難しいという方も多いのが実情です。
本業の仕事をしつつ、さらにYouTubeの撮影や編集、アップまでしていくのは、かなり時間がかかることでしょう。
ですから、最初はとにかく動画の質にはあまりこだわらず「とりあえず動画をアップしていく習慣をつける」ということに専念していきましょう。
毎日の歯磨きのように習慣化すると、非常にスムーズに動画が投稿できます。
投稿時間
動画投稿のタイミングは、できれば毎回時間を固定しましょう。
YouTube全体として、視聴者が最も多くなる時間は18~23時あたりなので、投稿は毎日「夜」にするというのもよいでしょう。
逆に、ビジネス系のチャンネルであれば「朝」の通勤時間などを狙い「毎朝8時アップ」などとするのも手です。
人気ユーチューバーのHIKAKINさんは、インタビューに応じたなか、YouTubeを伸ばす戦略として「投稿時間を毎日夜7時に固定」という話をしています。
また、自身の動画の中でも「毎日7時アップ」ということを発信しています。
そうすることにより、動画がアップされるタイミングを視聴者が掴みやすくなり、毎日定期的に訪れたくなる心理が生まれます。
「月9ドラマ」などのフレーズがあるように、「毎週月曜日の夜9時は、面白いドラマやっている!」という認識を持ってもらうことにより、視聴者のファン化が進みやすくなるわけです。
TBSの人気ドラマ、ガッキーこと新垣結衣さん主演の「逃げるは恥だが役に立つ」は、毎週火曜日の夜10時に放送されていました。
私の友人も食い入るように見ながら、毎週火曜日の10時を待ち遠しく感じていて、ドラマが終わった後には「ガッキーロス」だったのを覚えています。
無料で使えて便利なリサーチ・分析ツール
動画の編集に関して便利なツールがあることをお伝えしましたが、競合となるチャンネルをリサーチしたり、伸びている動画を分析し、自分のチャンネルの参考にするためのツールにも良いものがあります。
無料のものと比べれば、有料のものがオススメなのは間違いないですが、無料でも十分に使えるツールが少なくありません。
ここでは、数ある中から厳選したツールを4つご紹介します。
これらのツール活用のメリットは、YouTubeチャンネルの日々のネタ探しや、トレンドのキャッチアップ、トップ層で伸びている動画の確認などができることです。
絶えず情報をアップデートして、新鮮なコンテンツを考えるためのヒントを得ることができます。
自分の中だけでネタやチャンネルを探そうとすると、視野が狭く、似たようなチャンネルばかりにたどり着いてしまう場合が多いですが、これらのツールによって「自分では思いもよらなかった発見」をすることができます。
| NoxInfluencer | 各YouTubeチャンネルの月間の広告収益や過去のチャンネル登録者数の推移をリサーチすることができます |
|---|---|
| kamui tracker | トレンドのチャンネルや、キーワードを分析することができます。自身のチャンネルに関連するチャンネルやキーワードを参考にし、ヒット動画を作るヒントにしましょう |
| ユーチュラ | YouTube関連のニュースや速報などがまとまっているWEBサイトです。 |
| vidIQ | 指定したキーワードに基づく「関連キーワード」や、指定キーワードを含む「急上昇中の動画」などをリサーチすることができます |
広告収入以外のマネタイズをしましょう!
広告による収益以外にもYouTubeを使ったマネタイズの方法はあります。集客やバックエンドの商品・サービス販売への入り口にもなるルートと活用のコツをお伝えします。
- メンバーシップ
- スーパーチャット
- オンラインサロン
- 自社サービスや商品への誘導
- 広告タイアップ枠
1,2の利用にあたっては、チャンネル登録者数が1000人以上などの条件があります。
メンバーシップ
YouTube上の月額会員サービスです。自身のYouTubeチャンネルのメンバー会員だけに動画を公開したり、様々な特典を用意することで、毎月収益を得ることができます。
メンバーシップは月額6000~9000円の範囲で金額を設定することができるので、自身のファンがどれだけついてくるか、特典とのバランスを考慮しながらメンバーシップの内容と金額を決めていきましょう。
月額490円や980円など、気軽に出せる価格帯が集まりやすいイメージです。
スーパーチャット
YouTubeのライブ配信時や動画の公開時に、視聴者が自分のメッセージを目立たせてトップに表示する権利を購入するための機能です。特時に応じて権利を購入する、投げ銭のような機能で、俗にスパチャと呼ばれています。
ライブ配信時は特に、視聴者と直でリアルにやりとりをするのがうまい方に向いている機能と言えます。ただし突発的な売上なので、企業や法人としての収益の柱とはなりにくいでしょう。
オンラインサロン
YouTubeでチャンネルのファンになってくれた方に向けて、さらなる特典、YouTube外の濃いコミュニティ形成として使われる場合が多いです。自身のサイトを立ち上げたり、Facebookグループを使用したり、DMMオンラインサロンというオンライン管理サービスを使用したいするケースが一般的です。
有名なところで2つほどご紹介します。
中田敦彦さんのオンラインサロン「PROGRESS」では、YouTubeチャンネルの収録の様子がZoomで視聴できるほか、毎日のホームルームの視聴や、メンバー同士でのZoomやTwitterを使った交流などが行われています。
また、税理士の大河内薫さんは、YouTubeを活用してお金の知識を発信しているほか、Facebookを使った月額制のオンラインコミュニティを運営しています。
自社サービスや商品への誘導
動画のエンドロール、および動画やYouTubeチャンネルの概要欄などで、自社の製品ページやバックエンドの商品・サービスを宣伝し、そこへの受注に繋げていくサービスです。
初めてホームページに来訪する場合と比べると、既にあなたやあなたの会社をなんとなく知っている状態なので、成約率はかなり高くなるはずです。しっかりとした商品やサービスがある場合は、その収益の柱が大きくなるでしょう。
広告タイアップ枠
自身のYouTubeの動画枠を、広告のタイアップとして他社に売り出すという手法です。
例えば、コスメをたくさん紹介しているインフルエンサーのYouTubeチャンネルであれば、化粧品会社の製品の使用感を紹介するタイアップ広告を作成することで、その製品の起業から対価をもらえます。
動画を公開するにあたっては、その動画がプロモーションであることを視聴者に知らせる必要があるので、説明欄にその旨を明記したり、アップの際にYouTube Studio上で「有料プロモーション」の項目にチェックをするか、動画の説明欄に「●●企業とタイアップ案件」などと明記しましょう。
YouTubeから自社商品への効果的な誘導方法
視聴者をYouTubeから自社の商品・サービスやオンラインサロンなどに誘導するには、「動画のエンドロール」や「説明欄」を活用することが効果的です。その具体策とポイントをご紹介します。
エンドロールの効果的な使い方
これはYouTube上では終了画面と呼ばれており、動画アップロード時の「動画の要素」やYouTube Studio上の「終了画面」タブから設定することができます。
終了画面の表示時間は、5秒~20秒の間で設定可能です。
動画を視聴してくれた視聴者に対して、他の動画を宣伝したり、チャンネル登録を促すなどの目的に利用できます。具体的には、「視聴者に適したコンテンツ」「最新のアップロード」「特定の動画」「チャンネル登録ボタン」などです。
この終了画面を使って、自社の商品・サービスやオンラインサロンに誘導する手もありますが、その場合は、ちょっとしたコツが必要です。
普段は視聴者にとって価値のある情報を発信しつつ、自社の商品・サービスの説明動画も20本に1回くらいの割合で撮っておきます。そして、終了画面に、その自社誘導コンテンツを設定するのです。
視聴者にとっては、毎度自社のPRやサービスの説明では「また宣伝か」と思ってしまいますが、普段有益な情報を無料で届けてもらっていれば、「たまには宣伝の動画が混ざっていてもいいかな」と思うものです。
動画の「説明」欄に入れたいこと
興味を持った視聴者をしっかり誘導できるよう、動画の「説明」欄には、紹介した商品・サービス、その他の自社商品・サービス、オンラインサロンなどの説明やURLを入れておくと良いでしょう。
また、動画に関連する商品について、アフィリエイトリンクなどを貼っておくのもよいでしょう。例えば、動画内で紹介した商品を購入できるURLを「説明」欄に貼っておき、そこから視聴者が商品を購入してくれた場合、クリエーター側に手数料が入ってくるといった仕組みです。
YouTubeライブを活用する~1日で200万円売り上げるお店~
YouTubeは単に撮影した動画を観てもらうだけにとどまらず、ライブ機能も活用することができます。
ライブ配信を通して実演販売を行うことも可能です。新型コロナウィルスの影響により、実店舗での営業が困難になった事業者が多いなか、ライブ配信には今後かなりのポテンシャルがあるといえるでしょう。
ライブ配信のメリット
- 1対「1」ではなく、1対「不特定多数」の発信ができる
- 一方向ではなく、コメントなどで視聴者と双方向のコミュニケーションを取りながら販売できる
- リアル店舗を構えずとも、D2Cやオンラインだけでの販売が可能
- 配信場所は国内外を問わず、自由がききやすい
YouTubeライブを使って実際に販売を行うときのポイントは、次の2つです。
- 受け皿となるECサイトや、注文受付のフォームがあるとよい
- 購入してもらいたい商品の販売サイトのURLを説明欄やコメントに貼る
私のクライアントの化粧品会社では、YouTubeライブ販売の実演で1日に200万円ほど売上ているお店があります。
「そのパックはどんな風に使うの?」
「そのファンデーションの中身や塗り心地を見せて」
「化粧水の使用感は?」などと、
視聴者がライブ販売中にお店に質問をし、実際にお店側はその実演の様子を配信しているのです。
すると、その様子をわかりやすく動画で見た視聴者が、すぐに販売サイトから商品を購入してくれるのです。
テレビの通販番組をよく見ていた方ならわかると思いますが、動画というのはとても訴求力が高く、商品の性能もしっかり伝わってきます。そして、ついつい商品を買ってしまうのです。
ライブ配信の場合はさらに、コメント機能で画面の中の人とコミュニケーションをとることができ、まるでテレビの中にいる人と接触しているかのような感覚が得られます。YouTubeのライブ販売は、いわば「進化型テレビ通販」ともいえそうです。
YouTubeにアップしてはいけないコンテンツ
YouTubeに動画をアップロードする際には、YouTubeのコンテンツ規定に引っかからないよう配慮しなくてはなりません。アップした動画は、あなたやあなたのイメージに直結するので、その意味でも常に気を配っておきたいものです。
YouTubeが禁止している投稿内容
YouTubeではコミュニティガイドラインを掲げ、利用者にルールを順守するよう訴えています。具体的には、次の内容が示されています。
スパム行為
YouTubeコミュニティは信頼の上に成り立つコミュニティです。他のユーザーに誤解を与えたり、詐欺、スパム、不正を行ったりすることを目的としたコンテンツは、YouTubeで許可されません。
- スパム、詐欺に関するポリシー
- なりすましに関するポリシー
- 外部リンクに関するポリシー
- 虚偽のエンゲージメントに関するポリシー
- その他のポリシー
デリケートなコンテンツ
YouTubeは、視聴者やクリエイターの保護、特に未成年者の保護に努めています。そのため、ヌードや性的なコンテンツ、自傷行為が児童の目に触れないようにするルールを規定しています。
YouTubeで許可されるコンテンツと、ポリシーに準拠していないコンテンツを見つけた場合の対処方法について、
- ヌードと性的なコンテンツに関するポリシー
- サムネイルに関するポリシー
- 子供の安全に関するポリシー
暴力的または危険なコンテンツ
YouTubeでは、悪意のある表現、搾取行為、暴力的な描写、悪意のある攻撃や有害で危険な行為を助長するコンテンツが禁止されています。
- 有害または危険なコンテンツに関するポリシー
- 暴力的で生生しいコンテンツに関するポリシー
- 暴力犯罪組織に関するポリシー
- ヘイトスピーチに関するポリシー
- ハラスメントやネットいじめに関するポリシー
規制品
一部の商品は、YouTubeで販売することができません。販売が許可される商品と禁止される商品についてご確認ください
- 違法または規制対象の商品やサービスの販売に関するポリシー
- 銃器に関するポリシー
誤った情報
特定の種類の誤解を招くコンテンツまたは虚偽が含まれるコンテンツで、深刻な危害を及ぼす可能性のあるものはYouTubeで許可されません。これには、現実の世界で危害を与える可能性がある特定の種類の誤った情報が含まれます。
- 誤った情報に関するポリシー
- 選挙の誤った情報に関するポリシー
- COVID19の医学的に誤った情報に関するポリシー
その他、コミュニティガイドラインの基礎となる「YouTubeのポリシー」なども公開されているので、サイトをチェックしておきましょう!
広告がつかなくなってしまう動画とは
また、広告収益を求める際に気を付けておかなければならない点があります。それは、「なんでもかんでも、すべての動画に広告が挿入できるわけではない」ということです。
「Google広告のポリシー」に基づいて広告の審査が行われており、YouTubeは各動画に「広告を差し込んでもよいか」をAIにより自動で判別しています。
Google広告のポリシーでは「禁止コンテンツ」として次の内容が示されています。
虚像品
Google広告では偽造品の販売や宣伝を禁止しています。偽造品とは、他の商標と同一、またはほとんど区別がつかない商標やロゴを使用している商品を指します。真商品と偽って販売するためにブランドの特徴を模倣したものを指します。
このポリシーは広告およびウェブサイトやアプリのコンテンツに適用されます。
危険な商品やサービス
Googleではオンラインやオフラインを問わず人々の安全を保護したいと考えているため、損害、損傷、危害を引き起こすような商品やサービスの宣伝は認められません。
不正行為を助長する商品やサービス
Googleでは、不正な行動の実現を目的とする商品やサービスの宣伝は認められません。
不適切なコンテンツ
Googleでは多様性を尊重し、他者への思いやりを大切にしています。そのため、衝撃的なコンテンツを表示したり、憎しみ、偏見、差別を助長したりするような広告やリンク先は許可していません。
広告の審査プロセスについて
また、広告の審査の仕組みやプロセスについて、Googleは次のように示しています。
広告の審査の仕組み
広告や広告表示オプションの作成や編集が終わると自動的に審査プロセスが始まり、広告内のコンテンツ(広告見出し、説明文、キーワード、リンク先、画像や動画など)が審査されます。
審査を通過した広告はステータスが「有効」に変わり、掲載が開始されます。
審査でポリシー違反が見つかった広告はステータスが「不承認」に変わり、どこにも掲載できなくなります。この場合、広告主にはポリシー違反があった旨を対応方法についてのお知らせが届きます。
自分のことは自分が一番客観的に見られない
YouTubeを始めて続けていくなかで一番大切なことは何かと言うと、自分もしくは自社のチャンネルに対して「赤の他人がどう思っているか」を知ることです。
言い換えれば「客観性」が一番大切なのです。
これは私がYouTubeのプロデュースやコンサルをしているすべてのクライアントさんにお伝えしていることですが、「自分のことは絶対に自分では客観的にみられない」ので、必ず、他人の目線をチャンネルに入れてください。
私自身、チャンネルを運営していますが、その良し悪しや改善点は、必ず人に聞いています。
具体的には、
「この動画、10分もあって飽きがこないか」
「客観的に観てどこか改善点はあると思うか」
「サムネイルや最初の導入のテンポなどはどうか」
ということを複数人に確認して、フィードバックをもらうようにしています。私のように他人を客観的にプロデュースする職業であっても、「自分のこと」はわからないのです。
なぜなら、自分のことを精神的にも物理的にも外から見ることができる人はこの世に存在しないからです。どんなに冷静で客観的な人であっても、こと自分自身に関しては冷静に判断できないものです。
ですから、チャンネルを立ち上げたら、頻繁に人にフィードバックを求めることをオススメします。家族、友人、同僚、会社の外の人、あるいは専門的なコンサルタントやそれに近いことをしてくれる人に頼むのもありでしょう。
SNSなどにYouTubeの動画をアップして「成長したいので辛口な感想をお待ちしています」と書くと、意外なほどに周りの人は協力してくれるものです。
特に最初の頃は「話し方が、間が空き過ぎて聞きづらい」とか「動画の音量が小さい」「動画が暗い」など、自分では気づかないフィードバックが得られたりもします。
繰り返しますが、「自分のことは自分が一番客観的に判断できない」ということを踏まえ、「赤の他人のフィードバックを取り入れていく」ということを大切にしましょう。
そうすると、あなたの動画は劇的に改善されていき、動画の視聴回数やチャンネル登録者もグンと伸びて行きます。
ここで差がつく!動画ビジネス飛躍のヒント
YouTubeチャンネルを適度に新規の視聴者にリーチしながら成長させていくためには、どうすればよいでしょうか。
そのカギとなるのが、「ストック」型と「フロー」型の動画を効果的に使っていくことです。
まずは、「ストック」と「フロー」について、押さえておきましょう。
チャンネル成長のカギは「ストック」と「フロー」のバランス
ストック型動画
毎月、毎年、継続的に再生される動画。トレンドや時事性に左右されない、しっかりとしたニーズに基づく動画。長期的、永続的な需要が見込める。
例として、「確定申告の方法」「毎日ラクにできる3分ダイエット」「初めての肉じゃがの作り方」「新卒サラリーマンの名刺の渡し方」などです。
このような、確定申告やダイエット、料理の方法、新卒のビジネスマナーなど、毎年、あるいは年中ニーズのあるコンテンツは、「ストック」型として着実に長期的に再生される側面を持っています。
逆に言えば、いきなりグッと伸びるようなことはなく、再生回数の増え方もなだらかです。
あなたの運営するチャンネルのテーマにも、深堀すればこのような長期的なニーズを探せるはずです。チャンネルが長期的に伸びていくという観点でも、ストック型動画はあなたのビジネスについて長期的に発信していく“財産”としての動画になります。
フロー型動画
ストック型動画とは対照的に、トレンドに乗って一気に再生回数を稼ぐ、新規の視聴者を開拓できるような動画です。水もので鮮度が命、トレンドや流行に基づくコンテンツです。
例えば、「新型コロナウィルス助成金まとめ」「iPhone12の開封動画」「ガッキーと星野源、結婚の裏側」「BTSのダイナマイト歌ってみた」などです。
このようなタイトルの動画は、季節性のものや流行、時事ニュースと自身のチャンネルのテーマをうまく絡めることにより、再生回数の爆増を狙っています。こうしたフロー型動画は関連動画も多く、そこからの流入もより増えます。
しかし、動画を出すタイミングが遅れたりすると、あまり再生回数が増えない傾向にもあり、スピードや鮮度が命となります。
飛び道具的な動画と考えるといいかもしれません。また、著作権に問題のありそうな動画や、信ぴょう性のないコンテンツなどは、動画の広告がつかなかったり、個人の動画コンテンツよりもニュースサイトや権威のあるメディアのコンテンツが優先されるといったケースもあるので注意が必要です。
両タイプの使い分け方としてオススメなのが、「ストック型動画」で数年スパンの長期展望で再生回数を増やしていきながら、時事・トレンドネタなどを絡めた「フロー型動画」によって一気に視聴者数、チャンネル登録者数を増やすという戦略です。
「攻め」と「守り」の動画と考えるとわかりやすいかもしれません。
アップする量の配分としてはストック型が7割、フロー型が3割のような比率で動画を作っていくとよいかと思います。
ストック型だけだとチャンネルの伸びが低調で、フロー型だけだと、常にトレンドや流行のネタをアップしていかないとチャンネルが伸びていかず、自転車操業のように疲弊してしまうという側面があります。
続けるだけで上位1%の法則
多くの個人や企業がYouTubeでつまずくポイントは何だと思いますか。
ネタ切れ?編集がうまくいかない?いいえ、違います。様々なチャンネルが陥りがちなのは「続かない」という点です。
私の体感的に、全体のチャンネル数が100とすると、90以上のチャンネルは2,3カ月も経たずに動画のアップをやめてしまいます。なぜでしょうか。
YouTubeは「二次関数的の伸びる媒体」
理由はいろいろ考えられますが、よくあるのは「最初の投稿で伸びないと思ってしまう」とか、「最初から動画作りに凝って撮影や編集をしてしまう」ためです。
投稿して1,2ヶ月でいきなりバーンと伸びるのは、ごくごく少数の相当センスがあるチャンネルのみです。
喩えるなら、勉強をあまりしていないのに、東大に受かってしまうような人です。
YouTubeでこういうタイプを目指すのはやめましょう!スタートから1,2カ月で劇的に伸びていき、再生回数1万回をすぐに突破するようなチャンネルはごく稀で、0.01%くらいのトップのカリスマの話なのです。
そこで認識しておいてほしいのが、「YouTubeは二次関数的に伸びるメディア」だということです。チャンネルを立ち上げて初期のうちは、ほとんど視聴されません。
無数にある動画の中から、スタートして1本目の動画が発見されるはずもなく、最初の1ヶ月くらいは「5~20再生」が普通です。
またYouTube側も、新しいチャンネルをすぐ「おすすめ」や「関連」に積極的に出そうとしません。
なぜなら、「おすすめ」や「関連」などに載せて、一時的に再生回数やチャンネル登録者数が伸びたとしても、まだ実績がなく、今後そのチャンネルが定期的に動画をアップする保証がないからです。
YouTube側は「視聴者が長時間閲覧する動画、すぐに離脱しない動画を作れているか?」「しっかりと定期的に動画をアップしているチャンネルか?」といった点を評価しており、その基準に達したチャンネルや動画が積極的に「おすすめ」や「関連」などに露出されるのです。
すると、視聴回数やチャンネル登録者数がどんどん増えていきます。
「目標は半年で100投稿」「質よりも量」という話をしたのは、そのためです。
まずはストック型でコツコツと積み重ね、二次関数的な曲線で再生回数やチャンネル登録者数が増加するのを目指すとよいでしょう。
この点を理解しながら、最初はひたすら辛抱する期間を耐えていきましょう。
そこを抜けると必ず明るい未来がやってきます。私の運営するチャンネルも、最初の4ヶ月で60本程度の動画をアップし、ほぼ再生回数は上がりませんでした。しかし、1年経つと登録者数が2.5万人にまで成長したのです。
まずは「続けること」を目標にしましょう
したがって、最初のうちはとにかくYouTube側に認識してもらうこと、少しずつでも動画のデータをYouTubeに蓄積すること、高速でPDCAを回していくことが重要です。
その点で言うと、良質な内容の動画を作ることは大切ですが、最初から撮影や編集に凝り過ぎて多くの時間を費やすのは損失でしかありません。
様々な企業や個人のYouTubeプロデュースをお手伝いしてきたなか、よく言われる「1%の法則」はYouTubeにも当てはまると実感しています。
1%の法則とは、例えば「明日から痩せよう!運動しよう!」と思った人のうち、実際に運動や食事制限を継続してダイエットに成功する人は100人中1人しかいないといったことです。実際にそういう統計があるそうです。
それと同様に、私の間隔では「YouTubeはビジネスと相性が良い」と感じる人が100人いたとして、YouTubeを始める人はそのうちの10人程度、さらに1年間コツコツと動画をアップし続けるのはその中の1人、つまり1%程度なのです。
公式なデータはありませんが、この予測はかなり的を射ているかと思います。
私のFacebookの友人知人で、情報感度の高い経営者や個人事業主の方々が、2020年事からドサッとYouTubeを始め、SNSでも「ビジネス系のチャンネルを立ち上げました!」と高らかに宣言していました。
全員で50人くらいはいたのですが、1年ほど経って、彼らのアカウントをすべて1つ1つチェックしにいってみると、しっかり継続的に投稿していたのは、わずか2人。しかもその2人は、チャンネル登録者数が1万人を突破していたのです。
仕事側、私の友人はIT系の人が多く、WEBの知見が深い人も多いのですが、ノウハウよりも結果的には「継続していた人の勝ち」だとわかりました。
継続していなかった人は、5~10程度の動画投稿でやめてしまっている人が多く、本当にもったいないなという印象を持ちました。
こうした話から、いかに継続的にアップすることが大切か、おわかりいただけたのではないでしょうか。
できれば1日1投稿、クオリティは編集なしのノーカット版でも大丈夫です。
つい凝りたくなるかもしれませんが、視聴者が重視しているのは動画の編集クオリティや画質の綺麗さではなく「動画の内容」です。
毎日歯ブラシをしないと気持ち悪いように、まずはホームランを狙いに行かずに、動画をアップするというルーティーンを身体に染み込ませて継続するところから始めていきましょう。
継続するだけで、あなたはYouTubeに限らず、どこにいっても上位1%に入ることができるかずです。これは何にでも共通する成功のコツなのではないでしょうか。
YouTubeが伸びない原因:「自意識の壁」を克服しよう!
私は現在、100社近くのYouTubeチャンネルをプロデュースし、コンサルティングを行っていますが、その中で厄介だと感じるのが「自意識の壁」です。
個人であれ企業であれ、これが意外とYouTube事業が伸び悩む大きな原因となるのです。
クライアントの悩みには「自分なんかよりも上の人がいるのに偉そうに発信して大丈夫なのか」「自分の外見やしゃべりに自信がないので恥ずかしい」「友人や知人に観られるのがイヤだ」といった声があります。
初めて世の中に発信し、時として顔や声までも全世界に発信していくのですから、この気恥ずかしさというのは当然湧いてくるものかと思います。
しかし、安心してください。良くも悪くも「あなたのことを世界は見ていない」のです。
例えば、テレビに出ているような芸能人や著名な起業家がYouTubeを始めたら、多くの人が注目するでしょう。
そのような有名人でなければ、大企業の社長レベル、年商数百億円規模の中小企業の社長レベルであろうとも、世間的に見れば「無名の人」です。
あなたは、売上高トップ5の建設会社とその社長名を言えますか?
化粧品メーカーのトップ5、食品メーカーのトップ5はどうでしょうか?
ほとんどの人は、1割も答えることができないのではないでしょうか。つまり、「ほとんどの人は無名で、誰も注目していない」という前提が成立します。
そしてYouTubeは、今後あなたのサービスや商品に繋がる“潜在的な顧客”にリーチしたり、ファンになってもらうための「赤の他人にリーチするツール」です。
ですから、同業者や友人、知人などの存在を気にする必要はないですし、そこに向けてアプローチする媒体ではないのです。
初めてあなたのYouTubeチャンネルを訪れる視聴者は、あなたに注目していません。
面白そう、有益そうなら観る、そうでなかったら動画を閉じる。それまでです。
あなたがYouTubeで恥ずかしいと感じていることを、視聴者は何とも思っていないのです。
さあ、自意識の壁を突破できそうな気がしませんか。基本的にYouTubeで誰が発信しようと自由であり、失敗しても誰からも咎められる理由はないのです。
あなたのチャンネルを伸ばすための情報源
再生回数や登録者数を増やしたいとき、インターネットで調べれば様々な情報を得ることができるでしょう。YouTubeやTwitterでも「YouTubeの伸ばし方教えます!」といった発信をしている人が少なからずいます。
もちろんそれを参考にしてもいいと思いますが、最も大切なのは「YouTubeが何を考え、発信者側にどうしてほしいのか」を考えることです。
YouTube Creator Academy
Youtubeクリエーター向けのノウハウを提供している無料のオンラインコースです。
動画とテキストで、チャンネルの始め方から、機材や編集のコツ、視聴者を引き付けるポイントなど、様々なノウハウをYouTube側が無料でレッスンしてくれます。
チャンネルの最適化や、収益化の手続き、広告の種類など、詳細な部分まで教えてくれるので、何かYoutubeでわからないことがあったときに行き詰まったときに立ち返るサイトとして覚えておくと良いでしょう。
YouTubeの仕組みとは
ここには、YouTube全体としての思想や取り組み、現状の動向がまとめられています。
具体的には、コンテンツの規制・管理・プライバシーポリシー、動画の削除理由、YouTubeが社会に向けて貢献していることなどがあります。
この中の「YouTubeの動画削除理由」という項目を見ると、最も多い削除理由は「子供の安全」で50%以上を占めています。
子供の安全を害するコンテンツや児童ポルノなど、特にそういったコンテンツにYouTubeは神経を使って見張っていることが伺えます。
その次に「性的表現」や「暴力的描写」などが続き、「どういう内容・方向性の動画を作ってしまうと良くないのか」という判断基準にもなります。
「テーマのごった煮」に悩んだらサブチャンネルで可能性を広げよう
YouTubeがなかなか伸びていかないときの傾向としては、「テーマが分散している」という特徴も挙げられます。
「税金の話をしていたのに、自己啓発の話や料理の動画も上がっている」といったパターンです。
YouTubeで情報を発信していこうとする人や企業は意識が高く、伝えたいネタが豊富にあるのだと思います。しかしそれだと、視聴者は「このチャンネルがどのような情報を提供してくれ、何が有効なのか」を一瞬で判断できず、チャンネル登録にいたりません。
そこでオススメなのが、「チャンネルを分ける」「サブチャンネルを作る」ということです。
例えば、美容師として働く傍ら、フォトグラファーとしても実績のある方がいたとします。
実際、カットモデルのヘアメイクをして、そのまま撮影もするという美容師の方が最近増えています。
そんな方がYouTubeで発信していくとき、美容師系のネタと写真系のネタを1つのチャンネルにアップすると、なかなか登録者数が伸びません。
しかし、「ヘアメイク」と「カメラの使い方」の2つにチャンネルを分ければ、視聴者は「このチャンネルは何を発信しているのか」が一目でわかり、登録者数の増加や継続的な視聴に繋がるのです。
こんな話があります。コロナ渦により、ウーバーイーツのような宅配での食事文化が急速に広まりました。それによって、かなり売上をアップしたのが「ゴーストレストン」1つの調理場に複数の専門店を持つという営業形態です。
例を挙げると、調理場は1つでありながら「カレー専門店」「唐揚げ専門店」「タピオカ専門店」を宅配サービス上で出店し、注文を受け付けているようなスタイルです。
もし、1つのお店で、カレーと唐揚げとタピオカを出品していたら、お客さんに「何のお店がわからない」と思われてしまいますが、店舗を切り分けることで、何の専門店かが明確になり、それぞれのお店の売上も伸びていきます。
YouTubeにもそれと同じことがいえるのです。
重要なのは、「どう作るか、運営するか」ではなく、「お客さんにどう見えているか」そこを意識するだけで、1つどころか「複数のチャンネルでのビジネスチャンス」が広がっていきます。
YouTube×WEBの組み合わせでSEO効果をアップする方法
YoutubeのコンテンツはYouTubeでしか活用できないと思っている人が少なくありませんが、実はWEB上で相乗効果を生む使い方があります。
それは、YouTube動画をWEBサイトなどに組み込み、WEB記事として活用する方法です。
せっかく作った動画をYouTubeの中だけに留めるのではなく、WEBサイトの素材として、ブログやホームページでも活用していくのです。
この「YouTube×WEB」のメリットとしては、コンテンツの再利用に加えて、SEO効果が高いという側面があります。
海外のリサーチ会社が発表したデータによれば、Youtube動画を組み込んだWEB記事は、そうではない記事と比較した際に、SEO効果が12倍アップしたという話もあります。
そこまでの効果は見込めなかったとしても、YouTubeはGoogleが所有している点、そして、Googleは「ユーザーファースト」の理念を追求しているという点から、検索ではわかりやすい動画が有利に表示されるというのは事実です。
是非、YouTube×WEB記事を利用して、コンテンツの再利用と、さらなる認知の拡大を狙っていきましょう。効果的なやり方は、次の2パターンです。
- 動画の書き起こしをして全文を掲載する
- 動画のポイントを伝える簡易的な記事にする
その際に、YouTubeの各動画のシーンを「画像」として切り出し、数枚ほど記事に入れ込むと、視聴者は動画の様子をつかめて理解度もたかまります。
例えば、私がコンサルティングに携わっている業界NO.1の経済メディアも、2021年4月から本格的にYouTubeチャンネルを始動し、この「YouTube動画×WEB記事」のスタイルを開始して、PVの大幅増や、新規ユーザーの獲得に繋げています。
そこの編集部長が優秀でスピードが速く手数がおおい、というのも大きいでしょう。
アドバイスさせていただいた「量」と「媒体活用」をうまく遂行され、さらなる成長を実現させていきました。やはり、インターネットの時代においてはこのようにスピード適応力が必須ともいえるでしょう。
今や、SNSやホームページ、ブログだけの時代は終わり、「動画とWEBサイトの相乗効果」が、最もコスパが良いビジネスを生んでいくのです。
次世代型の動画集客手法:TikTokやInstagramのリール
ここでは、Youtubeでアップした動画をSNSなどの媒体でさらに認知拡大させるために、相性の良いアプリ戦略や機能をお伝えしていきます。
TikTok、Instagramリール機能、YouTubeショート機能の3つです。
TikTok
中国のバイトダンスが運営するショート動画の共有アプリです。60秒以内の短編動画を気軽に投稿・閲覧できることから、ここ数年の間に世界中でブームになりました。
スマートフォン全盛の時代ということもあり、「縦動画」での投稿が主流です。
また、TikTokの特徴は「オススメ表示機能」にあり、オススメに乗れば一気に数百万再生までいくことも珍しくありません。
このTikTokは若者を中心として大流行していますが、実はビジネス系とも相性がよいのです。
最近ではお金の話や自己啓発、人生論などを60秒でわかりやすく発信しているビジネス系のTikTokチャンネルも人気です。
YouTubeとの相乗効果の戦略としては、Youtubeで撮影した動画をTikTok用に短く編集したり、あるいは、反対にTikTokで撮影した60秒以内の動画をYouTubeの「ショート」機能で投稿するなどの戦略です。
TikTokという「再生回数を急激に伸ばす媒体」の力を借り、「短期間で認知をアップさせる」という効果に加え、「TikTokからYouTubeに流れてくる」という効果もあります。
ただし注意点があります。
TikTokのプロフィールや、プロフィールのリンクでYouTubeを宣伝するのは問題ないのですが、投稿動画にYouTubeへの誘導文言やテキストがあると、制限がかかる傾向にあります。
現代はスマホの可処分所得時間を奪い合っている時代です。TikTokも安易に、Youtubeにアクセスをとられたくないという意向があるのでしょう。
Instagram「リール」機能
アメリカ発の「写真共有型プラットフォーム」アプリとして誕生したInstagramですが、最近は動画を通してのコミュニケーションが活発です。
写真や動画をアップして1日で消えてしまうタイプの「ストーリー」という機能が流行ったことはご存知の方も多いでしょう。
現在はTikTokのような60秒以内の動画を投稿する機能の「リール」が、これまた大流行しています。
YouTubeとの相乗効果の戦略としては、基本的にTikTokと同じで、「YouTubeで撮影した動画をInstagram用に短く編集する」、もしくは「Instagram用に編集した動画をそのままリールに投稿する」という手があります。
Instagramのリールは、TikTokが流行しすぎたことへの焦りから新機能が追加されたという経緯もあって、YouTube動画との相性が良いのです。
YouTube「ショート」機能
Youtubeにもショート動画を投稿できる新機能が追加されました。
こちらも基本的にはInstagramと同様に、「TikTokの流行に負けじとYouTubeもショート機能を実装した」という説が濃厚です。
ショート動画の投稿の仕方は簡単で、60秒以内の動画にタイトル、もしくは説明欄にハッシュタグ「#shorts」をつけるだけです。
それだけで、YouTubeのショート動画として認識され、ショート動画タブにまとめられて閲覧されます。
昨今の動向と、これから
新型コロナウィルスの蔓延によって、テレビや撮影の収録などが減少した影響もあり、多くの芸能人やインフルエンサーがYouTubeに参入してきました。
YouTubeにおいて、コロナの影響により月間での視聴者数が増加しているとの報告もあります。
いまでは社会一般的にもYouTubeという存在が広く認知され、多くの人が使っているのですから、YouTubeをまだ活用できていないという企業や個人の方は、逆にピンチともいえるのです。
ビジネスにおける感度が高い層は、すでに自社の認知拡大や商品PR、サービス導入の入り口としてYouTubeを活用していて、その層がどんどん増えていくことは想像に難くありません。
だとすると、活用できていない層が相対的に不利になっていくことは明白でしょう。
現在、ホームページを持っていない企業はほとんど見かけません。持っていないとすれば、よほどビジネスを理解していないか、用意できないほど予算がないかのどちらかではないでしょうか。
なぜなら、ネット全盛の現代にホームページを持っていないということは、看板を掲げていないという行為に等しく、お客様から「信用ができない」というレッテルを張られてしまうからです。
これが20年前の話なら、ホームページを持っていなくても少数派ではありませんでしたが、いまの社会においてそれほどネット上での「看板」は重要になってきました。
それと同じように、いまYouTubeという媒体が次の時代の「看板」として急速に発展しています。
世界で2番目に大きなプラットフォームであり、日本人の77%が日常的に利用しているのです。
テレビやラジオに費やす時間が少なくなり、手軽にスマホで閲覧できるYouTubeが圧倒的に観られているのです。
そして、この流れは、今後さらに加速していきます。
つまり、「1企業1YouTubeチャンネル」という時代が必ずやってくるのです。
YouTubeというプラットフォームに代わるものが台頭してくるかもしれませんが、基本的には「動画をアップする自前のチャンネル」という概念は、ここ10年、20年はずっと続いていくでしょう。
YouTubeをビジネスに活用したいのであれば、できるだけ早く参入することをオススメします。
このYoutubeという媒体の“おいしさ”に気付いているビジネスをする企業や個人は、まだまだ少数派です。
今日にでもYouTubeチャンネル開設のために行動をはじめ、地道に動画をアップし続けて行ってほしいと思います。
そうすることで、あなたのビジネスには着実にファンがつき、売上をYouTube経由で上げて、ライバルや競合との差を一気につけることができるはずです。



































