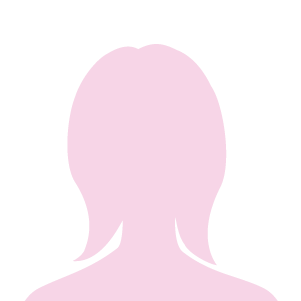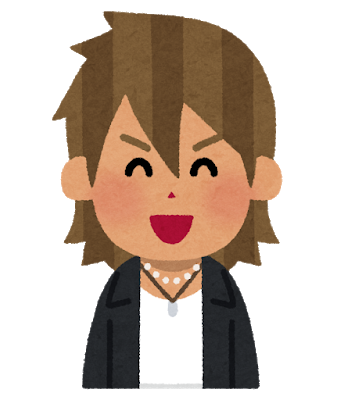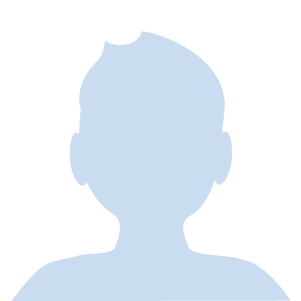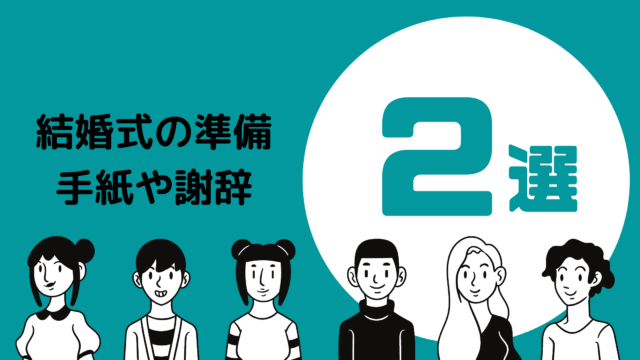① 招待客を書き出して優先順位をつけて絞り込みましょう!
② 招待客には事前に出席して欲しい旨を伝えておきましょう!
③ 遠方からの招待客には交通費、宿泊費の負担を考えましょう!
① ウェディング業界で10年間経験をした人間の情報が源です。
② 式場のプランナー50名分の知見を集約した情報が源です。
③ 実際に、結婚式を行った卒花嫁さん(約200名)の情報が源です。
※本記事の画像は、株式会社bloom(ぶるーむ)のアフターブーケを採用しています。
※参考資料として、ゼクシィブライダル総研の資料を使用しています。

※本記事の画像は、株式会社bloom(ぶるーむ)のアフターブーケを採用しています。

【結婚式】招待客(ゲスト)の決定方法
親族は優先順位がわからなかったら、必ず親に確認をとりましょう。後から追加すると人数調整が難しくなるので、早めに確認しておくことが大切です。
何の連絡もなしに招待状を送るのは相手を困惑させてしまうので避けるようにしましょう。
結婚式の招待客(ゲスト):直接出席してほしい気持ちを伝えましょう
直接出席して欲しいという気持ちを伝えることで丁寧な印象を与え、かつ出席者の人数をある程度把握することができます。
結婚式の招待客(ゲスト):どこまで招待するのか判断が大切
招待したい人のリストアップが終わったら、招待客を絞り込みます
この時に予定の人数よりも少し多めに設定しておきましょう。予定の数ぴったりにすると出欠に伴う人数調整が困難になるからです。
結婚式の招待客(ゲスト):遠方からの招待客には心配りしましょう
交通費や宿泊費を負担するのが基本的なマナーです
こちらで手配する場合は招待状にその旨を明記し、相手に心配させないように配慮をしましょう。
仲人や主賓には交通費、宿泊費ともに新郎新婦が負担をします。友人などには宿泊の手配は新郎新婦が行い、交通費については全額、あるいは片道分を負担するのが一般的です。

※本記事の画像は、株式会社bloom(ぶるーむ)のアフターブーケを採用しています。
結婚式の招待客(ゲスト):招待客への心配り
招待客(ゲスト)への心配り①:仲人や主賓
交通費、宿泊費は新郎新婦が負担します。こちらで交通チケットを手配する場合と、交通費を手渡しする場合があります。どちらにするかは先方に確認をしましょう。宿泊の手配も同様です。
招待客(ゲスト)への心配り②:職場の人
職場の人はどこまで招待するかが迷うところです。既婚者の先輩などにアドバイスをもらうのが良いと思います。呼ぶ範囲に悩んだら、会社関係は誰も呼ばないという方法もあります。
招待客(ゲスト)への心配り③:知り合いがいない
ひとつのグループからなるべくふたり以上を招待し、ひとり参加がいないようにしましょう。ひとり参加の人がいたら、その人と話や趣味が合いそうな人、年齢が近い人を同じテーブルにしましょう。
招待客(ゲスト)への心配り④:子供連れ
小さな子供がいる人には、子供を預けられるかどうかを確認しましょう。子供が同伴不可のときは素直にその旨を伝え、出欠の判断は本人に任せるようにしましょう。出席する場合はデグチに近い席に配置をしましょう。
招待客(ゲスト)への心配り⑤:遠方からの招待客
交通費や宿泊費を負担するのが基本的なマナーです。全額が無理でもどちらか片方は負担しましょう。招待された側からは聞きづらいので、どこまでこちらが負担するか招待状を発送する前に伝えておきましょう。

※本記事の画像は、株式会社bloom(ぶるーむ)のアフターブーケを採用しています。
結婚式の招待客(ゲスト):こんな心配りが喜ばれます!
① 旅費を全額負担する
② 宿泊場所を手配する
③ 飛行機のチケット代など交通費を出す
④ 当日に御車代を渡す
⑤ 御祝儀を辞退する

※本記事の画像は、株式会社bloom(ぶるーむ)のアフターブーケを採用しています。
【結婚式準備】招待状の発送
① 遅くても挙式の2ヶ月前には招待状を発送しましょう
② 宛名に間違いがないか何度も確認しましょう
招待状は遅くても挙式の2ヶ月前には発送しましょう
招待状の作成は会場に頼むのが一般的です。デザインや文面を選び、招待客のリストを渡すだけで作成してくれるので便利です。
その場合は、目上の人にも送ることを念頭に文面を考えることが大切です。また、必要事項に漏れがないか確認する必要があります。
招待状の差出人は新郎新婦名で出す場合と、両家連名で出す場合があります
どちらを主催者とするかで差出人が異なります。以前と比べ、新郎新婦名で出す場合が増えているようです。
封をする前に、もう一度確認をしましょう
旧字体や略字になっていないかも確認をしましょう。宛名は毛筆で書くのが正式です。
手書きに自信がありません!
筆耕(ひっこう)に依頼できます。費用は1通150~200円程度で、会場に問い合わせればたいていは紹介してもらえます。パソコンを利用して毛筆のような書体で印刷しても構いません。

※本記事の画像は、株式会社bloom(ぶるーむ)のアフターブーケを採用しています。
招待状を発送するまでの4ステップ
ステップ①:招待状の差出人を決める
差出人を新郎新婦にするか、親にするかを決めましょう。新郎新婦のときは少しカジュアルな文面でも大丈夫です。
ステップ②:招待状の文面を作成する
自分たちで考える場合は、日時、場所、会場の所在地、出欠の返事の締切などを必ず明記しましょう。
ステップ③:宛名を書く
宛名は誤字脱字がないか何度も確認をしましょう。筆ペンや万年筆で書いても良いですが、ボールペンはNGです。
ステップ④:封入作業をする
同封するものがいくつかあるので、忘れないよう気を付けましょう。スピーチや余興のお願いは手書きで書きましょう

※本記事の画像は、株式会社bloom(ぶるーむ)のアフターブーケを採用しています。
招待状に同封するもの
✓ 招待状
✓ 出欠返信用ハガキ
✓ 会場の案内・地図
✓ スピーチや余興のお願い
✓ 遠方の方への案内や交通チケット
差出人を誰にするかで文面が変わります
差出人を親にすると両家の結婚という意味合いが強くなるので、堅い文章になりがちです。親のあいさつ文の後に二人の挨拶を添えるのをオススメします。

※本記事の画像は、株式会社bloom(ぶるーむ)のアフターブーケを採用しています。
結婚式の招待客(ゲスト):席次を決定しましょう
① 招待状の返事をもとに最終的な人数を確定しましょう
② 招待客が楽しめる席次を考えましょう
招待客出欠の返事を元に、最終的な出席人数を決定
招待状を送付する際に定めた締切日を過ぎてもまだ返事がきていない人には、直接電話などで連絡をとり確認をしましょう。あくまでこちらは招待する側なので、一方的に急かしたり、問いただしたりしてはいけません。
そして口頭で返事をもらい、再度招待状を発送しましょう。
招待客(ゲスト)全員が楽しめる配置をしましょう
人数が確定したら、会場と席次を決めます。
新郎新婦に最も近い席が上座で、ここには主賓が座ります。次に会社関係者、友人と座り、親族や家族は新郎新婦から遠い下座に座るのがマナーです。親は高砂から最も離れた末席に座ります。
席の配置は関係者や面識のある人が同じテーブルに座るように設定します。上座や下座よりも、ゲスト全員が楽しい時間が過ごせることを重視して決めましょう
わからない場合は、親に相談をしましょう。
席次の決め方:最もポピュラーな丸テーブルの席次
メインテーブルがどの席からも見やすく、人数の調整が簡単な点がメリットです。同じテーブルの人全員と話すことができるので和やかな雰囲気になります。
席次の決め方:招待客が多い時は長テーブルが主流
丸テーブルより多人数が座れます。格式があり、落ち着いたムードになるので和食向けです。会話する人が隣の人に限定されるのが難点です。