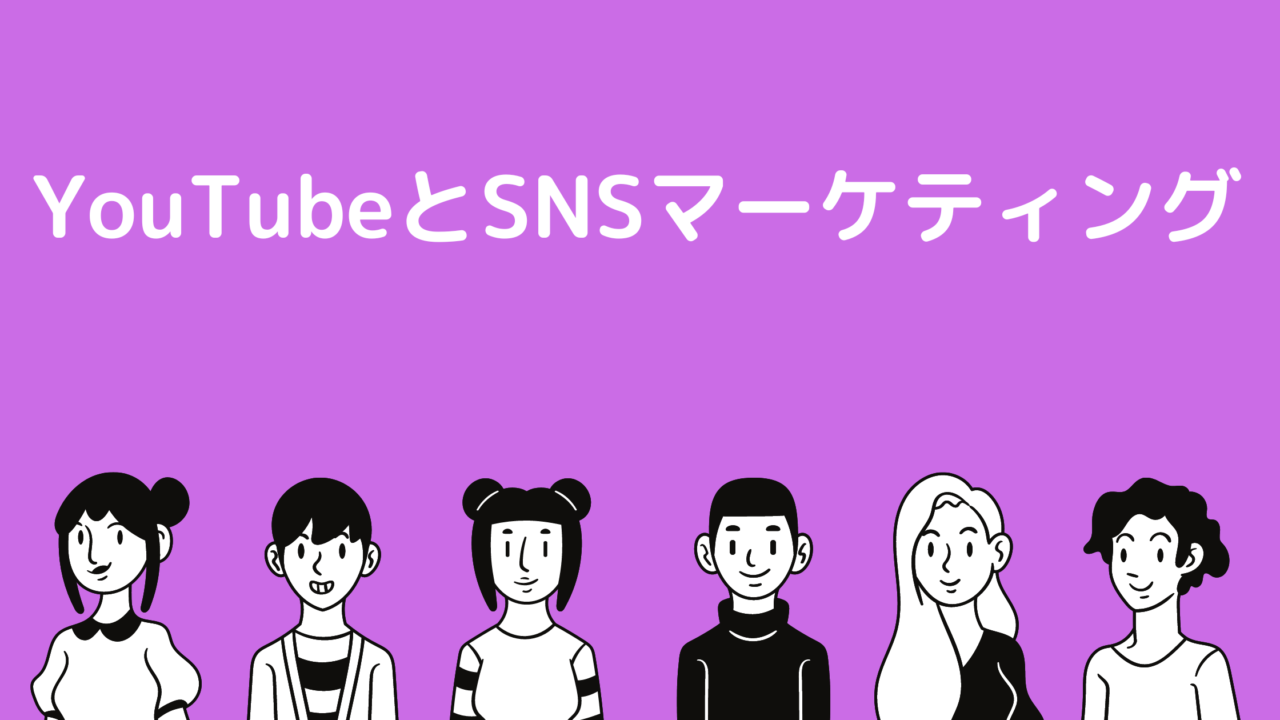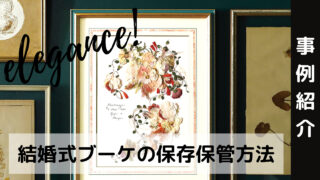結局は「クオリティ」が一番大事
動画の質を上げるためには、量をこなす必要がある
YouTubeは、台本とCTAがとにかく重要です。
台本は一言一句まで丁寧に書き、CTAは具体的にして最後に告知するのが鉄則です。
台本を作る時の注意点は、相手と対話しているような気持ちで書き、一方的にならないようにすることです。そうしないと、視聴者はすぐに離脱してしまいます。
また、CTAは最初や途中にはなるべく入れないようにして、最後にだけ入れることで「濃いお客様」が集まってくれます。
僕のYoutubeが伸びた理由は、次の2つに集約されます。
- 初心者にもやさしく、マス寄りの動画であること
- 上級者が見ても感心し、気付きを与えられるような部分が多く含まれていること
この2つを押さえつつ、少しレベルが高めのことも盛り込むと必ず伸びます。
また、視聴者が「2本目」に観る動画も重要です。例えば、何か1本の動画がバズって流入した新しい視聴者が「なんこの人面白い。ほかの動画はどうかな?」と思ってチャンネルにたどり着き、2本目の動画を観て「面白い」と感じて、やっと登録してくれるわけです。
つまり、「2本目に観た動画」で確実に興味を持ってもらうためには、すべての動画を高クオリティで作るしかないのです。
結局は「質が大事」ということなのですが、常に丁寧に作ることを心掛けているだけではダメです。
量をこなし、少しずつ修正する。これこそ、「質をあげる」ということです。
まずは思考停止でもいいから、とにかく量をこなしていくことが大事です。
そうすれば、徐々に質を高めるためのヒントが得られるようになります。

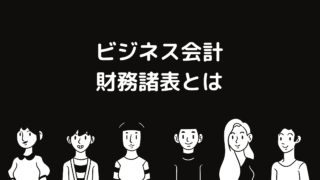
サムネイルタイトルが集客を左右する
動画を作る際は顧客の行動導線上から決める
動画を作る際、ほとんどの人は「動画→タイトル文字→サムネ文字→サムネデザイン」の順番で作ります。
しかし、僕の場合は「サムネ文字→タイトル文字→動画→サムネデザイン」の順番で作ります。
なぜかというと、視聴者は「サムネイル→タイトル→動画」の順で視聴するので、視聴者のアクション導線と同じ順番で力を入れるべきと考えているからです。
また、動画から作ると、できた動画に引きずられてサムネタイトルも視聴者の反応が悪いものになってしまう場合があるので、動画から作成するのはオススメしません。
最も大事なのは動画の内容であることは間違いないのですが、「決定の順番」に関しては、顧客の行動導線上から決めるべきです。
視聴維持率を上げるためのテクニック
Youtubeは、「視聴維持率」が命です。なぜなら、YouTube側は「視聴者になるべく長くとどまって、最大の収入源である広告を見てほしい」と考えているからです。
皆さんがYouTubeで配信する動画のジャンルにもよると思いますが、僕と同じような「ハウツー系」の場合は、視聴維持率を上げるために8つのつまらない動画の特徴にあてはまる部分がないか気を付けておくのをオススメします。
- 冗長なオープニングがある
- 無意味な前置きが長い
- カットが雑で間が多い
- テロップが見づらい
- サムネ詐欺
- 音質が悪い
- BGMやSEが多過ぎ
- 映像が暗い
自分の過去の配信動画を分析しましょう!
「視聴維持率」を上げるためには、自分が過去に配信したYouTube動画を分析することも大切です。
ぼくの場合は「視聴維持率が落ちる箇所」を確認し、なぜ多くの視聴者がその箇所で離脱したのかを分析して、次に活かすようにしています。
また、視聴維持率が落ちつ箇所が分かったら、該当する部分をYouTubeStudio内のエディタでカットするという方法もあります。
カットしたあとに元に戻すこともできるので、是非、試してみてくださいね!
動画を作成し、アップするだけでなく、そのあともできることは色々あります。こうして動画の精度を高めていくことで、動画の資産性もアップしていきます。
YouTubeで「伸びる人」「伸びない人」の特徴
YouTubeで成功する人は3種類います。
- もともと性格がYouTubeに向いている人
- YouTube用にキャラを使ってコツコツと努力できる人
- 背景の実績がもともとすごい人
YouTubeで成功している人は、この3種類のどれかに必ず当てはまります。ちなみに、僕は明らかに「2」です。もとからYouTubeには向いていなかったし、実績もほかの発信者の誰よりもありませんでした。
しかし、裏を返せば、もともと向いていなくても、誰もが認める凄い実績がなくても、コツコツと努力さえすれば誰でも成功できるということです。
本気でぶつからない人に成功はない
加えて、YouTubeですぐに伸びる人には「素直」「行動量がすごい」という2つの特徴があります。僕が見て来たなかで、この2つの特徴を持つ人は100%伸びています。
そして残念ながら「まったく伸びない人」にもいくつかの共通した特徴があります。YouTubeは戦場です。本気でぶつからないと成功することはできません。
結局は継続が一番の近道
継続していれば、誰だってつらくなる時はある
「台本作成も動画撮影も大変だな」と、何度も思いました。でも、「そんなふうに嘆いている暇があるなら、まずは弱音を吐かず、行動あるのみ」と何度も自分に言い聞かせて行動しました。
誰だってあっという間に年を取りますし、嘆いてばかりで行動しないなんて、すごくもったいないと思います。
「最低限、毎日これをする!」をルールを決めるようにしましょう!
とはいえ、ハードルを上げる必要はありません。最低30分でできることでも大丈夫です。気が重い時でも、ルールを決めて取り掛かり始めると意外と行動できます。
YouTubeは「緩く熱心に」やることが肝
YouTubeは「熱し過ぎず、冷め過ぎず」に運用することをオススメします。何ごとも、あまり熱くなると途中で嫌になったり、飽きてしまったりしがちなものです。しかし、YouTubeは最後まで継続した人が勝ちます。
僕は投稿の頻度が下がっている時でも、台本を書いたり、過去の投稿動画の分析をしたりと、次の投稿に向け、常に何かしらの準備をしています。矛盾した表現かもしれませんが、僕は「緩く熱心に」やることが肝と考えています。
物事を継続して成功をつかむためには、何かを「捨てる」ことも大事です。限られた時間を有効活用する方法はこれしかありません。
現在、僕は遊びの時間をほぼ捨てて、その時間を事業に充てています。普段は夜中の3時まで作業や撮影をして、翌日はお昼前に起きて筋肉トレし、14時からまた夜中の3時まで作業という生活の繰り返しです。
お金も普段はほぼ使わないのですが、十分に幸せな生活です。
僕も稼ぎが増え始めたことは遊んだこともありますが、よほど「遊び好き」な人でない限り、遊びは意外と簡単に飽きてしまいます。
結局のところ、僕が今の実績を出せたのは、こうした地道な努力と行動のおかげで、生まれ持った才能やセンスのおかげ、なんてことはありません。
稼いでいる人は、決してほかの人と比べて秀でた才能を持つ人という訳ではなく、ただひたすら行動している人なんだと思います。ロジックで考えてすぐに成功をつかめるほど器用でも優秀でもないから、ひたすら行動するのです。
Twitterの特徴と利点
中級者以上に出会いやすいTwitter
Twitterをマーケティングに用いる場合、その運用目的は価値提供によって信頼を集めたり、拡散して認知を拡大したりすることです。そして、LINEアドレスやメールアドレスなどのリストを獲得することです。
僕の場合、「英語」と「マーケティング」という2種類のコンテンツを販売しているのですが、初心者がターゲットである「英語」のコンテンツの集客にはYouTubeを使い、「マーケティング」のコンテンツの集客には中級者以上に出会いやすいTwitterを使用しています。
YouTubeは集客力が非常に高い半面、初心者が多過ぎるためレピュテーションリスクがあるので、マーケティングの集客にはほとんど使っていません。
「伸びるツイート」は何度でも使い回す
Twitterの主な特徴は「拡散性が高い」「ユーザーの学習意欲が高い」「運用コストを低く抑えられる」という点にあります。
特に拡散性の高さは、YouTubeにはない大きな特徴です。例えば、実績のない初心者のツイートでも、それがインフルエンサーに取り上げられたりすると一気に拡散してフォロワーが増えることがあります。
また、文字投稿が基本なので、もともとリテラシーが高いユーザーが多く、そうした人たちは学習や情報収集にも熱心な場合が多いため、僕が扱うような学習・ハウツー系の高額商品の販売のための集客に適したプラットフォームといえます。
また、基本的には文字投稿のため、運用コストがほとんどかからないこともTwitterの大きな利点です。
YouTubeの場合は、動画の撮影や編集などさまざまなコストがかかりますが、Twitterの場合は、忙しくてなかなか時間が割けない時でも、1ツイート3~5分程度で、ユーザーに対して手軽に「価値提供」ができます。
資産性が高い点も、Twitterの特徴です。YouTubeと違い、Twitterの場合は「伸びるツイート」を何度でも使いまわすことができます。
例えば、一度投稿して伸びたツイートをスプレッドシートに貯めておいて、一定期間をおいて何度も同じツイートをするのです。
「同じツイートを何回もして意味あるの?」と思うかもしれませんが、新にフォロワーになった人が過去のツイートを遡って全て見ることなんてことはほとんどありません。なので、同じとうこうをしてもまた伸びるのです。
また、Twitterの場合は、一度フォローした人が、その後わざわざフォローを外すということはあまりないため、YouTubeのように一度炎上するとフォロワーが一気に100人、1000人単位で減るということもありません。
それだけ、Twitterは「資産性が高いメディア」といえるのです。
Twitterの原理原則
新規ユーザーにリーチしやすいTwitter
Twitterがマーケティングに極めて適したプラットフォームである理由の一つに、新規ユーザーにリーチしやすい点があります。
例えば、1人のフォロワーが「いいね」や「リツイート」をした場合、似たような属性を持つ「そのフォロワーのフォロワー」だけでなく、「そのフォロワーのフォロワーのフォロワー」などにずっとリーチしていき、拡散していく可能性があります。
これが、YouTubeにはないTwitterの特徴です。
Twitterの場合、フォロワーなどが「ファン化」する可能性はYouTubeに比べて少ない半面、良い情報は拡散されやすいのです。そして、このように新規ユーザーにリーチした時に「プロフィール設計」が非常に大事になります。
フォロワーが増えるかどうかは「プロフィール設計」次第
Twitterのプロフィールを設定する際には、ターゲットがフォローするメリットを明確にしなければなりません。
| 興味づけ | 「この人は普段、どういったものを発信しているのかな?」といったトリガーになる要素が必要です。「この人、何なんだろう?」と思わせるような興味づけが必要です。 |
|---|---|
| フォローするメリット | ユーザーに対して、投稿者が普段からどのような発信を行っているかが分かるようにしておく必要があります。コンセプトが“ブレブレ”だと、途端に興味を失われてしまいます。 |
| 権威性や経歴 | 実績がそのまま権威性につながる場合もあります。また、学位や資格といったものでなくとも、あなたの経験や経歴が「権威」になる場合もあります。 |
また、アイコンも重要です。アイコンはTwitter上におけるあなたの「顔」ですので、普通の自撮り写真などでなく、プロのカメラマンにお願いして見栄えの良いものを載せた方が良いでしょう。
どんなツイート内容が人を引き付けるのか
人を引き付けるための9つのポイント
ツイートする内容を考える際は、9つのポイントを意識することで、権威性を出したり共感を生んだりすることができるようになります。
| 権威性 | 自分は何を成し遂げた人物なのをありのままに書きましょう。嘘をつくのは絶対にNGです。経歴や実績などを盛ってしまうと、変にユーザーの期待値を上げてしまい、あとでガッカリされるなんてことも。それよりも、実際に行動して自分で実績をつくっていくことが重要です。そうすれば自然と実力もつきます |
|---|---|
| 共感 | 例えば「月収10万円→50万円になりたい人が抱える悩み5選」など、他人が思っているであろうことも言語化すると、読む人の興味を引くことができます。 |
| 理想 | 「パソコン1台で働ける」「ストレスも通勤もなしで働ける」など、具体的なイメージを書くことで、理想の未来や状態をイメージさせることができます。 |
| 再現性 | 権威性は重要なのですが、「自分にはできない」と思わせてはいけません。「自分にはできない」と思っている人に向けて「僕は生まれながらの天才ではありません」などと同じ立場であることを伝え「あなたにもできる」ということを強調しましょう。 |
| 親近感 | 例えば「僕も昔は手取り18万円で疲弊していました」などと心理的な距離を近づける言葉を使うと読者に「身近な存在」と感じてもらうことができます。 |
| お役立ち | 普段から共感を生むツイートをしていても、価値提供にあたる「お役立ち情報」をしっかりツイートしていないと、ただの独り言になってしまいます。最終的に商品販売に結び付けるためには、発信内容が「勉強になる」と思ってもらうことが大切です。 |
| 仮想敵 | 読者と共通の敵を持つと信頼されやすくなります。ただし、「人」ではなく「概念」を否定するようにしましょう。また、この方法は効果的な一方で、やり過ぎると余計な敵をつくってしまうこともあるので、時々使うぐらいのほうが良いでしょう。 |
| 行動の重要性 | 特に教材やハウツー系の商品の場合は、「行動することが一番大事」と伝えることで商品を買ってもらいやすくなります。 |
| 自己投資の重要性 | 「お金を払って勉強することが大事」ということを理解してもらうことで、「お金の心理的ハードル」を下げることができます。 |