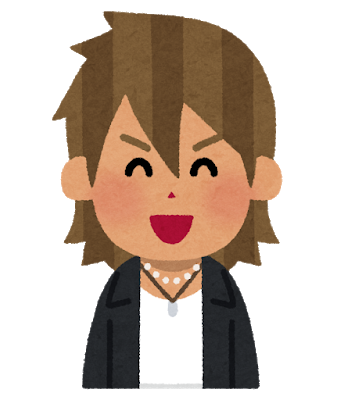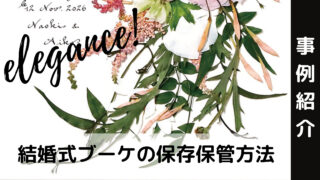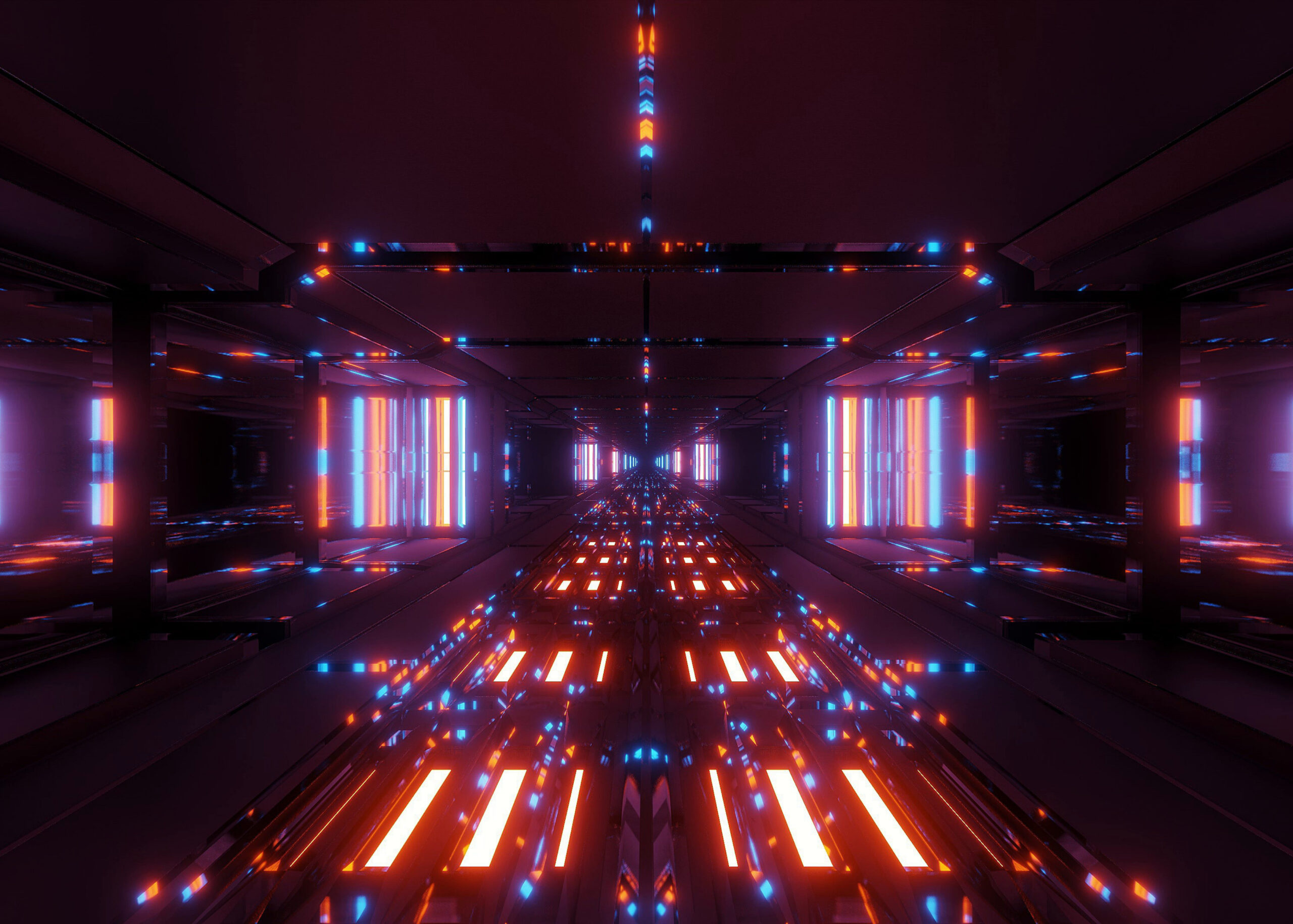

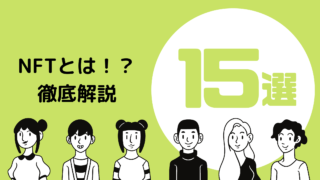









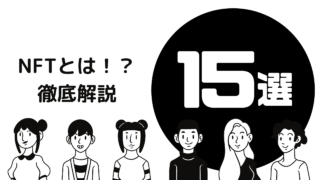



NFTの法律と会計
NFTの発行とは何か?NFTの保有・移転の法的意味や販売での実質的取引対象とは
NFTに関連する当事者とその法的関係について整理しておきます。
まず、NFTとは一般にブロックチェーン上で発行されるトークンのうち、トークン自体に固有の値や属性をもたせた代替性のないトークンをいいます。
ビットコインなど、ブロックチェーン上で発行されるトークンは、通常、ひとつひとつに個性がなく、同じトークンが多数存在していますが、NFTはひとつひとつのトークンが固有の値をもち、他のトークンと区別できるという特徴を有しています。
この性質を利用して、本来は容易にコピーできるデジタルコンテンツをNFTに表章させることにより、デジタルコンテンツに希少性をもたせ、ブロックチェーン上で取引できるようにするというのが、NFTの基本的なコンセプトです。
NFTに限らず、ブロックチェーン上で発行されるトークンの機能や当該トークンに表章される権利はさまざまです。
たとえばアートNFTの発行場面を考えると、アート作品をもつアーティストと、そのNFTを購入するNFT購入者が存在し、それぞれが当該ブロックチェーン上のトークンに係るウォレットを有していれば、アーティストが作品をNFT化したうえで当該NFTを購入者に対して発行することが可能となります。
もっとも、現在のNFTマーケットにおいては、NFTの発行が発行者・購入者の二者間で完結することはすくなく、NFTの発行と販売を一手に担うプラットフォームが関連当事者として無視できない存在となっています。
2021年3月にデジタルアーティストBeepleのEverydaysThe First 5000 Daysというデジタルコラージュ作品のNFTを取り扱ったChristiesを皮切りに、同じく伝統的なオークションハウスであるSothebysもNFTオークション事業に参入し、池田亮司氏のA Single Number That Has 10,000,086 Digitsという作品のNFTなどの複数のアートNFTが出品されました。
これに加えて、NFTの取引をはじめとする利用条件・環境が技術仕様や利用規約の形であらかじめ定められていることによって、NFTの売主・買主間の個別交渉などの事務負担を減らし、いわゆるセカンダリーマーケットも活発化させていると評価することもできるでしょう。
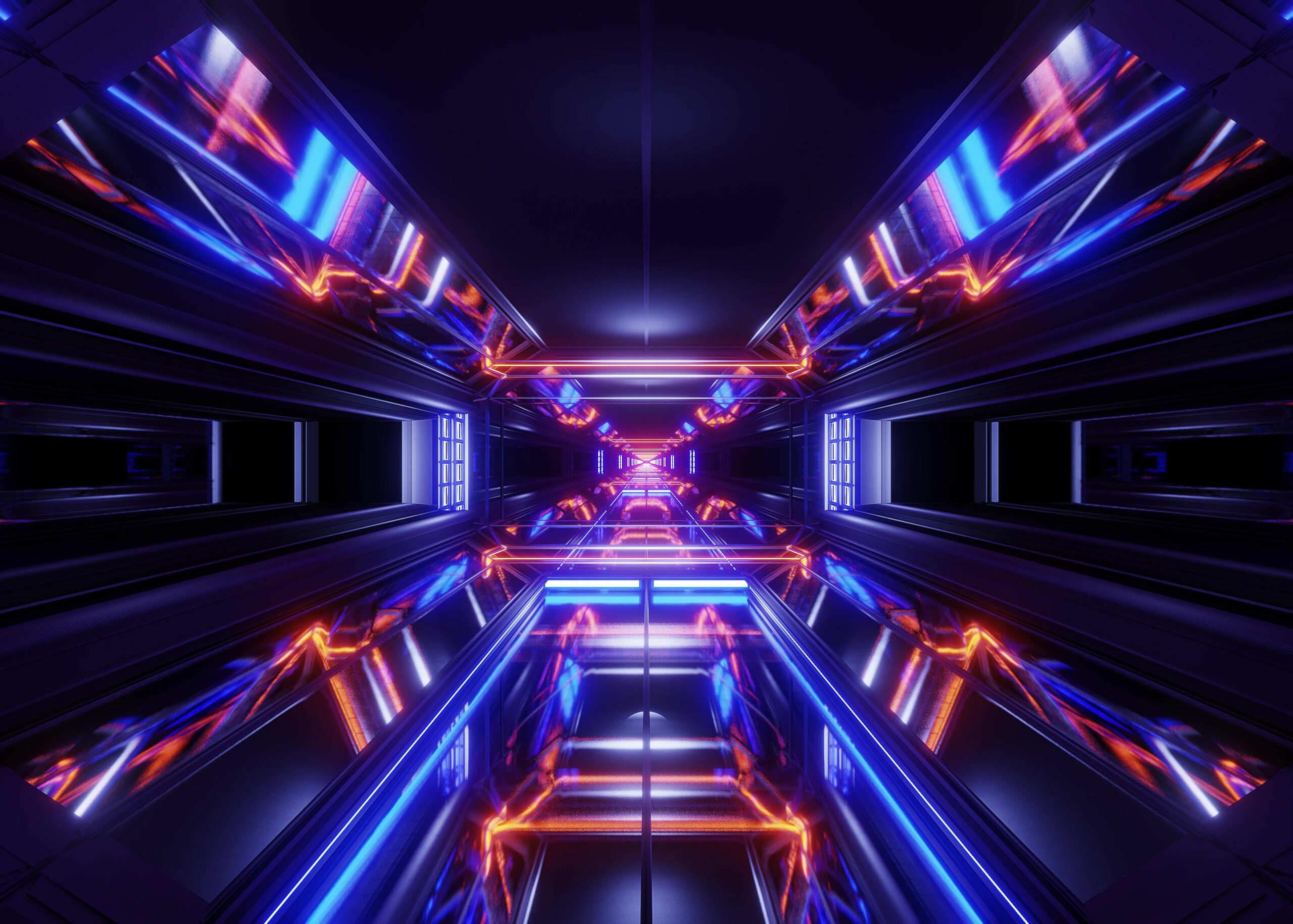
NFTやその保有・移転の法的性質
とりわけ、NFT保有者が何らかの利用権を行使できる場合に、それが法的にはどのような権利に基づいて、誰に対して主張できるものであるかを考えることは、NFTに関する法律関係を安定的なものとするためにも重要です。
また、議論される場面によっても見え方や答えが違うということがあるでしょう。こうしたことから、さまざまな事例があるNFT全体を抽象的・一般的に議論するよりも、何かしらの具体的な事例を念頭に置いて議論した方が理解しやすいでしょう。
そこで、ここではデジタルアートに関するNFTを特に取り上げ、主に著作権法の観点から考えてみます。
こうしたアート関連のNFTは、取引が特に活性化している事例のひとつであり、読者の皆さんも色々なニュースなどでも事例を見聞きしているかと思います。
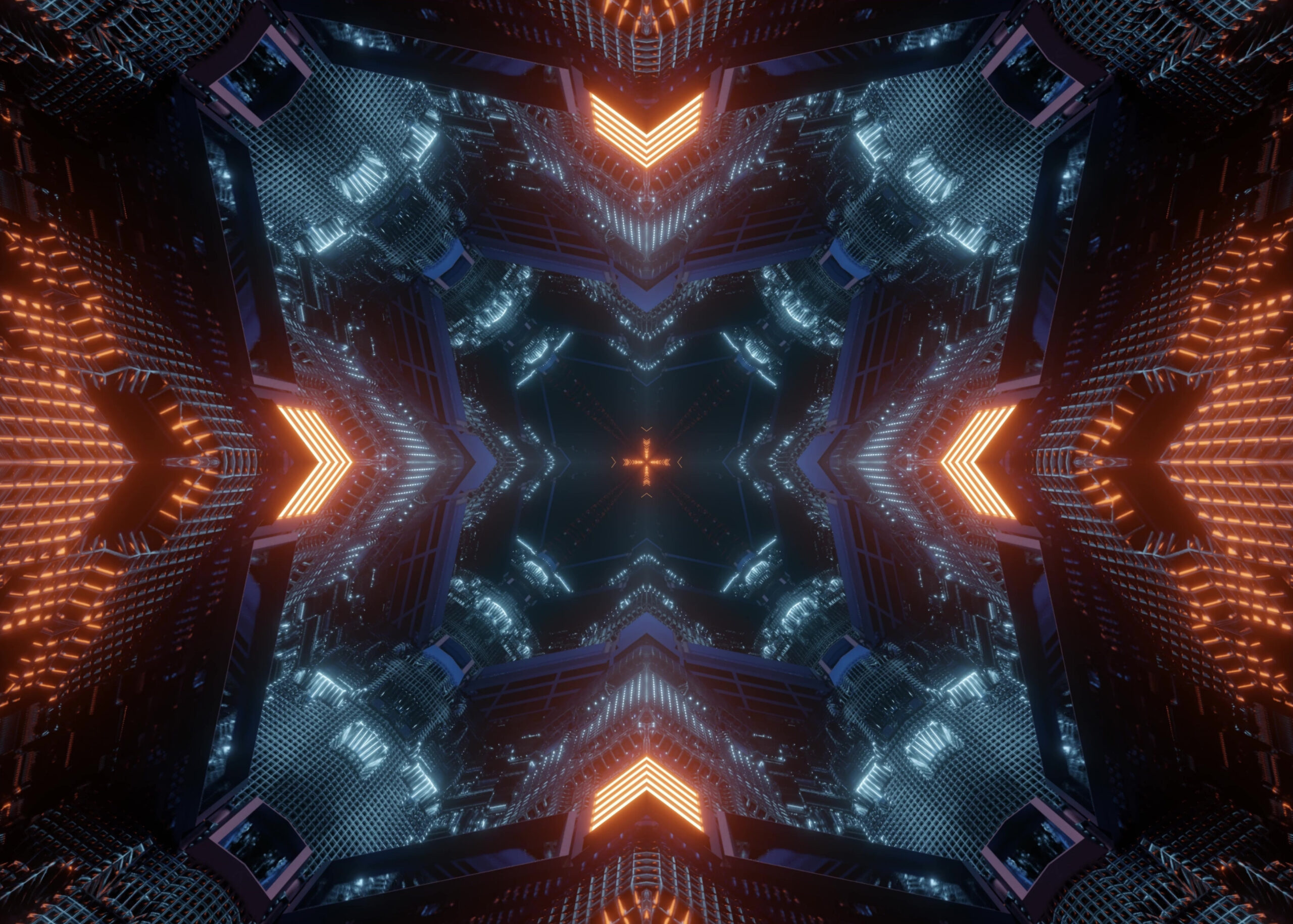
NFTアートとアートNFTの概念整理
具体的な検討に入る前に、少しだけ概念の整理をしておきたいと思います。このあとの議論を理解するためにも大事なポイントとなります。
デジタルアートのNFTに関する話題において、一般的に使われることの多い表現は、NFTアートという言葉です。
これは具体的には何を指しているのかというと、あの著名なアーティストのNFTアートを手に入れた!とは、あのNFTアートはとても美しくて素敵だ!という言葉を耳にしたとき、その客体として指し示されているものは何だと感じるでしょうか?実は、このNFTアートという用語が指し示すものには、
①NFT化の客体であるアート作品
②NFT化した結果として発行されるトークン
という2つの意味があるように思われます。
この整理が曖昧なままですと、ある人がNFT化の客体であるアート作品の意味で、アーティストはNFTアート自体を購入者にわたしたわけではないはずだと主張し、別の人がNFT化した結果として発行されるトークンの意味で、購入者はNFTアートを購入してウォレットに入れたのだと主張しているとき、議論がまったくかみ合わないことになってしまいます。
こうしたことから、アートNFTとNFTアートという各用語を使い分けしています。
そのため、小さなドット絵などがNFT化の対象であるなど、コンテンツ自体をトークンの内容として記録することが可能であるような例外的な場合を除いて、NFTアートとアートNFTとは一致しないこととなります。
そして、このように両社が一致しないときにこそ、アート作品とNFTとをどう関連づけるかが、いわゆるNFT化やその後の法律関係を明確化するうえで問題となるわけです。
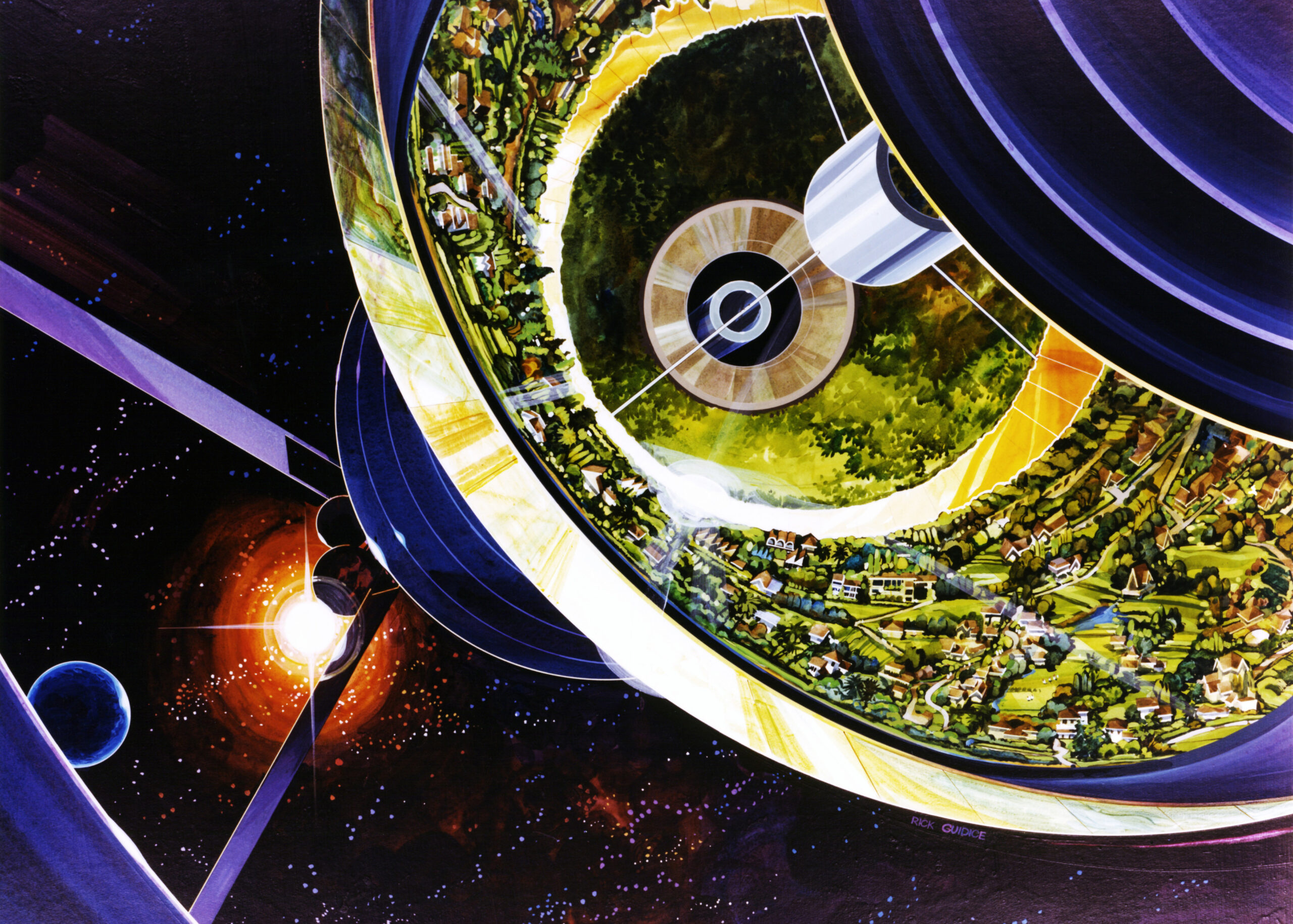
著作権の基盤
NFTの法的な位置付けを著作権法の観点から分析する前提として、著作権法や著作権についても、ここで簡単に解説しておきたいと思います。
まず、著作権法は、著作権の対象となる作品などを著作物と定め、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または恩田クの範囲に属するものと定義するとともに、小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物、絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物、プログラムの著作物など9つの典型例を挙げています。
そして、ある作品が著作物に該当する場合、その創作者には、著作権と著作者人格権が発生します。
このうち著作権は、著作物の利用に関する財産的な権利を指し、一般的に支分権と呼ばれるさまざまな権利で構成されています。
著作権は、著作者人格権とは異なり、大安者に譲渡することが可能ですので、創作者に限らず著作権を保有している者を著作権者と表現します。
著作権法は、著作権の譲渡方法を特定の方式に限定していないため、たとえば口頭での合意による譲渡も可能です。
また、著作権侵害は、一定の場合には刑事罰の対象ともなります。
さらに、著作権者は、著作物を利用しようとする者に対して、利用方法と利用条件を定めたうえで、利用を許諾することができます。
この利用許諾は、一般的にライセンスと呼ばれ、その許諾方法に関しての制限もありませんから、利用規約・契約による方法に限らず、口頭での利用許諾も認められます。
これに関連して、著作権者が不特定多数に一定の条件のもとで自らの著作物を利用許諾を一方的に公表することがありますが、その場合の条件設定を簡易に行うための仕組みはパブリック・ライセンスと呼ばれることがあります。
その代表例であるクリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、著作物を公開する際に複数の記号やマーク委を組み合わせて表示することで利用条件を簡易に示すことができ、たとえば、表示・改変禁止のマークをつけて著作物を公開すると、第三者は、著作者との直接の契約関係がなくとも、作品名や作者名といった作品情報を常時さえすれば、作品を改変しない限地、その著作物を自由に複製したり、収益化したりすることができるというわけです。
以上の基礎知識も踏まえて、対象となるアート作品が著作物に該当することを前提として議論を進めたいと思います。

アートNFTの正体:利用規約におけるアートNFTの取り扱い
まず、NFTの発行や取引の場として用いられることが多い、いわゆるNFTマーケットプレイスの利用規約ではどのように扱われているのでしょうか。いくつかの利用規約を見てみると、そこでは通常、NFTの法的性質は明治されておらず、せいぜい、アートNFTの保有がNFTアートの著作権の保有を意味するわけではない旨が説明されている程度です。
アートNFTの保有者が行い得る行為も、プラットフォームやアート作品ごとに大きく異なります。
非商業的利用のみを認めるもの、商業的利用も認めるもの、複製や展示など一部の利用方法のみを認めるものなどがある一方で、アートNFTの保有者であることをNFTの購入・保有という事実により世間に示せるだけで、何らかの利用が許諾されているわけではない場合も多くみられます。
このような、アートNFTの保有を通じてNFTアートを利用できる範囲は、プラットフォームで一律に決まっている場合もあれば、NFTを発行するアーティストがNFTごとに個別に設定できる場合もあります。

アートNFTの正体;アートNFTの保有はNFTアートの所有ではない
巷では、アートNFTの保有により、それと関連付けられたデジタルアートの所有を証明するといった説明が多く見られ、そのことをもって、NFTをデジタル所有権を実現するツールだと説明する向きもあります。このような説明は、はたして適当でしょうか。
たしかに、アートNFTを第三者に移転できる者は通常、それが記録されているブロックチェーン上のアドレスに対応する秘密鍵を知る者に限られます。
そうした者が当該トークンを事実上専有することから、一般的な意味でいうところの所有関係があると見る余地はありそうです。
しかし、そもそもデジタルアートを含むデータは、法的な意味での所有権の対象とはなりません。
所有権があれば、その占有を奪われたら所有権に基づく返還請求権を行使することができますが、NFTには類似の権利がなく、たとえばNFTを勝手に移転されてしまっても、その返還請求権を当然に行使できるわけではありません。
したがって法的には、アートNFTの保有がNFTアートを所有していることにはならず、デジタル所有権といった表現は少々不正確なものといわざるを得ません。

アートNFTの正体:アートNFTの保有はNFTアートの著作権の保有ではない
著作権についてはどうでしょうか。アートNFTの取引に伴って、NFTアートの著作権それ自体も一緒に移転させることは、法的には実現可能です。そのような取引当事者の間で合意すればよいのです。もっとも、NFTと著作権とを当然に結びつける法律上の根拠があるわけではないため、それは、譲渡による著作権移転を実現する方法として、合意に基づくNFTの移転を便宜的に用いていると評価すべきものです。
このようにトークンの取引により著作権を移転すること自体は法的に可能なのですが、それでは、トークンの取引によって「のみ」著作権を移転可能とすることを確保することは可能でしょうか。
著作権法上、著作権譲渡の方式自体を特定の方法に限定するということはできません。
そのため、どこかの時点で著作権者が第三者と別途の契約を結ぶなどして、NFTの譲渡を伴わずに第三者に著作権だけを譲渡してしまった場合には、その著作権の移転自体は有効に確定します。
このような状況を防ぐことは現行法上は難しく、よってNFTと著作権の保有関係を一体的にとらえる仕組みには、克服しがたい難点があるように思われます。
これに対して、著作権に基づく一定の許諾をNFT保有者に与えるという方式であれば、それを実施する上での克服しがたい難点はないといえます。
実際に、NFT保有者が利用規約等に基づきデジタルアートを一定の態様で利用することが許されている事例は多く存在しています。
このようなケースであれば、アートNFTの保有を通じて、ライセンスを保有しているだとか、アートNFTの移転によりライセンスを移転するなどと表現することも、それほど不自然ではないでしょう。

アートNFTに関するケーススタディ
ここからは具体的な場面をもとにNFTの法律関係について理解できるように、ケーススタディ形式でアート作品のNFTに関連して発生し得る法的論点や実務的論点をいくつか紹介しつつ若干の分析を加えたいと思います。
著作権に基づくライセンスと、複数のプラットフォームをまたいだ売買
しかしBはその後、当該NFTをXではない別のプラットフォームYで転売し、購入者Cがこれを購入した。この場合、Cは当該アート作品をコピーして商品化できるか。
あるNFTが、ERC-721トークンなど一般的なブロックチェーンで扱える形式のトークンである場合には、複数のNFTプラットフォームをまたぐ形での取引や、プラットフォームを利用しない相対での取引が行われることも考えられるでしょう。
このとき、アートNFTの保有者に対するライセンスが、プラットフォームに依存したものであるか、それとも複数のプラットフォームをまたいでも有効であるかは、アートNFTのエコシステムが特定のプラットフォームに依存せず拡大できるか否かの試金石であり、重要なテーマといえるでしょう。
この場合、購入者Cは商品化について許諾を得ていることにならず、こうした利用権を得ることが購入者Cの取引奥的であるならば、Xでない場でトークンを購入するインセンティブ自体がそもそも働かないことになります。
そのため、そのようなNFTの取引はそもそも、X以外では行われにくいと考えられます。
これに対し、利用規約が明確にプラットフォームXのユーザーでないNFT保有者に対しても利用権を許諾している場合には、購入者Cにも許諾に基づく商品化を行う可能性が出てきます。
将来出現する不特定の許諾埼の存在を前提として、あらかじめ包括的な許諾を公に行う方式としてはパブリックライセンスの実務が参考になります。