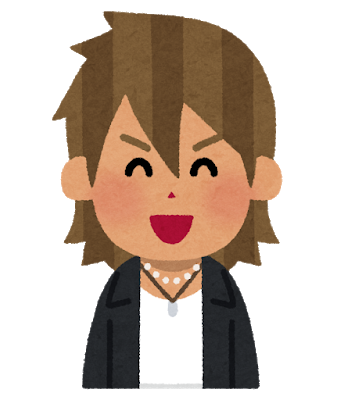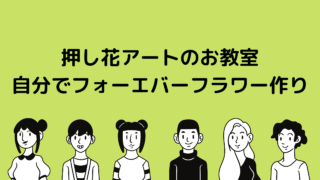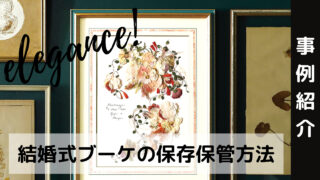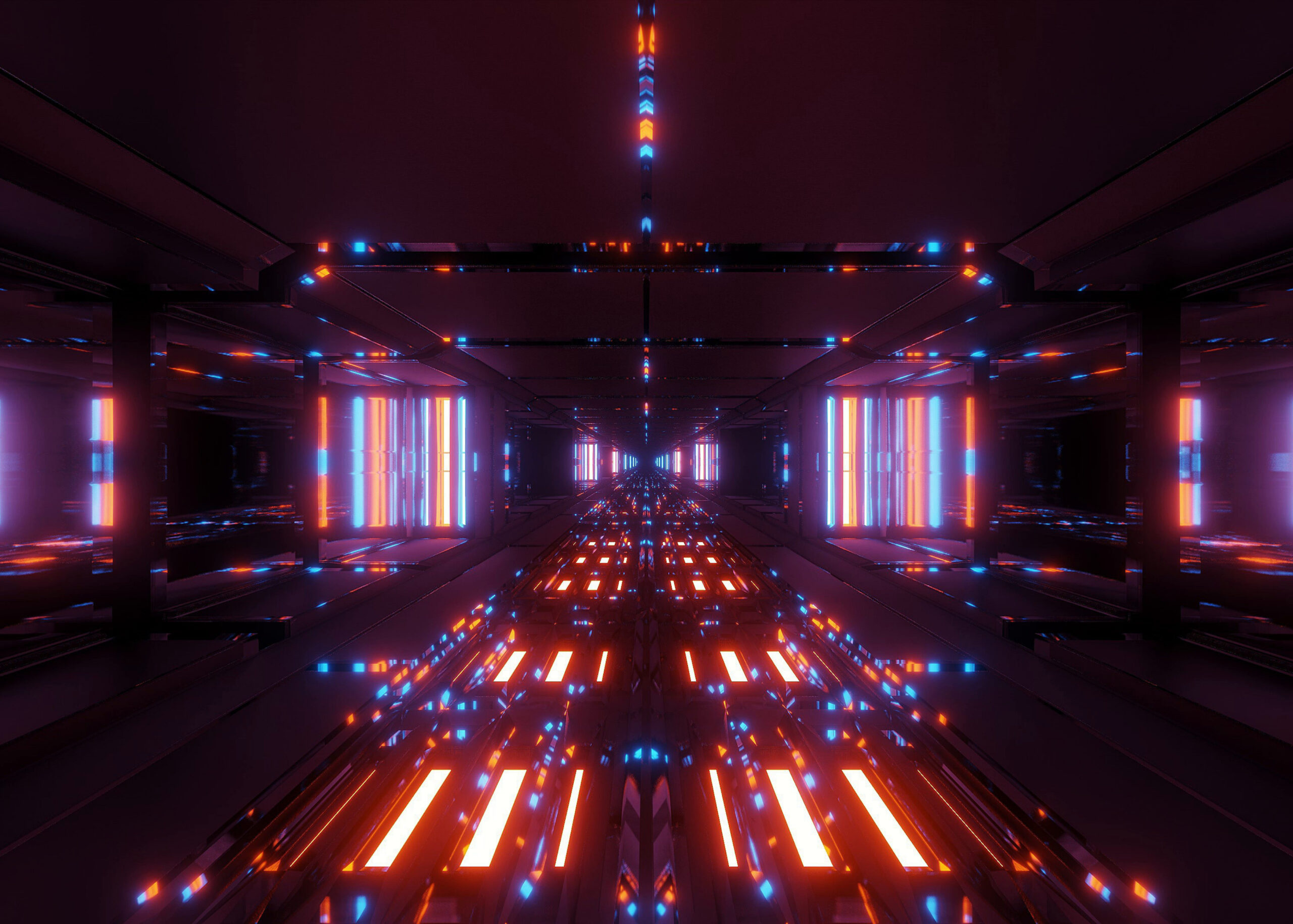

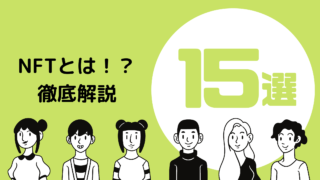









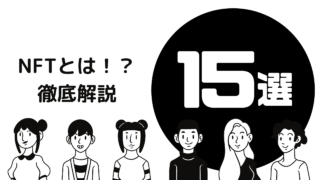

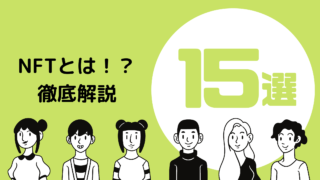

NFT普及のために必要な4つの技術的課題とその解決法
NFTの4つの技術的課題と用語について
NFTは、さまざまなブロックチェーン上で発行されているほか、いろいろな特徴をもったNFTマーケットプレイスが運営されています。しかし、NFTには、たくさんの技術的な課題が山積みしており、まだまだ発展途上な状態です。
- トランザクションとは
イーサリアムの送金やスマートコントラクトの実行など、ブロックチェーン上で処理された取引データ記載された情報のことです。
- メタデータとは
NFTは、metadataと呼ばれるデータ領域をもっており、そこにはname、description、imageがデータとして記録されていることです。
- ディスクリプションとは
NFTのmetadata領域に存在するNFTの説明を記載したデータのことです。
- サードパーティ
当事者ではなく、他の第三者のことです。ここでは、管理者となるサービスプロバイダーではなく、AWSなどをさします。
- ストレージサービスとは
インターネット経由で利用できるオンラインのデータ保存サービスのことです。
- スケーラビリティとは
トランザクションを同時により多く処理することができる最大限の処理性能のことです。
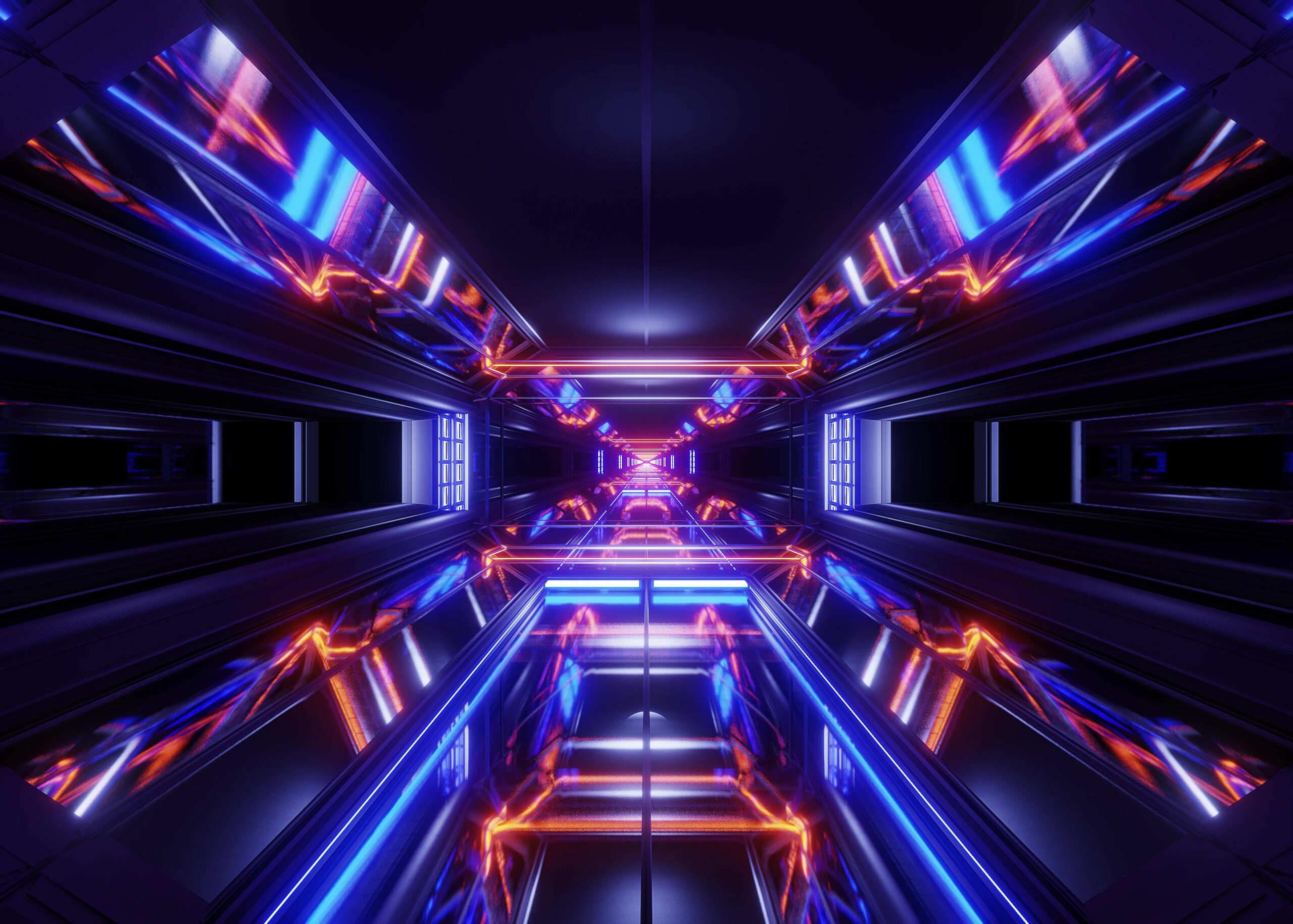
NFT画像データの管理問題について
現在、さまざまなブロックチェーン上でNFTマーケットプレイスが運営されていますが、それらのマーケットプレイスで取扱いのあるNFTは、ほとんど次の2つのタイプに分かれています。
- タイプ1:
NFTの画像データをブロックチェーン外で管理しているNFT
- タイプ2:
NFTの画像データをブロックチェーン上で管理しているNFT
上述する2つのタイプのNFTにおいて、それぞれNFT画像データ管理の側面で問題点が存在しています。
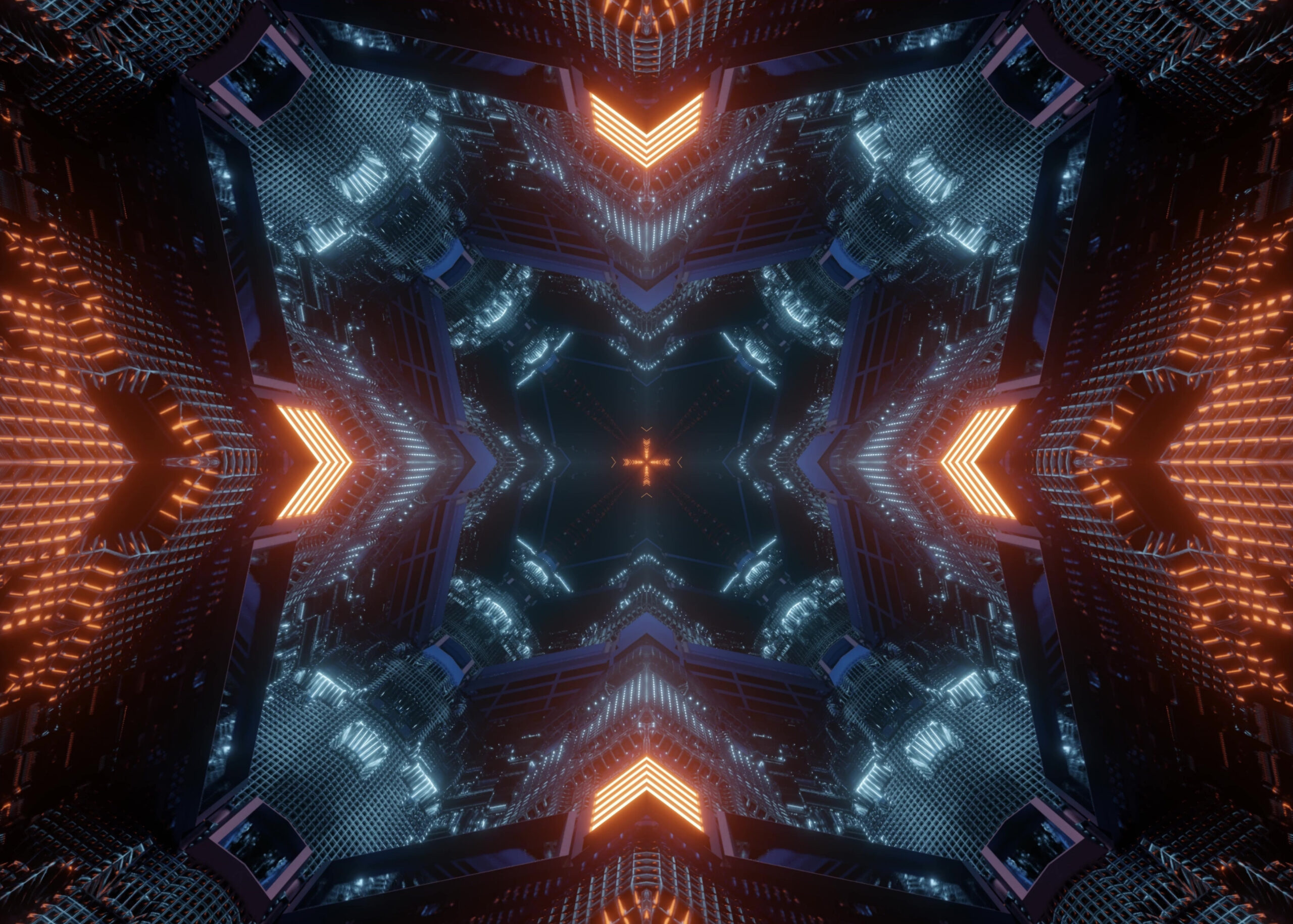
★タイプ1:NFTの画像データをブロックチェーン外で管理しているNFT
そのメタデータ内には、それぞれ個別NFTの名前やNFTのディスクリプション、NFTの画像データの参照先などがデータとして存在しています。
個別NFTの画像データは、ブロックチェーン上には存在せず、ブロックチェーン外のAWSなどのサードパーティのストレージサービスで管理されています。
したがって、ブロックチェーン上では画像データが存在しないことから、さまざまなNFTサービスにおいては、あくまでもブロックチェーン外のAWSなどから、画像データを取得する必要が出てきます。
そこでNFTの画像データは、ブロックチェーン外のサードパーティのストレージサービスに保存して、ブロックチェーン上には、保存してある画像データのURLのみを記録することで、データサイズを小さくしてNFTの管理コストを下げるような工夫をしています。
よってこういった管理コストの側面から、一般的なNFTマーケットプレイスで取り扱われているほとんどのNFT画像データはサードパーティのストレージサービスを利用しているケースが多いのです。
しかし、ここで問題になってくるのは、NFTの画像データが管理されているサードパーティのストレージサービスが何らかの影響によって利用できなくなった場合についてです。
よって、
たとえば、アートやトレーディングカードゲームなど、ユーザーにある一定の視認性が求められるNFTコンテンツを取り扱っている何らかのNFTサービスがあった場合、そのNFTの画像データをサードパーティのストレージサービスから取得することができないので、NFTを購入して利用したいユーザーにとってはかなりの影響が出てしまったり、または、NFTの価値そのものが下落する可能性が出て来てしまいます。
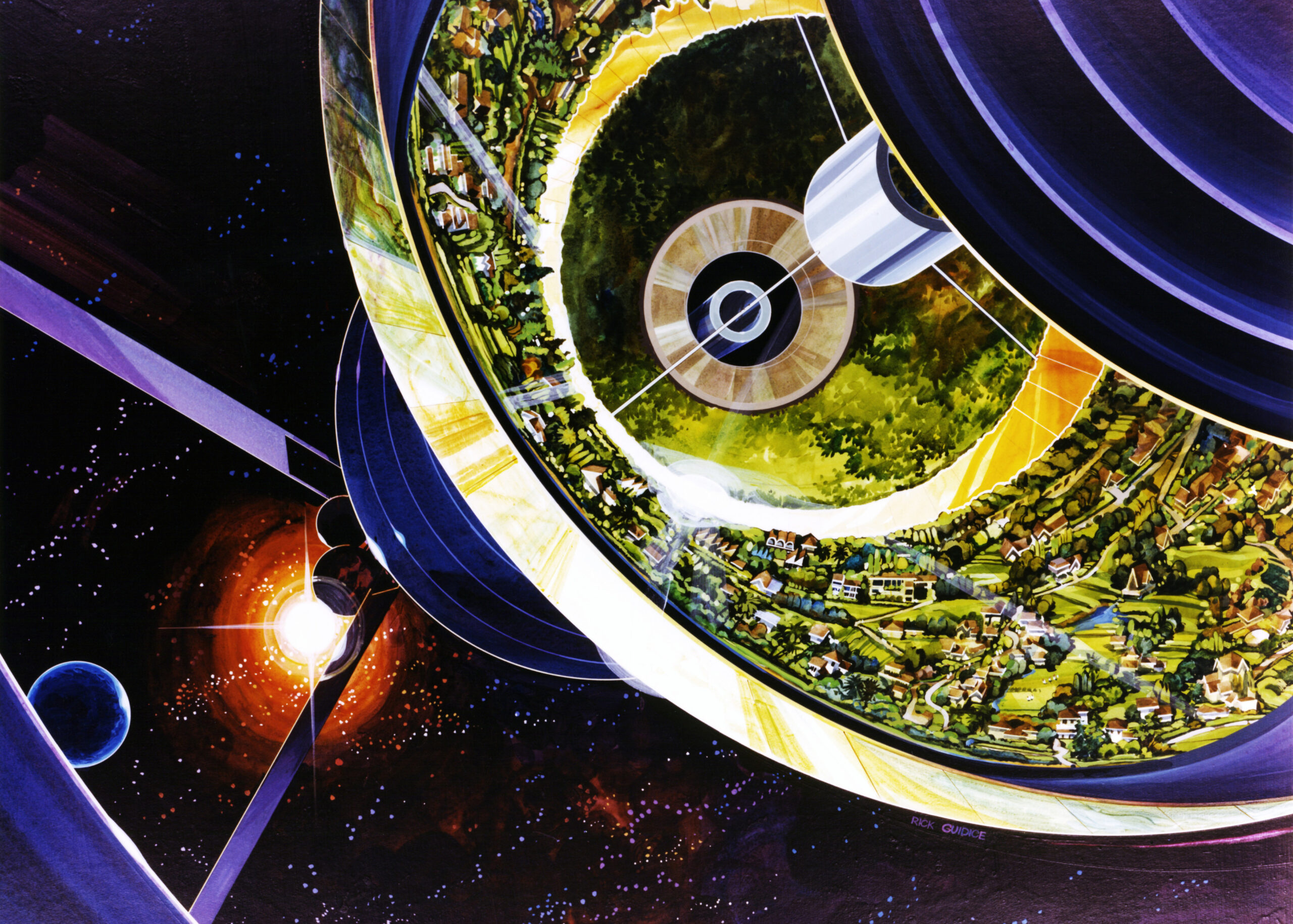
★タイプ2:NFTの画像データをブロックチェーン上で管理しているNFT
このようなげーすのNFTは、サードパーティのストレージサービスで画像データを管理しているNFTとは異なり、すべてのNFTのデータをブロックチェーン上で管理しているため、画像データを管理する外部サービスの影響を受けて、NFTの利用や価値に影響が出るというようなことが起きません。
しかし、すべてのNFTのデータをブロックチェーン上で管理する必要があるので、NFTのデータサイズが大きくなってしまい、その分だけのガス代を支払わなければならず、NFTの管理コストが高くなるというデメリットがあります。
こういった、画像データも含めてNFTのデータをすべてブロックチェーン上で管理するというケースが出てきた背景には、「NFTを所有する」という概念をより明確化する目的がひとつとしてあります。
たとえばタイプ1とタイプ2のNFTを比較すると、タイプ1のNFTはあくまでも外部サービスの利用を前提としてNFTの管理が前提となっており、たとえ、あるユーザーがNFTを購入して自分のものとして所有できたとしても、NFTの画像データはあくまで外部サービスに依存した形でのNFTの所有になってしまうため、NFTを自分のコントロール下として所有しているという状態だとはなかなかいえないでしょう。
しかし、タイプ2のNFTであれば、すべてがブロックチェーン上にデータとして存在しているので、NFTを購入して自分のものとして所有した瞬間から、どの外部サービスからの影響もまったく受けずに、所有している状態になっているのではないかと思います。
どちらのタイプが正しいか、どちらのタイプがより理想的な状態かは人によって異なると思いますが、NFTを購入する際のひとつの指標として考えてみるのはおもしろいかもしれません。

トランザクションのスケーリング問題
その人気さがゆえに、イーサリアム上での取引件数がかなり多くなってしまい、ネットワークの手数料が高騰してしまうというトランザクションスケーリングの問題が顕在化しつつあります。
たとえば、2020年5月ごろからトランザクション手数料が徐々に上がっていき、現在に至るまでかなり乱高下を繰り返しながら推移していることがわかると思います。
一時はネットワークのトランザクション手数料が高騰してしまい、1回の取引を行うのに当時のイーサリアムレートで数千円~数万円ぐらいの手数料を支払わないと、イーサリアム上で取引ができないという状況もありました。
つまり、イーサリアム上でさまざまなDeFiや、NFTマーケットプライスなどのDecentralized applicationsといわれる分散型アプリエーションのサービス取引が増えてくるにつれて、ネットワーク上の取引件数が上がっていき、それに伴いトランザクション手数料が徐々に高騰していって、それがイーサリアムのネットワーク上で行われるすべての取引に対して影響を及ぼしてくるということになります。
そういったトランザクションのスケーラビリティ問題に対して、2016年ごろから様々な企業や団体などが技術研究を行っており、Ethereum Layer2と呼ばれる技術が近年注目を集めています。
このLayer2というものは、イーサリアムブロックチェーンとは別に、ある外部環境でトランザクションを安全に処理するための技術的な総称のことをいいます。
イーサリアムブロックチェーンのメイン処理機能を1層目としてLayer1と呼び、それ以外の処理は、2層目で行うという意味合いから、Layer2とよばれています。
Layer2の目的は、トランザクションを処理する機能をLayer2という枠組みで別にも蹴ることで、メイン処理となるLayer1で処理するトランザクション量を減らし、トランザクションのスケーラビリティ問題を解決しようとする技術です。
このようなトランザクションのスケーラビリティの問題解決に対する研究開発は盛んに行われている一方で、このLayer2を使った技術を様々なイーサリアムプロジェクトですぐに利用できるような状況にはまだなっていません。
理由としては、ブロックチェーンとは異なる外部環境となるLayer2において、トランザクションの安全性をどのように担保するかというセキュリティの側面にまだまだ課題があり、その課題を解決するには技術的に高いハードルを越える必要があるからです。
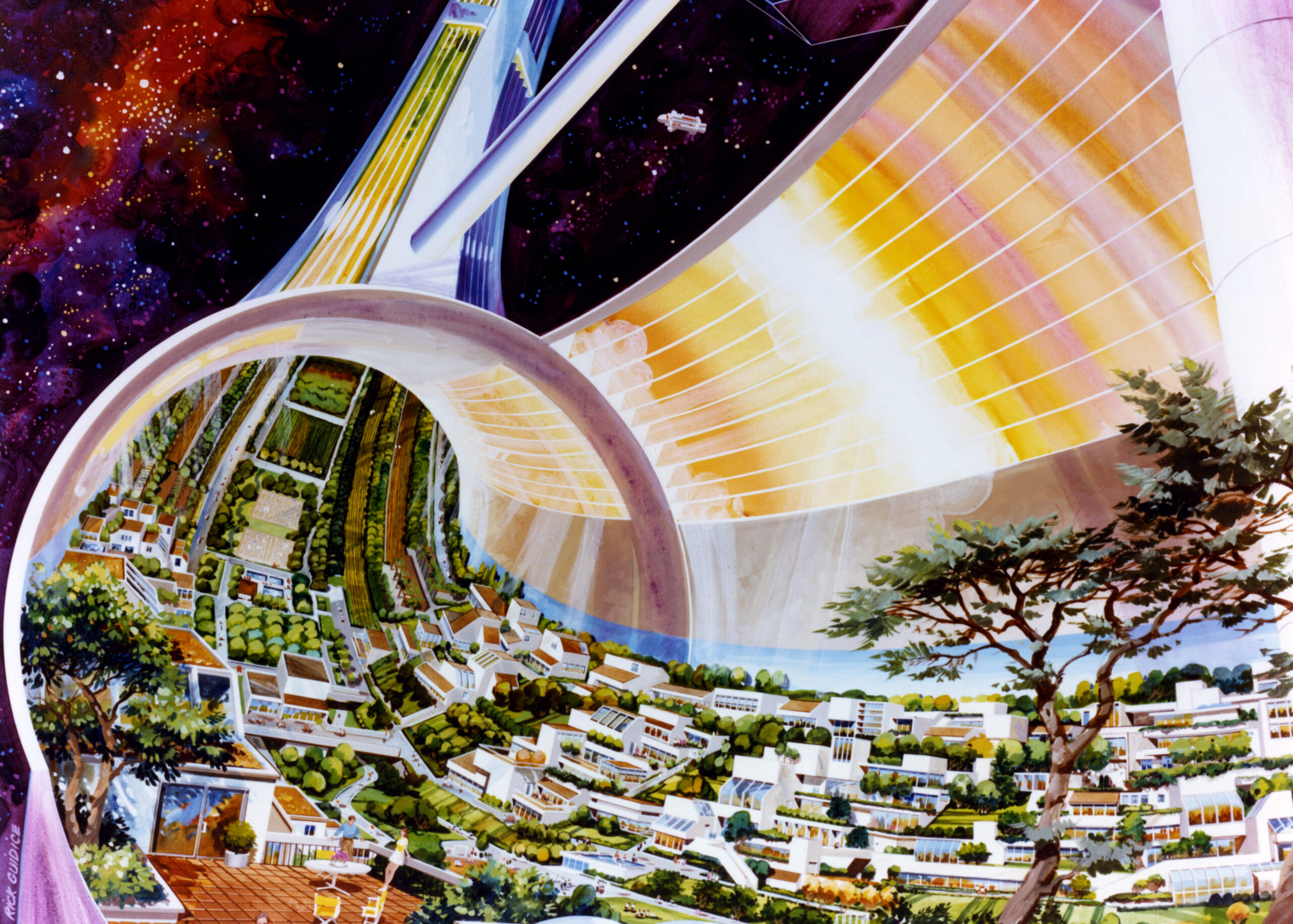
NFTマーケットプレイス間の互換性の問題
スマートコントラクトにはそれぞれのNFTのマーケットプレイスに必要な独自の機能が備わっていて、とたえば、NFTマーケットプレイス内でNFTを新たに発行する機能や、NFTの売買手数料の比率や仕組みなどがプログラムされています。
これらのプログラムは、それぞれのNFTマーケットプレイスで異なっていることから、たとえば、NFTを発行する際のNFTの規格が異なっていたり、NFTの売買手数料の比率がNFTマーケットプレイス間で異なっていたりします。
これは、NFTマーケットプレイスの共通インターフェースとなるような規格がそもそも存在しないため、互換性の問題はどうしても出てきてしまう課題です。
互換性がないということは、NFT自体により流動性を出すことを難しくしてしまうため、NFTを発行するクリエイターにとっては、発行したNFTをより多くのユーザーに使用してもらう機会、ユーザーにとってはNFTをより多くのマーケットプレイスで取引するための機会、NFTマーケットプレイスの運営体にとってはNFTの取り扱い数や売買機会が奪われるので収益機会が失われてしまったりします。
そのため、NFTマーケットプレイス間の互換性がないという問題は、NFTマーケットプレイスの運営体、NFT発行者、ユーザーのどの視点で考えてもメリットがあるものではありません。したがって、NFTマーケットプレイス間の互換性の解決が、今後のNFTの発展に必要になってくる可能性が高いのです。

環境問題への配慮
NFTに限らず、ビットコインやイーサリアムなど、ブロックチェーン技術を活用した市場が盛り上がる一方で、マイニングと呼ばれる多大な電力消費が環境に対して大きな影響を及ぼしていると、環境への配慮について一部で問題視されています。
たとえば、ケンブリッジ大学が公表しているビットコインの消費電力に関する指標によると、ビットコインの年間推定消費電力は、82.18TWhとなっています。
これは、世界子に別年間消費電力量ランキングと比較してみると、世界第34位のアラブ首長国連邦と並ぶ電力消費をしていることになります。
また、ビットコインに限らず、イーサリアムもビットコインと同様に多大な計算を行っているため、ビットコインほどではないにしても多大な電力を消費しています。
このような環境問題については、環境配慮への感度が高いコンテンツ制作者やクリエイター、ユーザーなどから、懸念の声が年々上がってきています。
ビットコインやイーサリアムなどが多大な電力消費を行う理由は、PoWお呼ばれる多大な計算に基づくコンセンサス・アルゴリズムによって、ブロック生成を行っているからです。この混戦猿・アルゴリズムというのは、PoW以外にも複数存在していて、その中で注目すべきコンセンサス・アルゴリズムは、PoSと呼ばれるものです。
したがって、PoWよりも、PoSの方がより計算量が少ない状態でブロック生成が可能になるので、ブロックチェーンネットワークを維持するために使われる消費電力が少なくすることが可能となり、環境に対して与える負荷を軽減させる可能性があります。
現在のイーサリアムは、イーサリアム1.0と呼ばれるPoWを中心としたブロックチェーンシステムで稼働していますが、将来は、イーサリアム2.0という全く新しいPoS稼働するブロックチェーンシステムへと移行することを発表しています。
したがって、イーサリアムが将来にわたり環境に対して与える負荷が軽減されるということは、イーサリアム上で取引されるNFTが環境へ与える影響も、結果的に軽減される可能性があります。

NFTの普及には技術的課題の解決が必須
ここで取り上げた以外にもまだまだ技術的な課題はたくさんありますが、特に重要と思われる4つの技術的な課題に絞って見てきました。どの課題も解決するには多くの時間を要しますが、それらの課題を解決した際に得られる恩恵はかなり大きなものばかりですし、NFTを今後もっとより多くの人に普及させていくには、これらの課題を必ず解決していく必要があります。
NFTは、2020年ごろから徐々に取引高が多くなっていき、2021年8月には、老舗NFTマーケットプレイスであるOpenSeaの過去30日間の取引高が1340億円に膨れ上がるまでにNFT市場が過熱しました。
特に、その取引高が多いのがアート分野で、今年3月には、デジタルアーティストBeepleのデジタルアートコラージュが日本円で約76億円で落札されたことで話題を呼び市場を牽引していきました。
デジタルアートの分野においては、NFTアートというまったく新しい技術によって、新しいコンテンツや新しい概念がいま広がっています。
そうなった場合、ここで取り上げたNFTの課題に目を向けてみると、まだまだ一般市民が気楽に使えるような仕組みやサービス設計にはなっていないので、もっとより多くの人がNFTを気楽に使えたり、またより多くの分野でNFTが使われて、グローバルレベルで取引が可能になったりするためには、やはりここで取り上げた技術的な課題の解決が重要なファクターになってくるのではないかと考えています。