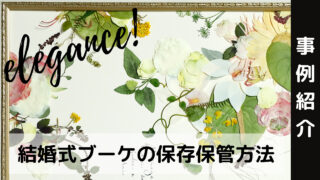貸借対照表とは、ある一定時点において企業がその活動に利用している資金がどのような源泉から調達され、その資金がどのように運用されているのか、すなわち資金の調達源泉とその運用形態を対照表示した計算書です。この意味で、貸借対照表は企業の財政状態を表示する計算書であるといわれています。
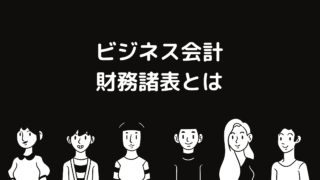
貸借対照表の仕組み
貸借対照表とは
貸借対照表(Balance sheet)は、ある一定時点で企業がその活動に利用している資金がどのような源泉から調達され、その資金がどのように運用されているのか、すなわち資金の調達源泉とその運用形態を対照表示した計算書です。
貸借対照表の右側には資金の調達源泉である負債と純資産が、左側にはその資金の運用形態である資産が表示されています。
このような意味で、貸借対照表は企業の財政状態を表しているといわれています。
また、右側の資金の調達源泉は負債と純資産の2つに分けて示されています。負債はいずれ返済が必要なもので、他人資本とも呼ばれます。
これに対して純資産は原則として返済する必要がなく、自己資本とも呼ばれており、このような相違を反映して2つに区分して表示されています。
貸借対照表は企業の同一の資金について源泉と運用の双方の視点から表現するものであるところから、左右の合計が等しくなっており、必ず「資産合計=負債合計+純資産合計」になります。
貸借対照表の様式
貸借対照表の様式には勘定式と報告式の2つの種類があります。勘定式の貸借対照表は前述したように資産を左側に、負債と純資産を右側に対象表示したものです。
報告式は、資産、負債、純資産の順に配列する方法です。
勘定式の貸借対照表は、主に株主向けの報告書などで見かけます。これに対して報告式の貸借対照表は一般向けの報告書である有価証券報告書などで利用されています。
流動項目と固定項目の区別
貸借対照表では、資産は流動資産、固定資産および繰延資産に、負債は流動負債と固定負債に区分して表示されます。
資金の運用形態としての資産は、運用している資金の回収が短期になされる部分とそうでない部分(固定資産)とに分類し、資金の調達源泉としての負債については、企業が調達した資金の返済が迫っている部分(流動負債)とそうでない部分(固定負債)に分類することによって、貸借対照表において一層多くの情報を提供するための工夫をしています。
資産と負債を流動と固定に分類する基準として「正常営業循環基準」と「ワンイヤールール」があります。
資産を流動資産と固定資産に分類する際には、まず正常営業循環基準を適用し、この原則で流動資産に分類されなかった項目についてはさらにワンイヤールールを適用し、該当するものは流動資産に分類されます。
また、負債についても同様に分類が行われます。
仕入れ→製造→販売に至る営業の循環を1つのサイクルと考え、このサイクルの過程にある項目を流動資産ないし流動負債とする。それ以外の項目についてはワンイヤールールを適用する
決算日の翌日から起算して1年以内に履行期日の到来する債権および債務については流動資産ないし流動負債とし、それ以外は固定資産ないし固定負債とする基準
配列の方法
一般的な企業ではまず、流動資産と固定資産、そして流動負債と固定負債に分類し、流動項目を先に配列する流動性配列法が採用されます。
なお、電力業、ガス業のように、流動資産より固定資産、流動負債より固定負債を先に記載する固定制配列法を採用する業種もあります。
流動性配列法の場合、それぞれの項目について流動性の高い順に配列します。たとえば、流動資産はこのように配列します。
| 現金及び預金 |
| 受取手形 |
| 売掛金 |
| 有価証券 |
| 棚卸資産 |
固定制配列法を採用する場合でも、流動資産や流動負債を構成する項目自体は流動性の高い順に配列されます。
総額主義の原則
資産・負債および純資産は総額によって表示することが原則です。資産の項目と負債の項目または純資産の項目とを相殺することによって、その全部または一部を貸借対照表から除外してはならないとされています。これを総額主義の原則といいます。
たとえば、貸付金と借入金の相殺消去を行うと実際の債権や債務の存在がわからなくなるため、資金の調達源泉と運用形態の関係を知ることができず、ひいては会社の財政状態を正しく理解できないことになります。
ただし、貸借対照表の見やすさや一覧性を高めるために、売掛金と貸倒引当金を相殺して、残高のみを表示することも認められています。
重要性の原則
貸借対照表上、その項目の性質や金額について重要性が乏しい場合は簡潔に示すことが認められています。これを重要性の原則といいます。
資産および負債の流動・固定の区分基準として正常営業循環基準とワンイヤールールがあり、正常営業循環基準が優先して適用される。資産の項目と負債の項目または純資産の項目とを相殺することによって、その全部または一部を貸借対照表から除外してはならないとする総額主義の原則や、その項目の性質や金額について重要性が低い場合には簡潔に示すことができるとする重要性の原則が適用される。
貸借対照表上の項目の配列法には流動性配列法と固定制配列法があり、特定の業種を除き、わが国では原則として、流動性配列法が採用されています。流動性配列法においては、流動資産に関して流動性の高いものから低いものへ順に並べられます。
資産の概念と分類
資産とは、将来において企業に経済的利益をもたらすと期待されるもので、貨幣額で示すことが可能なものをいいます。
企業が資産を保有するのはそれが経済的利益を生み出すことを期待しているからで、有形であるか無形であるかは問いません。
また、当該企業に経済的利益をもたらすものとは、資産を有している企業が排他的にその経済的利益を受け取ることができることを意味し、経済的利益を生み出すと期待されないものは資産としては扱われません。
さらに、経済活動を統一的に把握する尺度として貨幣が利用され、貨幣額で示すことができないものは資産として扱われません。
資産には、現金や預金、貸付金、土地、建物などが含まれますが、前述のとおり、資産は3つに分類され、流動資産と固定資産に分類するために、正常営業循環基準とワンイヤールールが適用されます。
資産の金額
資産に付されている金額の決定基準は、資産の種類により異なります。
| 資産の種類 | 資産の内容 | 原則的評価基準 |
| 事業用資産 | 清算・販売など、本来の企業活動に利用される資産 | 取得原価 |
| 金融資産 | 余剰資金の運用のために保有される資産 | 時価 |
取得原価
取得原価とは資産の取得のために支出した金額です。
たとえば、資産を購入した場合、購入価額に不随費用(買入手数料、引取費用、関税など)を加えた金額が取得原価となり、製品などを製造した場合、適正な原価計算基準に従って計算された製造原価(材料費、労務費および経費の合計)がその取得原価となります。
取得原価は、支出額を利用するために、客観的で信頼性が高いという長所があります。しかし、その金額は過去の取引の結果であって、時が経過するにつれて資産価額が実態からかけ離れてしまうという短所があります。
建物や土地のような事業用資産については、取得原価が原則的な評価基準となります。
その理由は、事業用資産を保有する目的は本来の企業の活動に利用するためであり、その価格の変動が会社にとって大きな意味を持たず、その本来の目的のために取得原価で据え置くことが適切だからです。
時価
時価とは期末時点での資産の評価額(たとえば市場価格)のことです。
時価は、期末時点の最新の資産の価格を反映できるという長所があります。
しかし、現実に取引をしたわけではない市場価格などを利用するために客観性に欠け、取得時より値上がりした場合に資金的裏付けに欠ける未実現の評価益が計上されるという欠点があります。
売買の目的とした有価証券のような金融資産については、時価が原則的な評価方法となります。その理由は、金融資産を保有する目的は余剰資金の運用であり、原則として、その資産の売買を繰り返すことによって達成されます。
その売却は容易で、期末時点での時価(市場価格)で誰でも売買することが可能であるため、取得原価よりも時価で評価することが適切だからです。
流動資産
流動資産は以下のようにまとめることができます。
なお、受取手形や売掛金などの債権はその一部が回収不能になる場合があり、これを貸倒れといいます。
このような貸倒れの可能性を決算時に過去の実績にもとづいて見積もりますが、この見積額を貸倒引当金といい、受取手形や売掛金から控除する形式で表示したり、その控除後の金額で表示したりします。
流動資産に含まれる有価証券は、時価の変動により利益を得ることを目的として保有されるもの(売買目的有価証券)と決算日の翌日から起算して1年以内に満期の到来する他社の社債などに限定されており、それ以外の有価証券は原則として固定資産に分類されます。
| 項目 | 説明 |
| 現金及び預金 | 通貨、金融機関などで発行される通貨代用証券のほか、各種の預金・貯金、郵便貯金など |
| 受取手形 | 取引先との通常の取引にもとづいて受け取った手形債権 |
| 売掛金 | 得意先との通常の取引にもとづいて生じた営業上の未収入金。企業の主たる営業活動以外の取引と区別が必要 |
| 有価証券 | 他社の株式、国債、地方債、他社の社債などのうち、売買目的有価証券および決算日の翌日から起算して1年以内の満期の到来する国債・地方債・他社の社債など |
| 棚卸資産 | 販売する目的で保有している財貨で、商品・製品・原材料・仕掛品・貯蔵品など。棚卸資産は商品、製品などに分類して示される場合も多く、貸借対照表上に商品のみが示される場合は商業、製品や仕掛品などが示されている場合は製造業であると判断することができる |
| 前渡金 | 商品・原材料などの購入代金を先払いしたときの金額 |
| 前払い費用 | 一定の契約に従って、継続してサービスの提供を受ける場合の代金の前払い分 |
| 繰延税金資産 | 税効果会計の適用によって生じる繰延税金資産のうち、翌期に解消されると見込まれるもの |
| 未収収益 | 金銭の貸付けや不動産の賃貸で、一定の契約に従って継続してサービスの提供を行う場合に、すでに提供したサービスに対していまだその対価の支払いを受けていない額 |
| 短期貸付金 | 決算日の翌日から起算して1年以内に期限の到来する貸付金 |
| 未収入金 | 土地や有価証券の売却など、会社の主たる営業活動以外の取引から生じた未収額 |
有価証券の分類と表示区分
| 有価証券の分類 | 具体例 | 表示区分 |
| 売買目的有価証券 | 値上がりによる儲けを得るために保有している市場性のある有価証券 | 流動資産 |
| 満期保有目的の債権 | 満期まで保有することを意図した他社の社債など | 固定資産 |
注記表と付属明細表
注記表は会社法によって作成が義務付けられています。注記表には、次のようなものがあります。
① 貸倒引当金・減価償却累計額の科目別金額のように、財務諸表に示されている科目・金額の内訳を示すもの
② 有価証券や棚卸資産等の評価基準または評価方法等に関する会計方針の開示などのように、財務諸表に示されている科目の金額の算定基礎を明示するもの
たとえば、②の有価証券の評価基準および評価方法については、次のような記載が行われます。
1:有価証券の評価基準および評価方法
(1)子会社株式および関連会社株式:移動平均法による原価法により評価しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの:期末日の市場価格等に基づく時価法により評価している
時価のないもの:移動平均法により評価している
付属明細表は金融商品取引法によってその作成が義務付けられています。付属明細表には次のようなものがあります。
① 有形固定資産明細表、引当金明細表、借入金明細表などのように、主な項目についてその金額の増減を明らかにするもの
② 有価証券明細表、社債明細表などのように、主な項目についてその内容と金額を種類別に増減を明らかにしたもの。
有価証券のうち、満期保有目的の債権(満期が決算日から起算して1年以内に到来するものを除く)、子会社・関連会社株式、その他有価証券(ただし、満期が決算日の翌日から起算して1年以内に到来するものを除く)は固定資産に分類される
棚卸資産は正常営業循環基準によって流動資産として分類される
固定資産
固定資産の意義と分類
固定資産は企業が1年を超えて長期的に利用するために保有する資産、および現金となるまでの期間が決算日の翌日から起算して1年を超える金融資産を総称します。
さらに、固定資産はその形態的な特徴に従って、以下のように分類されます。
| 固定資産の分類 | 主な項目 |
| 有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械装置、車両運搬具、工具器具備品、建設仮勘定など |
| 無形固定資産 | 特許権、商標権、ソフトウェア、のれんなど |
| 投資その他の資産 | 投資有価証券、長期貸付金、長期前払費用など |
有形固定資産
有形固定資産とは、物理的な形態を持っている固定資産で以下のような項目があります。
| 項目 | 説明 |
| 建物 | 店舗、工場、事務所などの建造物 |
| 構築物 | 橋、下水道、道路など、土地に定着した土木設備や工作物 |
| 機械装置 | 各種の機械および装置と不随する設備 |
| 車両運搬具 | 鉄道車両、自動車などの陸上運搬具 |
| 工具器具備品 | 各種の工作用工具、コンピュータ、コピー機、ショーケースなどで耐用年数が1年以上、金額が一定以上のもの |
| 土地 | 自己所有の土地 |
| 建設仮勘定 | 建物などの有形固定資産の建設に際して、建設業者に支払った金銭など、工事の完了までに要するすべての支出を集計するための項目 |
有形固定資産は、土地と建設仮勘定を除き、使用や時の経過、技術革新による時代遅れなどを原因として、その価値が下落します。
その価値の下落を減価といいますが、その減価を直接的に把握するのは困難です。
そのため、あらかじめ定められた一定の方法に従って、その取得原価を利用期間にわたって計画的・規則的に各期間の費用として配分します。これを減価償却といいます。
この計算をするために、取得原価、耐用年数および残存価値の3つの計算要素を利用します。
取得原価は既に解説したように、購入した場合にはその購入価格に買入手数料、引取運賃などの不随費用を加算した金額です。
耐用年数は使用可能年数をいいます。
残存価値を耐用年数到来時に予想されるその資産の処分可能価額(売却価額など)です。
一例として、価値の下落を毎期一定とする定額法では、毎期の原価を把握します。
定額法による減価償却費=(取得原価ー残存価額)÷耐用年数
また、毎期の減価償却費の合計額を減価償却累計額といいます。
この定額法以外にも、初期の減価償却費は大きく、次第に小さくなる定率法があります。
貸借対照表上、有形固定資産の取得原価と減価償却累計額は次のように表示されます。
例示1:有形固定資産から控除する形式で示す方法
| 建物 | 1000 | |
| 建物原価償却累計額 | 200 | 800 |
例示2:減価償却累計額の控除後の金額で示し注記する方法
| 建物 | 800 |
無形固定資産
固定資産のうち有形固定資産のような物理的形態を持たないもので、企業の収益獲得に貢献するものを無形固定資産といいます。
無形固定資産は以下のようなものが含まれます。
| 項目 | 説明 |
| のれん | 他社から営業を譲り受けた際に、相手方に対して対価として支払われた金額が受け入れた純資産の額を超える額で、それは相手方が有していた超過収益力に対する対価を意味する |
| 特許権 | 自然法則を利用した技術的発明を独占的に利用できる権利 |
| 商標権 | 文字や図形からなる商品の商標を独占的に使用する権利 |
| ソフトウェア | コンピュータを作動させるソフトウェアの制作に要した費用やバージョンアップ費用など |
なお、有形固定資産の場合と同様に、無形固定資産の取得原価は各会計期間に配分され、費用として計上されます。これを償却といいます。
また、費用となった金額は取得原価から直接控除され、その残高のみが貸借対照表に示されます。
投資その他の資産
投資その他の資産は他社を支配したり、取引関係を維持したりするための資産、長期的余裕資産の運用のための資産などであり、以下のような項目が含まれます。
| 項目 | 説明 |
| 投資有価証券 | 売買目的有価証券および決算日の翌日から起算して1年以内に満期の到来する国債・地方債・他社の社債以外の有価証券 |
| 長期貸付金 | 決算日の翌日から起算して1年を超えて期限が到来する貸付金 |
| 長期前払費用 | 一定の契約に従って継続してサービスの提供を受ける場合の代金の前払分で、決算日の翌日から起算して1年を超える期間を経て費用となるもの |
| 繰延税金資産 | 税効果会計の適用によって生じる繰延税金資産のうち、翌期を超えて解消されると見込まれるもの |
固定資産は有形固定資産、無形固定資産および投資その他資産に分類され、無形固定資産には特許権などが、投資その他の資産には長期貸付金などがそれぞれ含まれる。
減価償却の方法の1つである定額法は、取得原価から残存価額を控除した額を耐用年数にわたって毎期均等に減価償却費として配分する方法である。
繰延資産
繰延資産は、既に対価の支払いが完了しているかあるいは支払い義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現すると期待されるため、その支出額を効果がおよぶ将来の期間に費用として合理的に配分するために、経過的に貸借対照表に資産として計上された項目です。
これらの支出は発生時に費用処理するのが原則ですが、上記の理由から貸借対照表に資産として計上することが認められるので、特殊な資産といえます。
| 項目 | 説明 |
| 創立費 | 会社を設立するために要した費用 |
| 開業費 | 会社の設立後、営業を開始するまでの開業準備のために支出した費用 |
| 開発費 | 新技術、新経営組織の採用、資源の開発や市場の開拓のために特別に支出した費用 |
繰延資産とは、すでに対価の支払いが完了しているかあるいは支払い義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待されるため、資産として計上される項目であり、創立費や開発費などが含まれる。
負債とは
負債の概念と分類
負債とは企業が負うべき経済的負担で、貨幣額で示すことができるものをいいます。すなわり、負債は、企業にとって金銭あるいは財貨またはサービスを提供する義務を意味し、その金額が貨幣額によって示されるもので、買掛金や借入金がその例です。
資産と同様、負債も正常営業循環基準とワンイヤールールに従って、流動負債と固定負債に分類されます。負債を流動負債と固定負債に分類する際に、まず正常営業循環基準を適用し、この原則で流動負債に分類されなかった項目についてはさらにワンイヤールールを適用し、該当するものは流動負債に分類されます。
流動負債には以下の項目が含まれます。
| 項目 | 説明 |
| 支払手形 | 取引先との通常の取引にもとづいた支払義務のある手形債務 |
| 買掛金 | 仕入れ先との通常の取引にもとづいて生じた営業上の未払金。企業の主たる営業活動以外の取引から生じた未払い金とは区別が必要 |
| 短期借入金 | 決算日の翌日から起算して1年以内に返済期限が到来する借入金 |
| 未払い金 | 有価証券や固定資産の購入など、会社の主たる営業活動以外の取引から生じた未払い額 |
| 未払い法人税等 | 法人税、住民税、事業税の未払額 |
| 繰延税金負債 | 税効果会計の適用により生じる繰延税金負債のうち、翌期に解消されると見込まれるもの |
| 前受け金 | 商品やサービスを提供していない時点で受け取った代金 |
| 預り金 | 源泉徴収した従業員の所得税預かり金など、第三者から一時的に預かった金額 |
| 前受収益 | 一定の契約に従ってサービスの提供を行う場合に、サービスをいまだ提供していないにもかかわらず翌期分の対価を先に受け取った場合の前受分 |
| 引当金 | 将来、会社に支出を強いる負担について、その原因が当期以前に存在する場合に限定して、貸借対照表に記載されるもの。 |
| 社債 | 有価証券としての社債券を自社が発行し資金調達を行ったことから生じる債務のうち、決算日の翌日から起算して1年以内に償還期日が到来するもの |
固定負債
| 項目 | 説明 |
| 社債 | 有価証券としての社債券を自社が発行し資金調達を行ったことから生じる債務のうち、決算日の翌日から起算して1年を超えて償還期日が到来するもの |
| 長期借入金 | 決算日の翌日から起算して1年を超えて返済期限が設定されている借入金 |
| 繰延税金負債 | 税効果会計の適用により生じる繰延税金負債のうち、翌期を超えて解消されると見込まれるもの |
| 引当金 | 流動負債で取り上げた引当金と同様 |
将来、会社に支出を強いる負担について、その原因が当期以前に存在する場合に限定して、貸借対照表に表示されるものを引当金という。表示される条件として、次のものが要求される。将来の特定の費用または損失に関するものであること、その発生が当期以前の出来事に起因していること、その発生の可能性が高いこと、その額の合理的な見積もりができること
純資産とは
純資産の概念と分類
純資産とは資産と負債の差額をいいます。
純資産は、その発生源泉を重視し、株主資本、強化・換算差額等および新株予約券に分類されます。
株主資本
株主資本は、株主が出資をした部分(払込資本、会社の元本に相当する部分)とその元本を元手にしてかいしゃが増やした部分(留保利益あるいは稼得利益。株主に分配されずに会社に留保されている部分)から構成されています。そして、資本金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式の4つに区分表示されます。
株主からの出資額は原則として資本金に組み入れられることになっていますが、2分の1を超えない額は資本金に組み入れず、資本準備金とすることができます。これらが払込資本です。
また、利益準備金は、配当額の1/10を先の資本準備金の額とあわせて資本金の4分の1に達するまで積み立てるものです。そして、利益剰余金は利益を源泉として会社に留保された留保利益です。
なお、株式会社が発行済みの自社株式を買い戻し、これを保有している場合、その株式を自己株式といいます。自己株式の取得は株主に対する会社財産の払い戻しと考えられ、期末に保有する自己株式は、株主資本からの控除項目になります。
評価・換算差額等
評価・換算差額等には、その他有価証券評価差額金のように、資産または負債を時価で評価するが、評価差額を登記の損益計算書で認識しない場合に生じる項目があります。
評価・換算差額等には、以下のような項目があります。
| 項目 | 説明 |
| その他有価証券評価差額金 | その他有価証券を時価評価した際の取得原価と時価との差額であり、損益計算書に評価損益を計上するのではなく、貸借対照表に直接計上される |
| 土地再評価差額金 | 土地の再評価に関する法律に従って企業が事業用の土地を再評価した際に生じた取得原価と時価との差額であり、評価益は損益計算書には計上されず、貸借対照表に直接計上される |
新株予約権
新株予約権とは、新株予約権を有する者が会社に対して一定期間、あらかじめ定めた一定の価額で株式の交付を請求できる権利です。
会計上は、その権利を割り当てられた者が権利を行使したとき、または払込期日までに払い込んだときその金額を新株予約権として表示します。現在の株主からの払込資本とは発生源泉が異なるので、区別して記載されます。
純資産の部は、それが生じた源泉によって、株主が出資した部分である株主資本、特定の資産・負債についてその取得原価と時価による評価額との差額である評価・換算差額等、将来株主となることを前提に会社が受け入れた金額である新株予約権に分類される。また、株主資本は株主が払い込んだ部分である払込資本とその元本にして会社が増やした部分である留保利益から構成される。
株式会社が発行済の自社株式を買い戻し、これを保有している場合、この株式を自己株式という。これは一定の条件下で自由に取得することができるが、この株式取得は株主に対する会社財産の払い戻しと考えられ、株主資本の末尾に一括して控除する形式で表示される。